40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
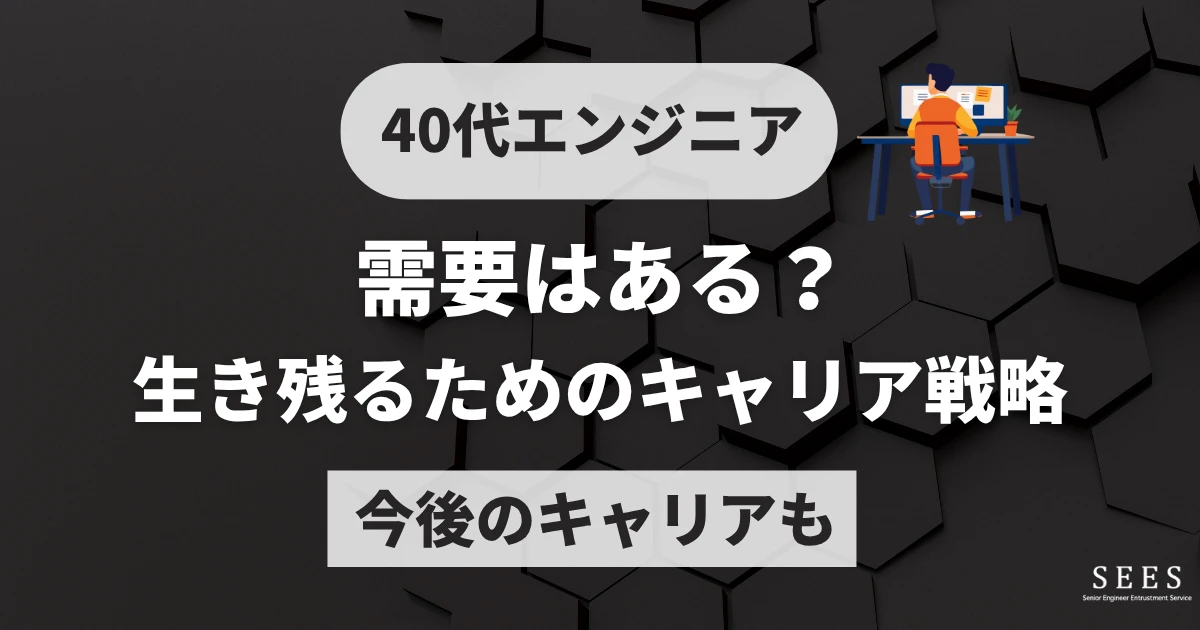
40代はキャリアの見直し時期でもあり、「自分は需要があるのか」や「このままエンジニアを続けられるのか」と悩むことも少なくありません。本記事では、40代エンジニアの需要について、キャリア戦略やキャリアパスなどを交えつつ解説します。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
エンジニアには「35歳定年説」といわれる言葉があり、40代を迎える頃になると「この先も需要はあるのか」や「自分は生き残れるのか」と不安を感じる方も少なくありません。とはいえ、実際には35歳を過ぎても現場で活躍しているエンジニアは多く、「35歳定年説」はあくまでも「説」にすぎないといえます。
ただし、近年は20〜30代でエンジニアを目指す方も増えているため、40代になるにあたり、自身のキャリアを見つめ直すタイミングでもあります。長く活躍し続けるには、現在の立ち位置や今後の選択肢を理解しておくことが大切です。
本記事では、40代エンジニアの需要について、キャリア戦略やキャリアパスなどを交えつつ解説します。

近年、エンジニアをはじめ多くの業界では人手不足に関する悩みを抱えているケースが少なくありません。成り手こそ増えつつあるものの、若手人材が多く、現場で即戦力となる中堅層やベテランの人材がいまだに少ないのが現状です。
とくに、経験を積んだ40代エンジニアには、活動をはじめて数年では身につけられないスキルが備わっています。今後のエンジニア人生で需要ある存在となるためにも、若手にはない強みを活かして活動することが大切です。
ここでは、40代エンジニアに需要がある理由について、以下4点を解説します。
40代エンジニアで長期にわたって多彩な案件に携わった方は、言語やフレームワークはもちろん、業務フローまで深く理解ができています。このような経験の積み重ねは、要件定義の段階で抜けやミスを防ぎ、どの技術を使用すれば良いか迷わず判断できるようになります。
また、障害分析の再現性が高いため、未知の課題にも過去の知見を活かして的確な対応ができる点も大きな強みです。
このような実力は短期間では身につかず、採用担当が40代を即戦力として評価される理由といえるでしょう。
40代エンジニアは、プログラミングのスキルはもちろん、設計や実装、運用までの工程を幅広く経験しているケースが少なくありません。このように経験が豊富であると、各工程を横断して業務に対応できるため、貴重な存在といえます。
また、仕様変更や追加要件が発生しても、過去の失敗例を踏まえながら影響度を定量化できるため、成果物の完成度の向上にも貢献できるでしょう。
このような横断力は経験数の少ない若手には難しく、プロジェクト全体の保険として重宝されます。
40代までに多くのトラブルを経験してきたエンジニアは、原因を整理しながら冷静に問題を解決する力が身についているケースが多くあります。そのため、再発防止まで見据えた提案ができ、品質改善のサイクルを早く回すことが可能です。
また、数値や根拠をもとに要点を伝える力にも優れているため、経営層や非技術部門とのやり取りも円滑に進みます。
結果として、技術チームは集中して開発でき、関係部門や経営層もプロジェクト価値を理解しやすくなるという好循環が生まれるでしょう。
現場経験が豊富な40代エンジニアは、作業工程を整理しながらプロジェクト全体を管理する力に長けており、プロジェクトマネージャーとしても活躍できます。実務も人員の調整や対応範囲の見直しを的確におこない、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
現在はプログラミングができる人材が増えている一方で、現場をまとめられるマネジメント人材は依然として不足しています。そのため、開発と管理の両方を担える40代は、今後も長く求められる存在といえるでしょう。

エンジニアの年収は、経験や年数を積むほど高くなる傾向があります。とくに、40代後半は年代別に見ても年収が高く、平均約738万円と日本国内の平均年収よりも高いといえます。
なお、年収のピークは50代後半まで続き、60代以降になると下降傾向にあるため、定年後もエンジニアとして活動する方はこの点をおさえておきましょう。
以下に、エンジニアの年代別年収をまとめているため、40代付近の年収が気になる方は参考にしてください。
| 年齢 | 年収 |
| 35〜39歳 | 631.35万円 |
| 40〜44歳 | 650.52万円 |
| 45〜49歳 | 737.98万円 |
| 50〜54歳 | 695.43万円 |
| 55〜59歳 | 730.76万円 |
| 60〜64歳 | 557.06万円 |
| 65〜69歳 | 607.68万円 |
| 70歳〜 | 354.4万円 |

エンジニアをはじめどのような職業であっても、長い期間一線で活躍し続けるのは難しいといえます。とくに、エンジニアは新しい技術が登場するスピードが早いため、ただ日々の業務をこなすだけでは周りのエンジニアについていけません。
エンジニアとしての市場価値を上げ、常に必要とされる存在であり続けるためにも、戦略を立てて行動を起こすことが大切です。
ここでは、40代エンジニアが生き残るためのキャリア戦略について、以下7点を解説します。
エンジニア業界は、常にトレンドが変化し続けるため、市場価値の高い人材になるためには学び続ける必要があります。とくに近年は、AI関連の技術の需要が高く、PythonやGoなどを使いこなせると成長分野で活躍することが可能です。
もちろん、自分のスキルを磨くことも必要ではあるものの、業務の幅を広げるためには新しい言語への挑戦も欠かせません。
複数の言語を扱えるようになれば、市場の流れが変わっても柔軟に対応でき、自分の可能性をさらに広げることにつながります。
人材不足に対応するため新人教育が進み、プログラミングができるエンジニアは今後さらに増えていきます。そうなると、技術だけでは年収や裁量に限界が生じるため、立場を1段上げてマネジメントにも関わることが重要です。
とくに、40代までエンジニアとして経験を積むと、全体を俯瞰して状況を把握できるため、リーダーとしての適性を備えているケースも多くあります。
現在はマネジメント人材が不足しているため、地位を確立するうえでも早めの準備と行動が求められます。
副業は、業務の幅を広げて市場価値を高めるための有効な手段です。とくに、正社員として働いている場合は、副業をはじめることで新しい分野にも手軽に挑戦できます。
最新トレンドの技術を低いリスクで試しながら収入を増やせるため、スキルアップと生活面の両方に良い影響を与えます。
さらに、副業で得た知識や経験は本業にも活かしやすく、成果として評価されることもあるため、キャリア全体の底上げにもつながるでしょう。
エンジニアは、技術を使って課題を特定し解決することが本質です。そのため、技術だけでなく、さまざまな業界が抱える業務課題への理解も欠かせません。
たとえば、異業界のセミナーや交流会に参加し、顧客のビジネスモデルを知ることで、課題の発見や提案の質が高まるでしょう。また、多角的な視点を持つエンジニアは企画段階から頼られる存在になりやすく、市場価値も上がっていきます。
業務内外を問わず、異業種の方と関わりながら知見を広げておくことは、キャリア形成にも大きく影響します。
40代は転職機会が20〜30代より減る傾向があり、少ない機会に備えておくことが欠かせません。
とくに、長年の経験を積んできたエンジニアほど、以前作成したポートフォリオや職務経歴書が更新されないまま放置されているケースが多く見られます。常に最新版に保ち、チャンス到来時にすぐに動けるようにしておくことが大切です。
転職だけでなく副業や登壇依頼など、あらゆる機会を逃さず動ける状態を整えておきましょう。
エンジニアとして転職や案件を獲得する際は、業務に活かせる知識やスキルの証明が重要です。そこで役立つのが「資格」です。
資格を保有していることで、自分の知識やスキルを客観的に示すことができ、顧客や採用担当者からの信頼にもつながります。また、すでに身につけている内容を復習し、知識を定着させる効果も期待できるため、経験がある方にとっても有効です。
資格を選ぶ際は、初級レベルの資格だけではスキルの差別化が難しいため、可能な限り難易度が高く専門性を問われる資格へチャレンジしましょう。
同じ企業に長くとどまると、業務が固定化し成長機会を逃してしまう可能性があります。自分のキャリアが停滞していると感じた際は、より自分が成長できる環境への転職を検討するのも1つの手です。
たとえば、任される業務の範囲が広がったり、マネージャー待遇でむかえられたりするようなポジションであれば、将来性のある選択といえるでしょう。
40代の転職は即戦力評価が重視されるため、専門エージェントを活用し、自分のスキルに合った企業を見つけることが大切です。

40代までエンジニアとしてキャリアを歩むと、スキルや経験が豊富になっているケースが少なくありません。
ただし、スキルや経験が溜まっても現状維持で活動していては、若手エンジニアに追い越される可能性があります。これまでのスキルや経験を無駄にしないためにも、40代エンジニアならではの強みを活かし、ベテランならではのキャリアパスを歩むことが大事です。
ここでは、40代エンジニアにおすすめのキャリアパスについて、以下4点を解説します。
現在の領域で技術を深掘りし、再利用可能な設計パターンや自動化スクリプトを整備すると、組織に欠かせない専門家として認知されます。成果物の質も向上し、クライアントからの信頼を得る機会も増えるでしょう。
また、専門性を高めると市場単価が下がりにくく、雇用形態や働く場所も自分の希望に合わせて選びやすくなります。
さらに、転職や独立の場面でも評価されやすくなるため、1つのスキルを深く磨いていくことは将来にわたって有効な戦略です。
開発現場を熟知した40代であれば、PM(プロジェクトマネージャー)やPL(プロジェクトリーダー)といったマネジメント職にも挑戦しやすくなります。タスク分割やリスク管理、関係者との調整といった業務は、現場経験を重ねた方だからこそ的確に対応できます。
マネジメント人材は常に不足しているため、実績を積むことで報酬や裁量も広がり、仕事へのやりがいも大きくなるでしょう。
また、PMやPLの経験があると転職や独立時の強みになるため、機会があれば積極的に挑戦するのがおすすめです。
近年、AIや機械学習は急速に発展しており、今後も長期的に高い需要が見込まれる分野です。業界を横断して注目されている領域であり、社会やビジネスへの影響力も大きいため、将来性のある分野で活躍したいエンジニアには非常に適した選択肢といえます。
これまで培ってきた技術や業務知識と組み合わせることで、対応できる業務の幅も広がり、成長分野においても高い市場価値を発揮しやすくなります。
長く現場で活躍したい方こそ、新しい領域への挑戦が大きな武器となるでしょう。
十分な経験と実績を積んだ40代エンジニアであれば、独立してフリーランスとして働くことで、より自由な働き方を実現できます。受注する案件の内容やボリュームによっては、正社員時代よりも収入を大きく伸ばすことも可能です。
ただし、スキルや経験が不十分な状態で独立してしまうと、仕事が安定せず思うように活動できないケースもあります。
リスクをおさえたい場合は、まずは副業から始めて経験と人脈を広げ、十分に準備が整った段階で独立に踏み切るのがおすすめです。

40代は、体力や家庭環境の変化を踏まえ、安定して働ける環境を求める方が多くなる時期です。とくに、経験と実績が積み上がってきたエンジニアにおいては、キャリアの方向性が固まりつつあるため、転職や独立の挑戦は最後となる可能性が高いでしょう。
もちろん、スキルや実績次第では40代以降でも転職や独立で市場価値をさらに高められます。
ただし、年齢を重ねるほど挑戦へのリスクも高まるため、慎重に検討したうえで行動に移すことが大切です。

エンジニアとしてキャリアを歩み続けると、キャリアアップや環境の変化などを目的に、転職や独立を検討する方も少なくありません。ただ、40代となるとキャリアの方向性が定まる時期でもあり、転職や独立する際のリスクが大きくなるケースもあります。
もちろん、40代から成功した事例も多数あるものの、これまでのキャリアを無駄にしないためにも、慎重に検討し行動に起こすことが重要です。
ここでは、40代エンジニアが転職や独立する際におさえておくべきポイントについて、以下5点を解説します。
40代以降で転職や独立を考えている場合は、定年までの収入や働き方を見据えた上で計画的に動くことが重要です。20〜30代と違って何度も挑戦できるわけではないため、再雇用や老後も含めた長期的な働き方をイメージしておきましょう。
とくに、独立を視野に入れる場合はより綿密に計画をする必要があり、経費や社会保険料なども考慮しなければいけません。
目先の条件だけで判断してしまうと、将来的に不安定になる可能性があるため、長期的な視点でライフプランを立てたうえで挑戦することが大切です。
40代になると、体力面の変化や家庭との両立を考慮した働き方が欠かせなくなります。そのため、転職や独立を検討する際には、実際の稼働時間や休日の取りやすさをあらかじめ確認し、自分の望む生活スタイルに合っているかを見極めることが大切です。
近年はリモート勤務を導入する企業も増えており、通勤時間を削減できれば、家族との時間や自己学習に充てられる余裕も生まれます。
年齢が上がるにつれて、ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる環境かどうかを意識しながら、働き方を選ぶことが重要です。
長く同じプロジェクトで働くためには、自分の働き方と現場の方針が合っているかどうかが大切です。とくに、年齢が大きく離れたメンバーばかりの現場では、価値観やコミュニケーションスタイルにギャップが生じやすく、なかなか馴染めないと感じることもあります。
一方で、同世代のエンジニアが在籍している現場であれば、仕事上の悩みを共有しやすく、安心感を持って働きやすくなります。
カルチャーフィットを軽視するとストレスの原因にもなりやすいため、求人や案件の年齢層を事前に確認しておくことが重要です。
若手エンジニアの増加が見込まれる今、40代以降も作業者のままで働き続けるには限界があります。そのため、転職や独立を考える際は、自分がステップアップできる環境かどうかを事前に確認しておくことが重要です。
たとえば、スキル次第で対応範囲が広がったり、PMやPLを目指せたりすると、報酬とモチベーションの両方を伸ばせるでしょう。
年齢を重ねると再挑戦が難しくなるため、自分の実力を評価してくれる環境に身を置くことが大切です。
近年は定年延長や再雇用制度の導入が進み、60歳以降も働き続けることを前提にキャリアを考える方が増えています。そのため、40代で転職や独立を考える際は、定年後も安定して働ける環境かどうかを事前に確認しておくことが大切です。
なお、60歳以降は報酬や業務内容が変わることも多いため、雇用条件の詳細までしっかり把握しておきましょう。
転職や独立のチャンスが限られてくる40代だからこそ、目先の条件だけでなく、定年後まで見据えた働き方を意識しておく必要があります。

40代までにエンジニアとして十分な経験や実績を積み、フリーランスとして独立を考えている場合は、フリーランスエージェントの活用がおすすめです。なかでも、40代以降のエンジニア向け案件を豊富に扱う「SEES」は、安心して利用できるサービスのひとつです。
ITに特化した専任のコーディネーターが、利用者に適した案件を提案してくれるため、独立直後に案件を獲得できるか不安な方にも適しています。
無料のカウンセリングも用意されているので、40代以降の働き方に悩んでいる方は、まず相談から始めてみると良いでしょう。
SEESではシニアエンジニア開発案件も豊富!

エンジニアは年収が比較的高く、プロジェクトによってはリモートワークが可能なことから、40代以降でも目指す方が増えています。
ただし、40代から未経験で転職する場合は、即戦力としてのスキルや実績が求められるため、20〜30代より難易度が高いのが現実です。まずは学習によって知識を身につけ、小さな実績を積み上げるところからはじめると良いでしょう。
もし、副業ができる環境であれば、本業と両立しながらリスクをおさえて挑戦できるため、より現実的なステップとしておすすめです。

本記事では、40代エンジニアの需要について、キャリア戦略やキャリアパスなどを交えつつ解説しました。
近年はIT業界に参入する方が増えているものの、スキルと経験を兼ね備えた40代のエンジニア層は依然として貴重で、確かな需要があります。また、マネジメント業務や成長分野への挑戦など、40代だからこそ広がる選択肢も多く、将来性のあるキャリアが築けるでしょう。
ただし、年齢を重ねるほど再チャレンジの難易度も上がるため、行動には計画性が求められます。だからこそ、定年までを見据えた長期的な視点でキャリアを描き、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く