40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
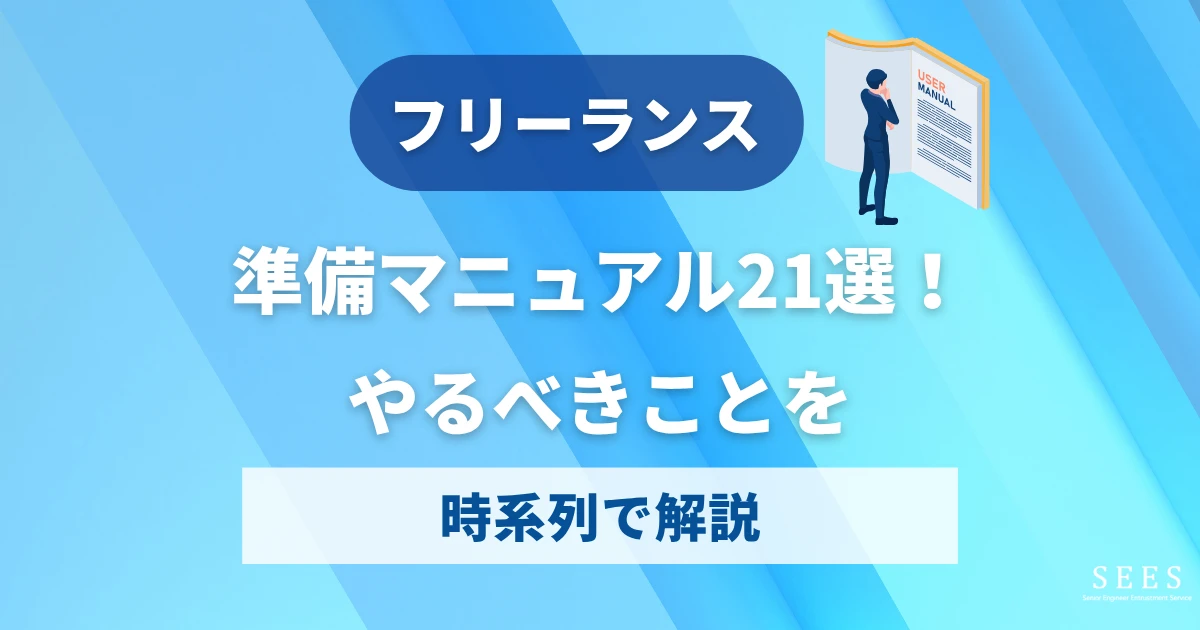
フリーランスになりたいと準備をしている方も多いのではないでしょうか。フリーランスになる場合には、やっておくべき準備が多々あります。フリーランスになってから慌てないように、この記事を参考に、しっかりと準備をした上でフリーランスとして活動しましょう。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
近年、リモートワークや副業が普及し、「会社に勤めなくても働ける」という価値観が広がっています。また、勤務時間や場所に縛られず、裁量権を持って働けることから、フリーランスを目指す方も少なくありません。
そんなフリーランスですが、スキルさえあれば誰でも始められる一方で、独立するまでにはさまざまな準備が必要です。
準備不足のまま勢いで独立してしまうと、案件が取れず生活が不安定になり、やむなく正社員に戻るケースもあります。加えて、再就職も簡単ではないため、独立前にリスクを最小限におさえるための備えが不可欠です。
本記事では、フリーランスになるために必要な準備について、環境面と資金面などカテゴリ別に解説します。

フリーランスには「年収が高い」や「柔軟に働ける」などの魅力がある一方で、営業力や継続的な案件獲得力など、実践的なスキルも求められます。そのため、必要なスキルや作業環境、資金面などをしっかり整えたうえで独立するのが望ましいでしょう。
もちろん、挑戦する業界や自身のスキルによっては、すぐに独立して成功するケースもあります。しかし、そのような例は少数派であり、多くの場合は準備不足のまま独立すると、案件が取れず収入が不安定になりやすくなります。
独立自体は簡単でも、失敗して会社員に戻るのは容易ではありません。後悔しないためにも、できる限りリスクをおさえる準備をしてからフリーランスになるのが賢明です。

フリーランスは、自由度の高さや裁量権を持って働ける点など魅力の多い働き方です。一方で、準備不足のまま独立してしまうと、その後の活動に支障をきたす可能性があります。
独立後に環境を整え始めると、その分だけ無収入の期間が長くなり、金銭面や精神面の負担が増大します。必要業務以外で余計なエネルギーを使わないためにも、事前にできる準備はすべて済ませておくのが理想です。
ここでは、フリーランス独立前に環境面で準備するべきことについて、以下4点を解説します。
未経験のままフリーランスとして独立してしまうと、仕事の受注方法や市場ニーズがわからず、収入を安定させるまでに時間がかかる傾向があります。そのため、まずは副業として小さくはじめ、市場のニーズを探りながらスキルを磨いていくのがおすすめです。
本業を続けながらであれば、万が一その職種が自分に合わないと感じた場合でも、方向転換をしやすいでしょう。また、収入源が確保されている状態であれば「キャッシュ不足」に陥るリスクも低く、時間をかけて向き不向きを見極められます。
フリーランスとして活動するには、自分で仕事を獲得しなければなりません。その際に、人脈があれば仕事を紹介してもらえるチャンスが生まれ、案件獲得の幅が広がります。
人脈を築くなら、肩書きや信用力のある会社員のうちに行動を起こすほうが、相手に話を聞いてもらいやすく、信頼も得やすい傾向にあります。
もし、独立に向けて知識やスキル習得の段階であれば、勉強会やオンラインコミュニティを通して交流を深めておくと、独立後の営業活動にもスムーズに活かせるでしょう。
独立直後は収入が不安定になりやすく、賃貸契約の審査に通りにくくなる傾向があります。そのため、引っ越しを検討している場合は、できるだけ会社員のうちに済ませておくのがおすすめです。
また、フリーランスになると営業や事務作業など業務量の幅が広がるため、独立後に引っ越しをするのは時間的にも体力的にも余裕がなくなることもあります。
事前に引っ越しおよび作業環境を整えておくことで、独立直後からスムーズに仕事に移行できるでしょう。
フリーランスとして活動するのであれば、仕事で使用する備品や通信環境は自分で用意する必要があります。独立時に準備が整っていないと、すぐに仕事を始められず、良いスタートを切れません。
また、すでにパソコンやWi-Fi環境が整っている場合でも、業務に支障がないか事前に動作確認しておくと安心です。
仕事内容によっては、使用する機材のスペックが作業効率だけでなく、クライアントからの信頼にも影響するため、必要に応じて買い替えも検討しましょう。

フリーランスとして独立する際は、環境面の準備だけでなく、資金面の備えも欠かせません。とくに、仕入れや価格の高い備品の購入が必要な場合は、ある程度まとまった資金を用意しておく必要があります。
独立してからでも用意はできるものの、信用が低く資金調達ができない可能性があるため、できるだけ会社員のうちに準備を済ませておくのがおすすめです。
ここでは、フリーランス独立前に資金面で準備しておく内容について、以下5点を解説します。
フリーランスは、会社員とは異なり生活費に加えて、事業運営にかかるさまざまな固定費が発生します。「どの程度の売上があれば生活や事業が成り立つのか」を把握するためにも、独立前に毎月の収支をシミュレーションしておくことが重要です。
たとえば、フリーランスとして活動する場合、以下のような支出が毎月発生します。
これらの支出を把握していないと、いくら売上を上げても経費がかさみ、想定よりも手取りが少なくなるおそれがあります。
安定してフリーランスとして活動を続けるためにも、あらかじめ収支のバランスを確認し、問題がないかを判断したうえで独立を検討しましょう。
ローンやクレジットカードを利用する可能性がある場合は、独立前に申し込んでおくのがおすすめです。これらの与信審査では、申込時点での年収や雇用形態が重視されるため、独立後では審査に通りにくくなる傾向があります。
ただし、独立直後は会社員時代よりも収入が下がる可能性があるため、高額なローンを組むのは避けたほうがよいでしょう。
もし、ローンを組む場合は、独立後の収支をあらかじめシミュレーションし、返済可能な範囲で借入額を設定することが大切です。
独立時に事業資金としてまとまった額が必要な場合は、日本政策金融公庫からの融資を検討し、早めに申請準備を進めておくと安心です。
日本政策金融公庫とは、政府が出資する公的な金融機関で、個人事業主や中小企業に対して融資をおこなっています。審査はあるものの、金利が低く返済期間も長いため、独立直後でも比較的余裕を持って返済できるのが特徴です。
融資の実行までには2週間程度かかるため、余裕を持ってスケジュールを立てましょう。
独立する際にまとまった資金が必要な場合は、日本政策金融公庫と並行して、地域の銀行や信用金庫からの融資も検討しましょう。
地域の銀行や信用金庫は、地域経済の活性化も重視しており、事業規模に関わらず、地域に根ざした個人事業主に対して親身に相談に乗ってくれる傾向があります。
融資を希望する際は、複数の金融機関を訪れ、金利や返済条件、担当者の対応などを比較して最適な金融機関を選ぶようにしましょう。
フリーランスは会社員と違い退職金制度がないため、老後に備えた資金は自分で準備する必要があります。その備えとして有効なのが「小規模企業共済制度」です。
小規模企業共済は毎月の掛金を1,000〜70,000円まで、500円単位で自由に設定できます。また、全額が所得控除として認められるため即効性の高い節税策といえるでしょう。
掛金の納付期間が長いほど受取額が増える仕組みになっているため、フリーランスとして長期的に活動する予定がある場合は、早めに加入しておくのがおすすめです。

現在勤めている会社を退職して独立する際は、雇用形態の変更にともない、いくつかの重要な手続きが必要になります。とくに、社会保険に関しては、これまで会社が代行していた部分も多く、独立後は自分で対応しなければいけません。
また、手続きによっては期限が定められているものもあるため、事前に必要な内容を把握し、漏れなく対応できるように準備しておきましょう。
ここでは、フリーランスとして独立する際に把握しておくべき手続きについて、以下4点を解説します。
会社員からフリーランスになる場合は、厚生年金の資格を失うため国民年金に切り替える必要があります。なお、国民年金への切り替えは、退職から14日以内に住民票のある市区町村窓口で変更手続きをしなければいけません。
手続きが遅れると未納期間が発生し、将来受け取れる年金額が減ってしまう可能性があるため、早めに切り替えるのがおすすめです。
また、扶養家族がいる場合は、会社員とは違って配偶者にも国民年金の支払いが生じます。独立する際は2人分の手続きを忘れないようにしましょう。
日本では、いずれかの公的医療保険に加入することが義務付けられています。そのため、会社を退職すると社会保険資格を喪失することから、国民健康保険へ切り替え、あるいは任意継続被保険を選択しなければいけません。
また、独立後の収入が130万円未満になる見込みがある場合は、家族の健康保険の扶養に入るという選択肢もあります。それぞれのケースで保険料や保障内容を比較し、自分にとってもっとも負担の少ない方法を選ぶと良いでしょう。
なお、手続き先は保険の種類によって異なるため、以下の表を参考に確認しておきましょう。
| 健康保険の種類 | 手続き窓口 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口 |
| 任意継続被保険 | 住まいの協会けんぽ支部 ※協会けんぽに加入していた場合 |
| 家族の健康保険 | 健康保険組合 |
フリーランスとして事業を開始する際は、開業届を所轄の税務署に提出することが義務付けられています。原則として、事業開始から1か月以内に提出することが求められているため、独立を決めた段階で準備を進めておきましょう。
なお、開業届は未提出でも罰則はないものの、公的支援を受けられなかったり職業を証明する場面で不利になったりする可能性があります。
e-Taxを利用すればWeb上で手軽に提出できるため、独立を決めたタイミングで早めに手続きしておくのがおすすめです。
青色申告は、個人事業主やフリーランスが税制上の優遇を受けられる申告方法です。青色申告に切り替えておくことで、最大65万円の特別控除や赤字の3年繰越など、さまざまなメリットが得られます。
申請書の提出期限は開業から2か月以内、またはその年の3月15日まで(前年から継続する場合)となっており、期限を過ぎると青色申告は翌年分からしか適用されません。
開業届と同様に、e-Taxを使用して提出できるため、開業届とあわせて早めに手続きを済ませておくのがおすすめです。

フリーランスとして活動する際は、お金を稼ぐことに加えて、守ることに関する備えも欠かせません。とくに、年度末に控える確定申告は事務作業のなかでも負担が大きく、ミスやトラブルが起こりやすい業務の1つです。
こうしたトラブルに発展しないよう、日頃からどのような準備をしておくべきか把握しておくことが重要です。
ここでは、年度末の確定申告に向けて準備すべきポイントについて、以下3点を解説します。
フリーランスとして活動する際は、経費の計上漏れや私費との混在といったトラブルが発生しやすくなります。そのため、プライベートの口座とは別に、事業専用の口座を開設しておくことがおすすめです。入出金の管理がしやすくなり、経費の計上漏れを防ぎやすくなります。
また、事業専用のクレジットカードを口座と紐づけておくことで、会計ソフトとの連携もスムーズになります。自動仕訳や確定申告書の作成も手軽になり、事務作業にかかる時間を大幅に削減できるため、本業に集中しやすくなるでしょう。
複式帳簿とは、資金の動きを「借方」と「貸方」の2方向から記録する帳簿の形式です。青色申告をおこなう事業者は、この帳簿をもとに確定申告時の決算書を作成します。
書面で複式帳簿をつけると複雑ではあるものの、近年は会計ソフトを活用することで多くの作業が自動化され、記帳の負担も軽減できます。
「freee会計」や「やよいの青色申告 オンライン」など複数の会計ソフトがあるため、機能や料金を比較して、自分に合ったものを導入しましょう。
毎年の確定申告では、日頃から記録している帳簿をもとに申告書を作成します。帳簿をつけるタイミングに明確な決まりはないものの、時間が経ってからでは領収書の紛失や記憶違いが起きやすいため、定期的に記帳する習慣をつけておくのが望ましいです。
たとえば、1週間以内や月末など、記帳のタイミングをあらかじめ決めておくのがおすすめです。このように定期的に帳簿を更新しておくと、売掛金の未回収や経費過多の早期発見につながり、資金繰りの見通しも立てやすくなります。

フリーランスとして活動する際は自分で案件を獲得する必要があるため、営業活動の準備が欠かせません。この準備を疎かにしてしまうと、案件を獲得できない状態が続き、無収入の期間が生じるおそれがあります。
収入がないと、生活基盤が安定せず仕事へも影響しかねないため、独立前に案件を獲得できるように準備を進めておくことが大切です。
ここでは、フリーランスとして稼ぐために必要な準備について、以下4点を解説します。
フリーランスとして案件を獲得するには、「自分に何ができるか」や「どのような人物か」を端的に伝えるポートフォリオの準備が欠かせません。発注者は費用をかける以上、実績やスキルが明確な相手に依頼したいと考えるため、実力が見えない事業者は敬遠されがちです。
ポートフォリオには、これまで携わってきた業務内容や実績、保有スキル、資格などをわかりやすくまとめておきましょう。
また、ポートフォリオのリンクをQRコード化して名刺やSNSに掲載しておくことで、商談前から実力をアピールしやすくなります。
案件を獲得するには、「この人に仕事を依頼したい」と思ってもらえるよう、自分の人柄を伝えることが大切です。ブログやSNSなどで情報発信することで、自身の活動への姿勢や考え方を伝えられます。
また、ブログやSNSで発信する内容を絞ることで「専門性」をアピールできるため、見込み客との接点を増やせます。
このような情報発信は信頼を得るまでに時間がかかるため、できるだけ早い段階から始めておくと効果的です。
独立直後は、想定より営業先を見つけられない可能性があるため、クラウドソーシングやスキルマーケットを利用するのがおすすめです。これらのサービスは、発注者と受注者をつなぐ仕組みが整っており、営業の手間を省けます。
利用するサービスによって、取り扱っている案件の業種や価格帯が異なるため、複数に登録して比較しながら探すと良いでしょう。
なお、多くのサービスでは報酬に対して手数料が発生するため、利益率も踏まえて利用サービスや案件を選ぶことが大切です。
独立時点で、ある程度の実績やスキルがある場合は、フリーランス向けの求人サイトやエージェントの活用がおすすめです。高単価の長期案件や非公開案件も多く取り扱っているため、自分の希望に合った案件を見つけやすいでしょう。
多くのサービスでは、無料相談のほか、営業代行や単価交渉などのサポートも提供しており、メイン業務に集中できるのも特徴です。
たとえば「SEES」では、無料カウンセリングに加えて、専属コーディネーターが就業をサポートしてくれます。独立後の営業に不安がある方は、こうしたサービスの活用を検討してみるとよいでしょう。

フリーランスとして活動する際は、収入を得ることだけでなく、法的トラブルを防ぐための知識を備えておくことも重要です。
とくに、注目しておきたいのが、2024年11月に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。この法律では、取引条件の明示や報酬の支払期日の設定など、フリーランスと企業の取引に関するルールが定められています。
複数の企業と取引を進めるなかで、不適切な対応をするクライアントに出会う可能性もゼロではありません。こうしたトラブルに備えて、フリーランス法の内容をあらかじめ確認し、いざというときに相談できる窓口も把握しておきましょう。
なお、万が一トラブルに巻き込まれた場合は「フリーランス・トラブル110番」の利用を検討してみてください。
フリーランスのトラブルは「フリーランス・トラブル110番」へ!

最後に、フリーランスになる際の準備に関するよくある質問について、以下7点を解説します。
職種やスキルレベルによって異なりますが、平均的には3〜6か月が目安です。この期間で副業としての実績作りや生活費の貯蓄、手続きに必要な書類を準備しておくのが理想とされています。
ただし、未経験ジャンルへ転向する場合はスキル習得と人脈形成に時間がかかるため、半年以上の時間をかけて準備するのがおすすめです。
結論、十分に準備をしたうえでフリーランスとして独立するのがおすすめです。すでに経験や生活費に必要な貯蓄があれば問題ない場合もあるものの、そうしたケースはごく少数です。
独立直後は仕事を軌道に乗せるのが難しいうえに、資金面や営業活動などで予期せぬトラブルも発生しやすいため、慎重に独立を進めましょう。
業務に必要な専門スキルは最低限として、フリーランスにはビジネススキル全般が求められます。たとえば、案件を獲得するための営業スキルや日程調整するためのマネジメントスキルなどが挙げられます。
これらのスキルを満遍なく身につけていないと、安定的に収益をあげ続けるのは困難です。書籍での学習はもちろん、独立前から実践しつつ身につけていくと良いでしょう。
ITエンジニアの場合は、最新スキルの習得はもちろん、自分の実績やスキルを証明するポートフォリオの構築を並行しておこないましょう。たとえば、GitHubで実績公開しておくと、発注者もスキル確認を簡単にできます。
そのほかにも、技術ブログで設計思想を発信しておくと技術力のアピールにもなるため、高単価案件を狙う際に活かせます。
グラフィックデザイナーやイラストレーターに関しても、ほかの職種と同様に、業務で使用するスキルと実績を公開できるポートフォリオを用意しましょう。
また、近年はInstagramやXなどで案件の受発注が生まれるケースもあります。そのため、早い段階からアカウントを育てて実績を公開しておくことで、案件獲得の選択肢を増やしておくのも良いでしょう。
目安としては、生活費6か月分が推奨されています。ただし、業界によっては案件開始から入金まで2か月かかるケースもあるため、状況に応じて6〜8か月の生活費を備えておくのがおすすめです。
まずは、1か月の収支を確認し、支出で削れる箇所を見つけながら6〜8か月生活するのに必要な金額をシミュレーションしましょう。
フリーランスとして独立するのであれば、ビジネススキルに関する書籍を読んでおくのがおすすめです。たとえば、案件獲得に関する内容であれば、以下のような書籍があります。
フリーランスに関する書籍は数が多いため、「何について知りたいのか」という点を明確にしたうえで探し始めると良いでしょう。

本記事では、フリーランスになるために必要な準備について、環境面と資金面などカテゴリ別に解説しました。
フリーランスとして活動する際は、仕事環境や資金面の準備などを自分でおこなう必要があるため、独立前からコツコツ進めることが不可欠です。
もちろん、独立後に準備と仕事を並行して進めることも可能ではあるものの、その場合は案件獲得から報酬発生までに時間がかかり、効率が悪くなるおそれがあります。できるだけ最短で事業を軌道に乗せるためにも、スムーズに案件を獲得し、報酬を得る流れを構築しておくことが重要です。
フリーランスへの挑戦が失敗とならないためにも、事前準備を念入りにおこない、リスクを最小限におさえたうえで独立しましょう。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く