40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
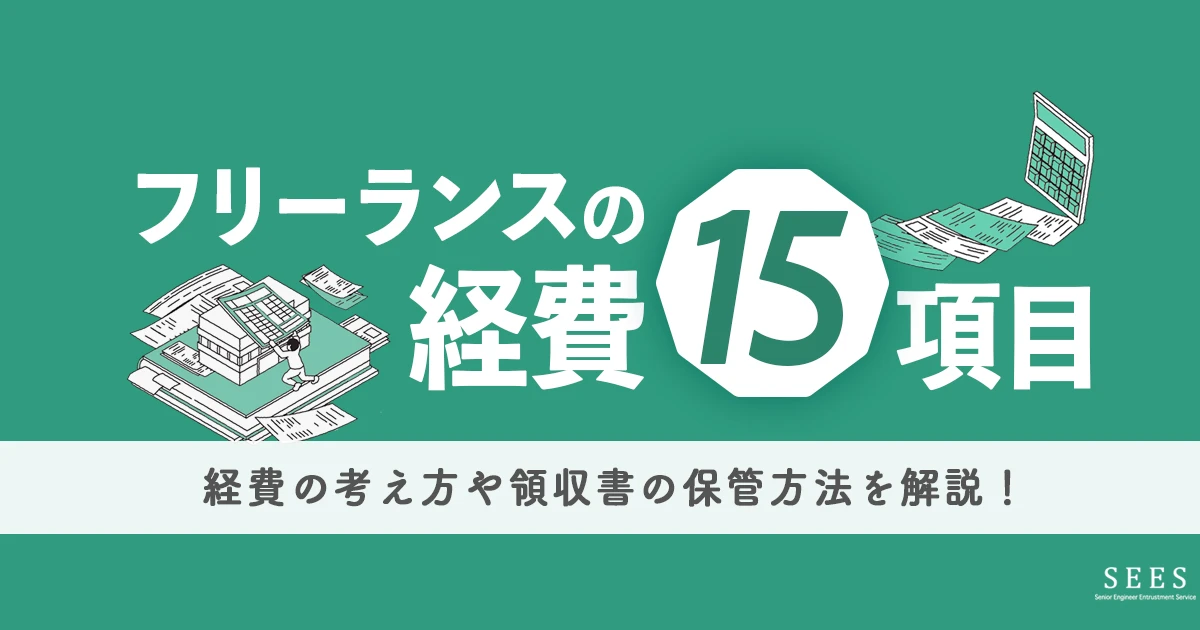
フリーランスの事業では、何が経費に計上できるのでしょうか。漏れがある場合、税金を過剰に払ってしまうことが懸念されます。本記事では、フリーランスが経費にできる費用、証拠として必要な領収書の保管方法やない時の対応方法を詳しく解説します。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
「フリーランスの経費ってどんな仕組み?」
「フリーランスが経費にできる費用は?」
「経費を計上するための領収書が必須?ない時はどうすればいい?」
フリーランスとして働く場合、納税のために必ずしなくてはならない確定申告ですが、節税のために重要なのが、経費の計上です。事業上で発生する費用のうち経費として計上できる費用を知り、適切に対処することで節税が図れます。しかし、これからフリーランスになる方や活躍中の方でも、経費について曖昧に理解している部分も多く、疑問を持っている場合もあるでしょう。
本記事では、フリーランスで事業を行う際に必要な経費の考え方やその重要性、経費として計上できるものには何があるかを詳しくまとめました。さらに、領収書の保管期間や領収書がない場合の対応方法などもあわせて解説します。
この記事を読むことで、経費についての知識を得られるため、日頃の領収書などを整理するという基本的なことから、確定申告で正しい経費を計上し節税することにまで役立てることができます。フリーランスにこれからなる方や活躍中の方は、ぜひ参考にしてください。
 フリーランス(自営業)における経費とは、前年の12月31日までに債務が確定している事業上の費用をさします。支払いが済んでいても請求が確定していないものは経費とならず、逆に支払っていなくても請求が確定しているものは経費の対象です。
フリーランス(自営業)における経費とは、前年の12月31日までに債務が確定している事業上の費用をさします。支払いが済んでいても請求が確定していないものは経費とならず、逆に支払っていなくても請求が確定しているものは経費の対象です。
経費はフリーランスの所得税や住民税の算出時に、対象となる売上から除外されるため、適切に計上することで節税に繋がります。
ただし、事業で使ったお金がすべて経費となるわけではなく、「事業を行うにあたって必要なものであり、直接売り上げに貢献しているか」という判断基準があります。定義についての具体例はないため、経費になるかどうかの判断はフリーランス自身がそれぞれで行います。
直接的に売り上げにつながることを証明しづらい生活用品としても使える服飾品などは、対象とならないことを覚えておきましょう。
出典:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

フリーランスになると、自分で所得を計算して納税するため、確定申告が必要となります。
その際、なるべく納税額を減らしたいと考える事業者が多いのではないでしょうか。そこで節税に有効となるのが、経費を計上することです。経費は住民税や所得税の算出時に対象となる売上から差し引かれるため、経費の計上により納税額を抑えることができます。
つまり、「売上=所得」ではなく、経費を差し引き「売上-経費=所得」とすることで、課税額を抑え、節税することが可能です。
フリーランスの確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、青白申告には節税につながるメリットがあります。例えば、30万円未満の減価償却資産や家族への給与を経費として計上することができ、その結果納税額を抑えることが可能です。また、所得から最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
出典:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

経費が多いと所得が減り、納税額を抑えることができます。しかし、なんでも経費にすれば良いというわけではなく、適切とされる割合があります。この経費の比率を経費率といいます。フリーランスは経費率を意識することが大切です。
経費率とは「経費÷収入」で計算される収入に対しての経費の割合のことをいいます。業種や売り上げによって異なりますが、フリーランスの場合50%が経費率の目安とされています。ただし、経費率については、具体的な基準が定められているわけではないため、フリーランス自身が自分でバランスをとる必要があります。
出典:事業所得者の課税のあり方の検討-事業所得における概算経費控除の導入の検討を中心として-|国税庁
参考:https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/72/04/index.htm

フリーランスが事業上の経費として計上できる費用を15の項目に分けて紹介します。
フリーランスは、日々発生する経費を自分で分類し記録していく必要があります。1つ1つの経費を仕分けしていく際にも参考となる内容です。また、青色申告をする場合には複式簿記で取引を記帳します。複式簿記では勘定科目に分類するため、こちらについても紹介します。
なお、確定申告で経費を申告する場合には会計用のソフトウェア・システムやWebサービスを利用すると便利です。勘定科目についても候補から選択することができます。
売り上げを生み出すための広告や宣伝費用は経費として計上できます。チラシを配布する、ネット上に広告を掲載する、テレビCMを作成するなどが対象です。勘定科目は「広告宣伝費」となります。
支払いをした時点では経費とならず、実際に広告や宣伝に使ったタイミングで経費として計上します。つまり、契約金を払っていてもCM放映が翌年であれば、翌年の経費となります。
自分が取引先やお客さんの所へ行って仕事をする場合、それにかかった旅費や交通費を経費として計上できます。電車、バス、タクシー、飛行機を利用した際の費用や出張先での宿泊費などが対象です。
車を使って移動しなければならない場合は、車に関する費用も該当します。駐車場代、車検代、自動車税、燃料費(ガソリン代)などがその対象です。
勘定科目は「交通費」、「旅費交通費」として計上することが一般的で、ガソリン代については「燃料費」、「消耗品費」とされることもあります。
仕事場の家賃や駐車場の料金も経費として計上できます。勘定科目は地代家賃「地代家賃」か「旅費交通費」として扱われます。
フリーランスの場合、持ち家で仕事をしている人も多いのではないでしょうか。その場合、事業を行うスペースの分だけが経費の対象となります。見取り図をもとに、事業スペースが家全体のどのくらいを占めているのか面積の割合を算出しましょう。
このように、プライベートと兼用の経費を家事関連費といいます。取引の記録に基づき、仕事のために直接必要だったということが明確であれば経費となります。
プライベートとの兼用の場合、 家事按分を行います。家事按分とは家賃などをプライベートでの使用と事業での使用に分ける計算方法です。どこまでが事業用途と認められるかは一概にはいえないため、フリーランスが一般的な範囲で比率を定める必要があります。
消費税以外に、個人事業税、固定資産税、動産に係る償却資産税は経費にすることができます。動産とは、お金や家具など動かすことができる財産をいいます。
通常、家族への家賃は経費とはなりません。ただし、家族名義の土地建物を使って事業を行なっている場合は、その部分の固定資産税が経費の対象となります。
勘定科目は「租税公課」です。
出典:No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合|国税庁
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm
て使用する水道やガス、電気、冷暖房に用いる灯油などに係る費用は経費にできます勘定科目は電気代も含めて「水道光熱費」となります。
自宅で仕事をしている場合はプライベートと兼用のため、業務で使用した光熱費、電気代のみを計上しましょう。1日のうち何時間仕事をしているのか平均値を出し、業務で使用した分を算出する方法があります。プライベートと兼用している場合は地代家賃と同様に家事按分が必要です。
開業前の準備にかかった費用を開業費といい、経費ではなく繰延資産という資産として扱います。初年度にいったん資産として計上し、翌年から経費に入れていくという仕組みです。
繰越損失(マイナスの繰越資産)は最大三年繰り越して所得と相殺できます。十分に売り上げを得ていない初年度に全て計上すると翌年以降の相殺に利用できなくなるため、数年にわたって経費処理を行います。
外部の法人や個人と請負契約を結び、業務の一部を委託する際に使用した費用は経費にできます。勘定科目は「外注費」、「外注工賃」です。委託された業務の完成を約束し、完成した仕事に対して報酬を支払う契約を請負契約といいます。
課税仕入れとなるため仕入税額控除を受けることができ、従業員の給与ではないため社会保険料は不要です。
仕事で使っている文房具や事業を保つために必要な消耗品は、経費にできます。勘定科目は「消耗品費」です。ファイル、コピー用紙、インクなど、使用可能期間が1年未満または少額(10万円未満)である消耗品が対象です。
雑費と似ていますが、使用頻度と金額が異なります。仕分けする際には注意しましょう。
出典:No.6451 仕入税額控除の対象となるもの|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm
従業員への給与は勘定科目「給料手当」として経費にできます。正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象です。なおフリーランス(個人事業主)本人への給与は対象外です。
通常、生計をともにする家族への報酬はお小遣いとみなされ、経費にできません。しかし、青色申告専従者給与に関する届出書を税務署に提出することで、経費として認められる特例があります。ただし、半年以上その業務に専念しており、15歳以上であることが条件です。
また、従業員を雇う場合、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を税務署に提出する必要があり、源泉徴収義務者となります。給与から源泉徴収分を徴収し、税務署に納めましょう。
出典:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
業務上使用しているクレジットカードの年会費、振込手数料などは経費にできます。また、クライアントがクレジット決済した際に代行業者(クレジット会社)へ支払う手数料も対象です。勘定科目は「支払手数料」となります。
事業のためにお金を借りている場合、借入先に対しての利子も経費となりますが、返済費自体は経費にできません。この利子は勘定科目「支払利子」として扱います。
事業で利用するパソコンや車などの購入で10万円以上かかった場合は、原則として減価償却しなければなりません。減価償却はこれらの費用を耐用年数と同等の期間で年ごとに分割して経費として計上する仕組みです。支払いが済んでいなくても、事業のために使い始めたら減価償却を始めましょう。
年月が経つことにより、劣化したり性能が落ちたりして価値が減っていくものが減価償却の対象です。そのため、時間が経っても劣化しない土地や借地権、劣化しても価値が下がらない書画や骨董品などは対象となりません。勘定科目は「減価償却費」となります。
出典:No.2100 減価償却のあらまし|国税庁
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
事業の一環として打ち合わせや接待など関係者と一緒に食事をした際の費用は、接待費として経費にできます。また、手土産や御中元など贈り物にかかった費用も対象です。勘定科目は「接待飲食費」です。また、会議を伴う場合には「会議費」とすることができます。
従業員との社員旅行、会議で提供されるお菓子や弁当などの飲食費については、接待交際費には該当しません。
自治会や商工会への会費は、経費にできます。期間が1年間で、金額が比較的小さいものが対象です。
勘定科目「諸会費」で計上します。
親睦が目的となっているクラブ活動への年会費などは、接待交際で使う意味合いが強いため、交際費として処理しましょう。NPO法人への賛助会費など見返りのない寄付行為は、寄付金として扱います。
出典:No.6467 会費や入会金の仕入税額控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm
通信環境を整えるために係る費用は、経費にできます。インターネット回線の利用料金、電話代、プロバイダー料金などが対象です。常に音楽や映像を流している場合のサービス費も該当します。アプリの使用料は、雑費として処理しましょう。勘定科目は「通信費」です。
注意が必要な点として、PCや電話機、タブレット端末やルーターなどのデバイスの購入、リースなどの費用は別の科目として扱います。
フリーランスの場合、プライベートと兼用でスマホやインターネットを使用する人が多いのではないでしょうか。1日のうち何時間仕事をしているという平均値を出し、業務で使用している通信費を家事按分して算出しましょう。
書籍や新聞を購入した費用は、経費にできます。情報を得るために使用するなど業務に関係あると判断できるもので、電子版も対象です。勘定科目は 「新聞図書費」、「福利厚生費」、「研修費」、「雑費」などで利用目的により変わります。例えば、従業員の福利厚生のために購入した場合は「福利厚生費」、業務に関するセミナーで必要となる場合は「研修費」となります。
フリーランスの場合、プライベートで利用する書籍や新聞と分けることが難しく、全額経費に計上するのは難しいといえます。
ご祝儀や香典、自動販売機で飲料を購入した場合など、どうしてもレシートや領収書がもらえない時は、結婚式や葬式であれば案内状にいくら包んだのかメモを残しましょう。
案内状など証拠となるものがない場合は、出金伝票に書いて残しておくという方法があります。出金伝票は100円ショップでも購入できますが、何でも書いて良いというわけではありません。どうしても領収書がもらえないケースの時のみ、使用しましょう。

経費は事業上で使った費用を記録しておき、確定申告の際に申請します。その際、支払っていない費用を申請できないように証拠となる書類を保管しておく必要があります。
レシートや領収書がその証拠となります。税務調査が入った場合にも、経費計上の根拠を準備しておくため、いつ来ても対応できるよう普段から整理しておきましょう。
確定申告では、フリーランスは住民税、所得税の対象となる所得を申告します。その際に経費の一部は課税対象から除外でき、節税の効果が期待できるため、フリーランスであれば必ず知っておきたいポイントです。
以下では、領収書の保管期間と保存方法について確認しましょう。
フリーランスの場合、確定申告の種類が青色申告と白色申告で保管期間が異なります。
青色申告の場合、保管期間は原則7年です。ただし、申告した前々年の所得が300万円以下だった場合、保管期間は5年となります。
白色申告の場合、保管期間は原則5年です。ただし、帳簿の保管期間は7年のため、何かの時のために領収書も同じ期間残しておくと良いでしょう。
保管期間は領収書を受け取った日から○年と数えるのではありません。いずれも領収書を受け取った事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から○年と数えます。
出典:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
電子帳票保存法に基づき、一定の要件を満たした帳票類は電子データとして保存することが認められています。
デジタルで保存する方法は以下の3通りあります。
領収書を管理する負担の軽減や紙にかかるコストの削減、紛失の心配がないなどのメリットがあります。
出典:電子帳簿等保存制度特設サイト
参考:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
アナログで保存する方法としては、以下の3通りなどがあります。
レシートの場合、時間が経つと印字が消えてしまうのが問題です。そのため、印字が薄くなっても経費であることを証明できるようにする必要があります。
余白にメモを残しておく、コピーやスキャンをする、写真に残しておくなどの対策をしましょう。レシートのコピーでも問題はないとされていますが、原本も一緒に残しておくと安心です。
クレジットカード会社が発行する利用明細書も領収書代わりにすることができます。ただし、発行者、宛名、購入内容、金額、購入年月日が明記されていることが条件です。
また、Webの明細書は表示期間が決まっているため、期限を過ぎると見ることができなくなってしまいます。早めに印刷しておきましょう。
支払に関する領収書以外の帳票として請求書があります。しかし、通常は請求書だけでは領収書のように経費の証拠としては不十分です。請求書はあくまで費用の請求が書かれているだけで、支払った事実は記載されていないためです。
ただし、銀行振り込みやクレジットカード払いの場合は請求書と明細が揃っていることを条件に経費の資料とすることができます。
請求書兼領収書は通常の領収書と同様に経費の証拠として問題ありません。
原則、領収書の発行は1回の取引につき1枚までとなっています。再発行の義務はなく悪用のリスクもあるため、再発行依頼に応じない会社がほとんどです。
新幹線や飛行機など高額の交通費は、半年から1年以内であればインターネットで再発行手続きができるケースもあるため、まずは各支払い先に問い合わせてみましょう。
どうしても再発行が難しい場合、購入証明書と支払明細書で対応できます。これらの証明書に日付、金額、取引内容、購入元、支払い先、領収書紛失について記載します。また、証明書の発行は有料となるケースがほとんどです。
出金伝票は、バス代などの交通費や仕事で関わりのある方へのご祝儀や香典といった慶弔費、自動販売機で飲料の購入、領収書をなくしてしまった時などに領収書の代わりとして使えます。
なお慶弔費については、案内状にいくら包んだのかをメモしたものも有効です。
出金伝票は文房具店や100円ショップでも購入できますが、自分でエクセルなどを使って作成しても問題ありません。自分で作成する際は、日付、支払先、勘定科目、摘要、金額、合計額の6つを必ず記載するようにしましょう。
このように、領収書やレシートがなくても経費として計上することはできますが、出金伝票を使うのはどうしても領収書が出ないもので、かつ事業と関連があるもののみです。
自ら発行する出金伝票は、第三者が発行する領収書やレシートに比べ信憑性に欠けるため、多用すると税務調査が入った際に追求されるケースもありますので、必要最低限にとどめておく方が良いでしょう。
フリーランスの経費について、よくある質問とその回答を集めました。
経費はフリーランスが税制上で損をしないために利用できる仕組みです。特にこれからフリーランスを目指すという方は、損をしないよう理解・把握して活用してください。
フリーランスが確定申告において経費を計上するメリットは、所得税や住民税の課税対象金額である所得から経費分は除外することができるためです。事業上で発生した費用を経費として計上すると、結果として節税することができます。
確定申告での経費として計上した金額に対し税務調査が行われる場合があります。税務調査の際には、経費を支払った証拠として領収書やレシートが必要となるため、フリーランスは経費の領収書などを適切な期間保管しておく必要があります。領収書はデジタルデータとして保管するか、紙で保管しておく方法があります。保管期間は7年または5年で、確定申告の種類などによって違います。
事業で必要となった支出でなおかつ領収書がどうしても発行されない場合には、出金伝票などを使うことで経費に計上することができます。例えば、慶弔費や自動販売機での購入などが対象です。出金伝票は購入したものを利用するか、自分で作成することもできます。ただし、他者の発行した領収書などと比べると信ぴょう性は薄くなるため、むやみに使用することは避けたほうがよいでしょう。

経費は、適切に計上することでフリーランスが節税することのできる仕組みです。経費の活用に関する知識は、フリーランスとして事業を行う上で欠かせないものの一つといえます。
ただし、根拠のない経費はペナルティが科され、より多くの税金を納めることにもなりかねません。したがって、事業を行うにあたって直接必要なもので、直接売り上げに貢献しているかどうかという判断基準のもと、各種の費用が経費にあたるのか見極めましょう。
フリーランスの場合、プライベートと兼用のものに関する費用も多くあります。それらは、明確に分けられる根拠のある数値をもとに算出しましょう。もし経費処理で不安な部分があった場合は、税務署へ確認することをおすすめします。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く