40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
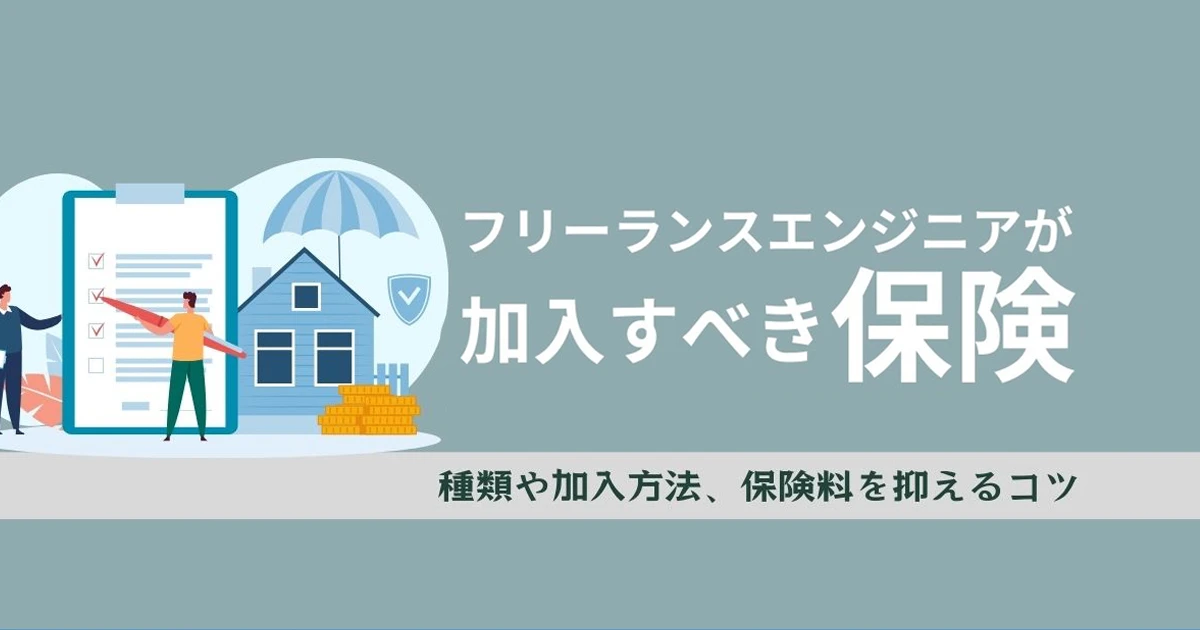
フリーランスエンジニアが利用できる公的保険制度の内容や、おすすめの民間保険についてわかりやすく解説します。フリーランスに保険の加入を推奨する理由や、保険料を節約する方法もまとめました。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
会社員とフリーランス(個人事業主)では、加入できる公的保険制度の内容が異なるため、独立する場合は加入している保険の見直しが必要です。
この記事では、フリーランスが利用できる公的保険制度の内容や、加入すべきおすすめの民間保険について解説します。
フリーランスや個人事業主はさまざまなリスクに自分ひとりで対応しなければならないので、最低限必要な保険を理解し、万全に備えておきましょう。
フリーランスや個人事業主が加入する公的年金制度や公的医療保険制度は、会社員が加入できる健康保険や厚生年金と比較すると、保障内容が不十分です。
さまざまなリスクやトラブルに対して自分ひとりでの対応が求められるフリーランスや個人事業主は、備えが必要だといえるでしょう。
ここでは、フリーランスに保険の加入をおすすめする理由を下記の3つの視点から解説していきます。
【フリーランスに保険の加入をおすすめする理由】
フリーランスの方が加入する国民健康保険には、会社員が加入する健康保険と同様に「療養の給付」や「高額療養費制度」が設けられています。
| 療養の給付 | 医療費の自己負担が3割になる |
| 高額療養費制度 | 毎月1日~月末までの自己負担額が所定の上限を超えた場合に、超過分が払い戻される |
しかし、国民健康保険には傷病手当金がないので、病気や怪我によって働くことができなくなった場合、貯蓄や保険などでカバーしなければなりません。
退職後に健康保険を任意継続しても、傷病手当金は受給できないので注意が必要です。出産に備えて休んだ場合に支払われる「出産手当金」も受給できません。
会社員は、国民年金保険と厚生年金保険の両方に加入するので、老後は「老年基礎年金」と「老年厚生年金」の2つを受給できます。
一方で、フリーランスは国民年金保険のみに加入するため、老後に受け取れる年金も老年基礎年金のみです。フリーランスが老後に受給できる金額は、会社員よりも少なくなるでしょう。
厚生労働省が公表している「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、平均受給額に大きな差が開いていることが明らかになりました。
| 厚生年金加入者 | 145,665円/月額 |
| 国民年金加入者 | 56,479円/月額 |
上記の数値は「平均値」ではありますが、フリーランスが受給できる老齢年金の額は、 厚生年金加入者である会社員の半分以下であることが見て取れます。
フリーランスが老後年金の受給額を増やすために、付加年金や国民年金基金、個人型確定拠出年金(iDeCo)などに加入することを検討した方が良いかもしれません。
フリーランスや個人事業主は、老齢年金のほか、遺族年金や障害年金も基礎年金のみの受け取りになるため、受給額が少なくなります。
| 遺族年金 | 公的年金の被保険者が亡くなった場合に残された家族に支給される年金 |
| 障害年金 | 公的年金の被保険者が所定の障害認定を受けた場合に受給できる年金 |
フリーランスの場合、遺族基礎年金は子どもがいない配偶者には支給されません。
また、障害基礎年金は、受給対象が狭くなります。障害基礎年金が障害等級1級または2級に該当しなければ受け取れないのに対し、障害構成年金は障害等級が3級の場合でも受給可能です。
このように、フリーランスになると年金受給額や条件が大きく異なるため、自分で必要に応じて備えなければなりません。
出典:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
 フリーランスエンジニアが健康保険に加入する方法として、「国民健康保険に加入する」「家族の扶養に入る」「社会保険・被用者保険の任意継続」「国民健康保険組合への加入」の4つが挙げられます。
フリーランスエンジニアが健康保険に加入する方法として、「国民健康保険に加入する」「家族の扶養に入る」「社会保険・被用者保険の任意継続」「国民健康保険組合への加入」の4つが挙げられます。
それぞれ詳しく解説するので、自身のライフスタイルや状態にあわせて加入方法をご選択ください。
フリーランスエンジニアが加入できる健康保険の中でもっとも一般的なのが国民健康保険です。
国民健康保険には、各自治体が運営している「国民健康保険」と、同業種の方たちが集まって運営されている「国民健康保険組合(国保組合)」の2つがあります。
国民健康保険に変更する場合、会社を退職してから14日以内に手続きをしなければなりません。
出典:【資格】会社を辞めたので、国民健康保険の加入手続きをしたいのですが|江戸川区
▼関連記事
・フリーランスの健康保険の入り方を解説!
・フリーランスが国民健康保険を安くする方法を解説!
家族が健康保険に加入している場合、家族の扶養に入るという選択肢もあります。家族の扶養に入ると個人で保険料を支払う必要がないというメリットがあります。
家族の扶養になるためには、認定対象者の年間収入が130万円未満など一定の要件を満たさなくてはならず、収入が多い場合には加入できません。要件を満たしていれば、家族の扶養に入った方がお得でしょう。
出典:被扶養者とは?|全国健康保険協会
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
会社勤めからフリーランスになった場合、任意継続被保険者制度を利用する方法もあります。会社で加入していた保険を任意継続できる制度です。資格喪失の日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者期間があれば、2年間は任意継続できます。
ただし、任意継続する場合、これまで会社と折半していた保険料を全額自分で支払わなくてはなりません。負担が大きくなってしまうことを理解しておきましょう。
国民健康保険は、市区町村の地域によって加入先が決定するのに対し、国民健康保険組合は「業種や職種」によって加入できるものが異なります。どちらも同じ国民健康保険法に基づいて運営されています。
国民健康保険は所得に応じて保険料が変わりますが、国民保険組合の場合はほぼ一律で保険料が定められているので、高収入の人ほどお得になる仕組みです。
国民健康保険組合には、下記のようにさまざまな団体があります。
組合には誰でも加入できるわけではなく、特定の職種の方や資格取得者など条件が設けられています。
なお、個人事業主のエンジニアが加入できる可能性がある国民健康保険組合は、「文芸美術健康保険組合」です。文芸美術健康保険組合は、エンジニアをはじめとしたデザイナー、ライター、写真家といったクリエイティブ職の人を対象としている団体になります。
ほかにも、「全国ソフトウェア協同組合連合会」や「商工会議所」などもフリーランスエンジニアが加入できる可能性があるので、一度条件面をチェックしてみてください。
 フリーランスになると、これまで会社に任せていた手続きを自分でやらなければならず、大変に感じてしまいます。事前にどのような手続きをしなければならないか把握しておくことで、スムーズに動くことができるでしょう。
フリーランスになると、これまで会社に任せていた手続きを自分でやらなければならず、大変に感じてしまいます。事前にどのような手続きをしなければならないか把握しておくことで、スムーズに動くことができるでしょう。
ここでは、フリーランスになった場合、行いたい手続きを紹介します。ぜひ参考にしてください。
会社員時代に加入していた失業保険から、給付金を受け取る手続きをしましょう。
失業保険の給付金は、離職日以前2年間の間に12ヶ月以上の被保険者期間がある、再就職の意思がある、現在求職活動を行っているなどの要件を満たすことで受給可能です。
ただ、フリーランスとして事業をしながら給付金を受け取ることは禁止されており、違反するとペナルティが課されます。
給付金を受け取るためには、フリーランス業務を最低限に留めたり、開業届を出す時期に注意したりする必要があるでしょう。
フリーランスになった際、退職から14日以内にお住いの自治体の窓口で被用者保険から国民健康保険への切り替えを行わなければなりません。手続きには、健康保険の資格喪失証明書と本人確認書類が必要です。
ただし、任意継続保険を利用する場合には国民健康保険への切り替えは行う必要がありません。
フリーランスになったら、厚生年金から国民年金への切り替えも行わなくてはいけません。
退職日の翌日から14日以内に、お住いの自治体の窓口で手続きを行う必要があります。手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書、印鑑、身分証明書、離職票(退職日がわかる書類)などが必要です。
ただし、配偶者などの扶養に入る場合には、この手続きを行う必要はありません。配偶者などが勤務している会社などを通じて手続きをしてください。
▼関連記事

ここからは、フリーランスエンジニアが加入したい社会保険以外の制度について紹介します。
フリーランスエンジニアは社会保険(健康保険)以外に、年金保険への加入が必須です。年金は大きく分けて、国民年金、国民年金基金、付加年金があります。以下でこの3つについて詳しく説明しますので、参考にしてください。
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方に加入が義務づけられているものです。
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があり、フリーランスの方は第1号被保険者に該当します。保険料は年収や年齢に関係なく固定されており、令和3年度の保険料は1カ月当たり16,610円です。
出典:公的年金の種類と加入する制度|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20140710.html
出典:国民年金保険料|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html
フリーランスエンジニアが加入できる年金として、国民年金基金があります。国民年金だけでは不安な方が、将来受け取る年金を増やすために加入するものです。
国民年金基金には、掛金は全額社会保険料控除となる、公的年金等控除の対象になる、ライフプランに合わせて年金額や受取期間を設定できるなどさまざまなメリットがあります。
加入後も年金や掛金の額を増やしたり減らしたりできるので、収入に合わせて設定しましょう。
出典:国民年金基金制度|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059350.html
付加年金も第1号被保険者であるフリーランスエンジニアが加入できる年金です。付加年金に加入することで、将来もらえる年金額を増やすことができます。
付加保険料の月額400円を支払うことで、「200円×付加保険料納付月数」だけ年金を増やせる制度です。
ただ国民年金基金を加入中の方は、付加年金には加入できませんので注意しましょう。
出典:付加年金|日本年金機構
 フリーランスや自営業、個人事業主として事業を営む人は、会社員よりも社会保障が充実していないため、民間保険に加入して不足分を補う必要があります。ここでは、フリーランスや自営業、個人事業主の方に加入をおすすめする民間保険を6つご紹介するので必要に応じてご検討ください。
フリーランスや自営業、個人事業主として事業を営む人は、会社員よりも社会保障が充実していないため、民間保険に加入して不足分を補う必要があります。ここでは、フリーランスや自営業、個人事業主の方に加入をおすすめする民間保険を6つご紹介するので必要に応じてご検討ください。
もちろん、ここでご紹介する民間保険のすべてに加入する必要はありません。自分自身の生活背景やご予算などに合うものを選択することが大切です。
医療保険とは、病気や事故などの怪我で通院・入院した場合に、医療費負担を軽減してくれる制度のことです。
基本的に会社員が加入する「健康保険」では、傷病手当金や出産手当金が支給されますが、フリーランスが加入する「国民健康保険」はこれらの保障がありません。
民間の医療保険は、傷病手当金や出産手当金の給付に加え、公的医療保険ではカバーできない部分にも備えられます。具体的には、病気やケガで働けなくなった場合の保障や、三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)になった場合の保障、所定の介護状態や認知症になった場合の保障などが挙げられます。
さまざまなニーズに応える「オリックス生命」
「オリックス生命」は、医療保険はもちろんのこと、がん保険や死亡保険、収入保障保険などさまざまなニーズに応える保険商品が充実しています。
フリーランスや自営業などの個人事業主におすすめの収入保障保険(家族をささえる保険Keep)もあります。「家族をささえる保険Keep」は、もしものときに家族を守れる保険商品で、保険期間中に亡くなったとき、または病気・ケガにより約款所定の高度障害状態に該当したときに、毎月決まった金額(収入保障年金または高度障害年金)を保険期間満了まで受け取ることが可能です。
ほかにも、病気・ケガによる入院を一生涯保障してくれる「医療保険CURE Next [キュア・ネクスト]」など、お手頃な保険料で手厚い保障を受けられるものが豊富ですので、万が一のときに備えたい方はぜひチェックしてみてください。
手軽に医療保険やがん保険、死亡保険を資料請求|オリックス生命
就業不能保険は、病気や怪我で長期的に働けなくなった際の収入減少に備える保険です。所得補償保険は、短期的に働けなくなった際の収入減少に備える保険です。
会社員が加入する「健康保険」は、病気や怪我で働けなくなった場合、最大1年6ヶ月間給与の約3分の2を支給される傷病手当金がありますが、フリーランスは基本的にこのような制度がないため、就業不能保険あるいは、所得補償保険で備えておくと安心できるでしょう。
個人年金保険とは、契約時に定めた年齢まで保険料を支払い続けて、支払い金額に応じた給付を受け取る仕組みの保険です。
フリーランスは会社員よりも老後にもらう年金額が少ないため、もらえなかった場合の不足分を補うために加入する人が多いです。
ここ数年では、会社員であっても個人年金保険に加入し、老後に不足する可能性がある生活資金を準備している人も増えてきています。
 最後に、フリーランスから法人化した場合に必要となる手続きを紹介します。
最後に、フリーランスから法人化した場合に必要となる手続きを紹介します。
法人化した場合、社会保険への加入が必須です。従業員が1人でも社会保険に加入しなくてはいけません。健康保険と厚生年金に加入する手続きと国民健康保険から脱退する手続きが必要です。以下では、詳しい手続きの方法について紹介します。
法人化した場合、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられているため、「新規適用届」を提出して加入手続きをしなくてはいけません。
会社設立から5日以内に会社所在地を所轄する年金事務所に届け出る必要があり、会社の登記簿謄本の原本の添付が必要です。
また被保険者になる方、全員分の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出もしなくてはいけません。
出典:就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き|日本年金機構
法人化した場合、社会保険(健康保険)に強制加入することになるため、フリーランスのときに利用していた国民健康保険の脱退手続きをしなくてはいけません。社会保険に加入することで、自動的に脱退手続きが行われるわけではないため注意しましょう。
手続きは住んでいる自治体の窓口で行います。手続きには、加入した社会保険の保険証と国民健康保険証、本人確認書類、個人番号確認書類が必要です。

国民健康保険の保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料、介護分保険料の3つで形成されており、所得割、資産割、均等割、平等割の4つの賦課基準から計算された金額を合わせて世帯ごとの保険料が決定します。
自治体ごとに賦課方式や料率に違いがあり、保険料にバラつきがあるため一概に所得が〇円なら保険料は△円とはなりません。
たとえば、40歳未満の1人世帯で所得が202万円の場合、年間の保険料は横浜市では197,490円であるのに対して、札幌市では251,580円となっています。このように国民健康保険料には地域格差があるため、詳しい保険料を知りたい場合は自治体に問い合わせた方がいいでしょう。
出典:保険料について|横浜市
 フリーランスエンジニアになると、会社と折半して支払っていた保険料を自分で全額支払わなければなりません。支払ってみると意外に負担が大きく、できるだけ節約したいと考える方も多いでしょう。
フリーランスエンジニアになると、会社と折半して支払っていた保険料を自分で全額支払わなければなりません。支払ってみると意外に負担が大きく、できるだけ節約したいと考える方も多いでしょう。
ここでは、フリーランスエンジニアの保険料を節約する6つの方法を紹介します。節約したいと思っている方はぜひ参考にしてください。
国民健康保険と任意継続保険のどちらが得かを考えましょう。
国民健康保険の保険料には所得が一定水準を下回ると減額され、所得が上がると保険料が割高になります。一方、任意継続保険の保険料は所得によって保険料は変わることはなく一定です。所得が高い方ほど任意継続保険のほうがお得と言えます。
また、国民健康保険には扶養という概念がなく、扶養家族がいるとその分保険料が高くなってしまいますが、任意継続保険には扶養制度があり扶養家族が居ても保険料は変わりません。扶養家族が多い方ほど、任意継続したほうがいいです。
このほか、疾病手当金や出産手当金の支給に関しても違いがあり、保険料を節約するためには総合的に見てどちらが得か考える必要があるでしょう。
出典:退職後の健康保険 – 国民健康保険と健康保険任意継続制度を比較|マネーフォワード
国民年金の支払いは、クレジットカードで行うことで節約につながります。
国民年金の支払いをクレジットカードにするメリットは、ポイントやマイルが貯まることです。貯まったポイントは支払いに利用できたり、ギフト券や商品に交換できたりする場合があります。
ただし、国民年金の支払いではポイントやマイルが貯まらないカードもあるため、自分が持っているカードでの支払いがポイント付与の対象か確認する必要があるでしょう。
前述しましたが、国民健康保険の保険料は自治体により差があるため、負担が軽い自治体へ引っ越すのも一つです。
それぞれが置かれている状況により保険料は異なりますが、最も高い自治体と最も低い自治体では2倍以上の差があります。
フリーランスは誰からも住む場所を限定されないため、そのメリットを活かして負担の軽い自治体への引っ越しも検討しましょう。
文芸美術国民健康保険組合は、文芸、美術、著作活動などに従事しており、組合加盟団体に属している方とその家族のための健康保険組合です。
国民健康保険と違い文芸美術国民健康保険組合は、保険料が収入により変わることはなく一定というメリットがあります。収入が多い方は、国民健康保険に加入するよりも保険料を節約できる可能性があるでしょう。
ただし、加入できるのはエンジニアの中でもWebデザインの仕事をする方だけに限られ、すべてのフリーエンジニアが加入できるわけではありません。Webデザイナーの業務を請け負う方は、加入を検討してみましょう。
確定申告を青色申告で行うことでも、国民健康保険の保険料を節約できます。
青色申告では、複式帳簿での記帳、貸借対照表および損益計算書の添付、期限内の申告を満たすことで55万円の特別控除を受けることが可能です。さらに、e-Taxによる電子申告もしくは電子帳簿保存を満たすことで10万円の控除を受けられます。
青色申告では最大65万円の特別控除を受けられるため、所得金額が下がり国民健康保険料の節約が可能です。
▼関連記事
・フリーランスは確定申告をするべき?初めての人でも分かるやり方と節税方法まで解説
フリーランスエンジニアになると確定申告を自分で行います。確定申告の際に、必要な経費は全て計上することが重要です。
国民健康保険の保険料は所得に応じて決定し、所得が低ければ保険料の負担が軽くなります。保険料の計算には、収入金額から控除と必要経費を差し引いた所得が使われるため、必要な経費を全て計上しないと損です。
▼関連記事
「特別受託事業者」にあたる企業から業務委託を受けている事業者やフリーランスは、令和6年11月より労災保険に特別加入できるようになります。
労災保険に加入することで、仕事中や通勤中の怪我や病気、障害、または死亡などに対して補償を受けられます。
給付内容としては、ケガなどの治療費の給付やケガで休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付などが挙げられます。死亡した場合、遺族への給付などが支給されます。
労災保険への特別加入を希望される方は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体への申込手続きを行いましょう。
フリーランスのITエンジニアは、「一般社団法人 ITフリーランス支援機構」が設立した特別加入団体にて申請手続きを行ってください。
出典:令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
出典:フリーランス※の皆さまも、 - 特別加入により労災保険の補償
 フリーランスの保険に関するよくある質問に対して、Q&A形式で回答します。
フリーランスの保険に関するよくある質問に対して、Q&A形式で回答します。
個人事業主やフリーランス、自営業者は会社員よりも社会保障制度が充実していないので、収入減に備えられる「就業不能保険」への加入を推奨します。
自営業者や個人事業主、フリーランスにおすすめの保険は下記の通りです。
なお、「国民健康保険」と「国民年金保険」については加入する必要がある公的保険です。
自営業や個人事業主(フリーランス)が生命保険料を経費として計上することはできません。
「経費として計上できるもの=事業に必要なもの」という考え方ですので、個人のものである生命保険は経費に該当しません。
ただし、個人事業主の場合は生命保険料控除があるため、税金の負担が軽くなります。
フリーランスは、個人で事業を営む「自営業者」として扱われるため、法律上「国民健康保険」と「国民年金」への加入が義務づけられています。
会社員が加入できる保険は、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の4つあるため、フリーランスは比較的加入義務が少なくなります。その分、備えが不十分だといえるので、民間保険に加入するフリーランスも増えています。
出典:地方厚生局「社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?」
フリーランスは、年金保険である「国民年金保険」に加入します。厚生年金のように会社と折半ができないため、全額自己負担となります。
国民年金の保険料は、年間を通して一律となっており、所得に左右されないことが特徴です。令和4年度では一律16,590円、令和5年度は一律16,520円となっています。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?」
本記事では、フリーランスエンジニアが加入できる社会保険やフリーランスになったら行いたい手続きなどについて紹介してきました。
フリーランスになると会社勤めをしていたときとは異なり、すべて自分で行わなければなりません。やらなければならないことが多く面倒に感じてしまうでしょうが、社会保険はいざというときに役立ちます。
手続きを漏れなく行うために、フリーランスが加入すべき社会保険について事前に理解しておくようにしましょう。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く