40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】

フリーランスになる際は、どのように加入する保険を選択すればよいのでしょうか。この記事では、フリーランスが加入できる保険の種類について紹介します。また、万が一のリスクに備える補償についても紹介しているため、フリーランスで働き始める方は、ぜひ参考にしてみてください。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
「フリーランスとして働きたいけれど、保険ってどうしたらいいの?」
「会社員とフリーランスで、補償の違いってあるのかな?」
「フリーランス向けに、加入できる補償があるのか知りたい」
このように、フリーランスになることを目指す上で、保険や補償についての心配はつきものです。
この記事では、フリーランスになる際に選択できる、健康保険の加入方法について紹介します。
そのほか、フリーランスになったときに起こりうるリスクに備えて、万が一の際にサポートが得られる補償も解説しています。
この記事を読むことで、フリーランスに必要な保険や補償の知識を得ることができます。
今後、フリーランスになることを目指している方は、ぜひ参考にしてください。
また、会社員は雇用保険や労災保険にも自動で加入しますが、フリーランスは原則対象外となります。
任意加入できる制度もありますが、加入手続きは自分で行う必要があります。そのため、保険制度の違いを理解し、自衛手段を整えることが重要です。
日本の社会保険制度は、「健康保険」「介護保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5つで構成されています。
会社員はこれらすべてに加入しますが、フリーランスや個人事業主は対象外の保険もあります。それぞれの役割や加入条件を理解して、自分に合った保障を選ぶことが大切です。
出典:厚生労働省|被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について
健康保険は、病気やけが、出産時の医療費負担を軽減する制度です。会社員は「協会けんぽ」や「組合健保」に加入し、保険料は会社と折半となります。
一方、フリーランスは「国民健康保険」に加入し、保険料は全額自己負担です。扶養制度の有無や出産手当金の支給など、制度によって給付内容に差があるので正しく理解しておきましょう。
介護保険は、介護が必要になった際の経済的な負担を軽減し、社会全体で支え合うために設けられた公的制度です。
フリーランスも40歳になると自動的に加入対象となり、保険料の納付が始まります。介護保険に関しては、特別な手続きは不要です。
被保険者は年齢によって「第1号(65歳以上)」と「第2号(40〜64歳)」に分類され、それぞれ給付条件が異なります。
65歳以上の方は、介護が必要と認定されれば、原因を問わず介護保険のサービスを利用することが可能です。一方、40〜64歳の方は、がんや関節リウマチなど、老化が原因とされる特定の病気によって介護が必要になった場合に限り、給付を受けることができます。
フリーランスの場合、原則として国民年金に加入しますが、会社員や法人化した場合などで厚生年金に加入するケースもあります。厚生年金の保険料は、報酬月額や賞与に18.3%の保険料率をかけて算出され、会社と本人が折半で負担します。
報酬には基本給だけでなく通勤手当や各種手当も含まれ、年に一度の見直し(定時決定)や報酬の大幅な変動があった際の再計算(随時改定)によって保険料が調整されます。
なお、フリーランスとして厚生年金に加入するには、法人設立や契約内容の見直しなどが必要です。
雇用保険は、主に労働者の失業時や教育訓練時の生活と就労支援を目的とした制度で、企業に雇われている人が対象です。そのため、フリーランスは原則として加入できません。
ただし、一定の条件を満たす複数事業従事者(マルチジョブホルダー)向けの制度や、離職後にフリーランスとして独立した場合に受給期間の延長特例が認められるケースもあります。
再就職手当や教育訓練給付金などの制度も存在しますが、いずれも要件が細かいため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
2024年11月から、フリーランスも労災保険に「特別加入」できるようになりました。企業などから業務委託を受けて働いている場合、業種や職種を問わず対象となり、業務中や通勤中のケガ、病気、死亡時に補償が受けられます。
加入を希望する場合は、厚生労働省が承認した特別加入団体を通じて手続きを行う必要があるので事前に確認しておきましょう。
ただし、個人の消費者からのみ仕事を請け負う場合は、対象外となるため注意が必要です。フリーランスにとって重要なセーフティーネットの一つですので、以下のページを参考にしてみてくださいね。
出典:令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました|厚生労働省
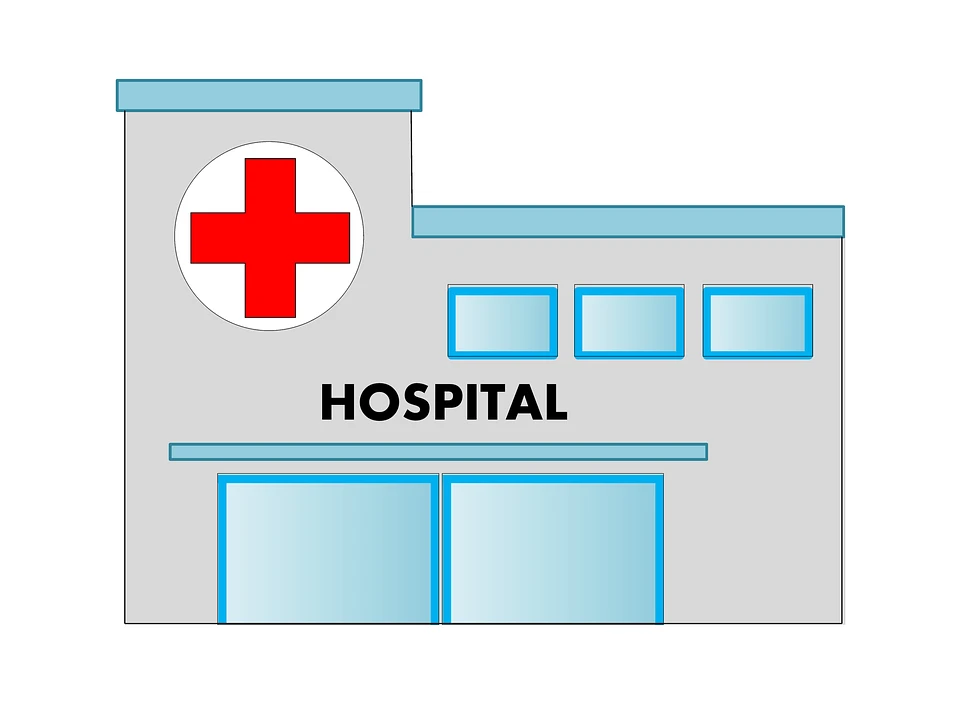
フリーランスのエンジニアが加入できる健康保険は、いくつか選択肢があります。
基本となるのは在住する自治体による国民健康保険への加入ですが、国民健康保険組合への加入や家族の扶養に入る方法、所属していた会社の健康保険を任意継続する方法などもあります。
以下では、それぞれの特徴や違いについて紹介します。
在住する自治体(市町村)が保険者となる国民健康保険は、フリーランスも加入することができます。
原則として、会社を退職してから14日以内に加入する必要があり、保険料は前年度の収入や自治体によって異なります。また、在職時に家族を扶養に入れていた場合は、今まで負担が無かった家族分の保険料も納付する必要があるため注意が必要です。
納入した保険料は、所得控除の対象となりますので、忘れずに確定申告の際に申告しましょう。
出典:千代田区ホームページ - 国民健康保険(国保)のしくみと手続き参照
出典:No.1130 社会保険料控除|国税庁
国民健康保険に加入する際は、住所地の市区町村へ届け出を行います。市役所や役場にて受け付けており、自治体によってはオンラインでの手続きができる場合もあります。各自治体のWebサイトなどで確認しましょう。
健康保険の資格喪失日等を確認するため、健康保険資格喪失証明書が必要となります。そのほかに、届出人の本人確認資料(マイナンバーカード等)やマイナンバーの確認書類が必要です。
届け出する市区町村により、キャッシュカード等が必要となる場合もあります。詳しくは、各自治体のホームページを確認しましょう。
家族が会社員等として働き加入している健康保険組合に、被扶養者として加入することもフリーランスがとれる選択肢です。
ただし、被扶養者として加入するには、年収130万円未満で被保険者の年間収入の2分の1未満であること、加入している家族(被保険者)に生計を維持されていることなどの条件があります。
フリーランスの場合は、収入から控除できる経費が事業所得の経費とは異なりますので、加入を希望する場合は各組合の算定基準を問い合わせてみましょう。
被扶養者の該当条件から外れてしまう場合は、他の健康保険に加入する必要があります。
会社を退職してフリーランス(自営業)になる場合、希望すれば健康保険の任意継続が可能です。
退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること、退職日から20日以内に申請することなどの条件があります。
また、加入できる期間は2年間で、在職中は会社と折半していた保険料が全額自己負担となり、傷病手当金や出産手当金を受けることはできなくなるため注意しましょう。
地域ごとに同種の事業や業務に従事する者で組織された国民健康保険組合に加入することも、フリーランスの選択肢です。ただし、該当する職種や地域は限られ、各組合の定める条件に該当する必要があります。
対象は個人事業主であることが条件です。業種については医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、理・美容師、建設業界、食品業界などがあり、保険料は多くの組合で定額になっているのが特徴です。また、扶養制度がないため、家族分も保険料が掛かりますが、130万円以上の収入があっても被保険者に該当します。
出典:国民健康保険組合
文芸美術国民健康保険組合はクリエイティブ関連の職を対象とした健康保険組合です。
対象者は文芸、美術及び著作活動に従事し組合加盟の各団体の会員である者とその家族となっています。保険料は収入で変わらず一律です。
フリーランスエンジニア全般が対象にはなりませんが、Webデザイン、Webライティング、ゲームシナリオライティング、ネットクリエイティブ、CG・VFXの職域に属する仕事をしている人であれば加入できる場合もありますので、検討の余地があるといえるでしょう。
美容師やエステティシャンなど、美容業界で働く個人事業主やフリーランスが加入できる業種特化型の健康保険組合です。
国民健康保険より保険料が割安で、出産育児一時金や傷病手当金などの給付制度も充実しています。東京都内の美容業に従事していることが加入条件となりますが、フリーランスで安定した保障を得たい人にとっては非常に有利な制度です。詳しくは公式サイトで最新情報を確認しましょう。
出典:東京美容国民健康保険組合
ITエンジニアやプログラマー、ソフトウェア開発に携わるフリーランス向けの健康保険制度を提供している団体です。
全国ソフトウェア連合会を通じて「文芸美術国民健康保険組合」に加入でき、保険料が比較的安価で給付も手厚い点が魅力です。組合員として一定の活動実績が必要ですが、フリーランスのIT従事者にとって心強い選択肢となります。加入条件や必要書類は事前に確認が必要です。
 フリーランスとして働く場合、会社員とは異なる年金制度に加入することになります。国民年金を基本に、将来の受給額を増やすための上乗せ制度も選択できます。ここでは、フリーランスが加入できる年金保険の種類や特徴、手続き方法について詳しく解説します。
フリーランスとして働く場合、会社員とは異なる年金制度に加入することになります。国民年金を基本に、将来の受給額を増やすための上乗せ制度も選択できます。ここでは、フリーランスが加入できる年金保険の種類や特徴、手続き方法について詳しく解説します。老後に受け取れる「老齢基礎年金」のほか、障害や死亡時の保障も用意されているのが特徴です。会社員のような厚生年金の上乗せがないため、将来の年金額が少なくなる傾向があり、自助努力が求められます。未納や滞納を防ぐため、口座振替などでの支払い管理を行うと良いでしょう。
国民年金だけでは将来の年金額が不安なフリーランスに向けた、公的な上乗せ年金制度です。
加入は任意で、60歳まで積み立てることができます。掛金や給付のタイプを選べるため、自分のライフプランに応じた設計が可能です。掛金は全額が所得控除の対象となるため、節税効果も期待できます。職業によっては加入できない場合もあるため、条件を確認しておきましょう。
出典:国民年金基金連合会
「2年で元が取れる」と言われるほど効率的で、少額ながら長期的な効果があります。ただし、国民年金基金と併用はできないため、どちらか一方を選ぶ必要があります。将来的にiDeCoなどを併用する予定がない方や、手軽に年金を増やしたい方におすすめです。
出典:付加年金
掛金は全額所得控除の対象で、運用益も非課税となるため、節税メリットが大きいと言えるでしょう。フリーランスの場合、月額の掛金上限は68,000円(年間81.6万円)となっており、積極的な資産形成が可能です。ただし、原則60歳まで引き出せないため、長期運用を前提とした設計が必要です。
出典:iDeCo
フリーランスとして開業した場合、14日以内に住所地の市区町村役所で「国民年金の第1号被保険者」としての届出が必要です。
国民年金基金や付加年金、iDeCoはそれぞれの運営団体や金融機関で別途申し込みを行います。申請にはマイナンバーや本人確認書類、印鑑などが必要です。未納期間を作らないよう、早めに手続きを済ませましょう。なお、口座振替やクレジットカード払いも選択できます。
どの保険に加入するかによって、手続き先や必要書類、期限が異なるため、事前に流れを把握しておくことが重要です。ここでは、代表的な保険の切り替え方法をわかりやすく解説します。
手続きは退職日の翌日から14日以内に、住民票のある市区町村の役所で行います。
必要書類は、退職証明書や離職票、本人確認書類、印鑑などです。保険料は所得に応じて決まり、年4回または月ごとの納付が選べます。滞納すると保険証が使えなくなることもあるため、早めに手続きを済ませましょう。
申請期限は退職日の翌日から20日以内で、加入している健康保険組合に申請が必要です。保険料は全額自己負担(会社負担分も含む)となるため、国民健康保険と比較して保険料が割高になる場合もあります。ただし、扶養制度の継続や、給付内容が変わらない点はメリットです。
出典:任意継続の加入手続きについて | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
収入が年間130万円未満(被保険者が年収の2分の1以上を負担している場合)などが主な条件です。加入申請は扶養者の勤務先を通じて行い、収入証明書類や続柄がわかる書類などが必要です。保険料負担がなくなる点は大きなメリットです。
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
国民健康保険組合に加入する方法美容師やデザイナー、ITエンジニアなど、特定の業種で働くフリーランスは、業種別に設けられた「国民健康保険組合」に加入できる場合があります。
加入には、業種団体への所属や業務実績の証明などが必要で、各組合の定める条件を満たさなければなりません。保険料が比較的割安で、出産手当金や傷病手当金などの給付がある組合もあります。詳細は各組合の公式サイトで確認しましょう。
保険料は収入や自治体によって異なり、計算方法や支払い方法も会社員時代とは異なります。ここでは、健康保険や年金保険の保険料の目安と、払えないときの対処法を紹介します。
基本的には「所得割(所得に応じて決まる)」「均等割(人数に応じて一律)」「平等割(世帯単位で一律)」などの合計で決まります。保険料率や減額制度は自治体ごとに異なるため、正確な金額はお住まいの市区町村のサイトで確認が必要です。任意継続や国保組合への加入も選択肢となるため、比較検討するとよいでしょう。
2025年度の保険料は月額17,510円(前納や口座振替による割引制度あり)となっています。収入が少ない場合は、免除や猶予制度を申請することで保険料の負担を軽減できます。
ただし、免除期間中は将来の年金額が減額されるため注意が必要です。安定した老後のためにも、可能な限り納付を継続するか、上乗せ制度(付加年金やiDeCo)も活用しましょう。
国民年金には全額免除・一部免除・学生納付特例制度があり、国民健康保険も所得に応じた減免措置が設けられています。手続きは市区町村役所で行い、必要書類として所得申告や本人確認書類などが求められます。制度を正しく使えば、将来の保障を守りつつ負担を軽減できます。
保険料は前年の所得に応じて決まるため、収入が増えるほど負担も大きくなります。ただし、いくつかの工夫をすることで、保険料を抑えることが可能です。ここでは、自治体の選び方や各種制度の活用、節税対策など、フリーランスが実践できる保険料節約の方法を紹介します。
例えば、所得割や均等割、平等割などの比率は自治体ごとに独自に設定されており、都市部より地方の方が安い傾向にあります。住居や事業拠点の移転が可能であれば、保険料が安い自治体への引っ越しは現実的な節約手段の一つです。ただし、医療機関の充実度や交通アクセスなども併せて検討しましょう。
たとえば、所得が住民税非課税レベルであれば、均等割・平等割が7〜9割軽減されることもあります。自然災害や失業、病気による一時的な収入減でも減免が適用される場合があるため、役所に相談する価値があります。申請には所得証明や理由書などが必要なので、早めの準備がカギです。
フリーランスは確定申告で事業に関する経費を適切に計上することで、課税対象となる所得を抑えることができます。
所得が減れば、当然ながら国民健康保険料の負担も軽くなります。家賃の按分、通信費、業務用の備品など、漏れなく経費処理することが重要です。帳簿管理やレシート保存を徹底し、青色申告特別控除も活用すれば、節税効果はさらに高まります。税理士や会計ソフトの活用もおすすめです。
たとえば、美容業やデザイン業、IT業などの業種別組合では、保険料が国民健康保険より割安で、手当金などの給付が充実している場合も。加入には実務経験や業種団体への所属が条件となることがあるため、事前に条件や必要書類を確認しておきましょう。
配偶者などが会社の健康保険に加入している場合、自身の年収が一定額以下であれば「扶養家族」として保険に入ることが可能です。
年間130万円未満(または106万円未満の条件もあり)に収めれば、保険料の自己負担が不要になり、大きな節約になります。ただし、事業の規模を抑える必要があるため、将来の働き方や収入目標とバランスを取りながら判断することが重要です。

フリーランスは健康保険料を全て自己負担する必要があります。
支払った保険料は所得控除の対象になり節税効果が期待できますが、そもそも支払う金額を抑えたいと思うこともあるでしょう。
ここでは、フリーランスが健康保険料を抑えるアイデアを紹介します。
まずは自分の所得を知り、どの健康保険に加入すればいいのか検討しましょう。
まだフリーランスに転向したばかり等で年収が130万円未満に収まる場合は、家族の健康保険に扶養として加入することを検討するのがおすすめです。
逆に収入が高く、国民健康保険では保険料が高額になってしまう場合は、保険料が一律であることが多い国民健康保険組合や、退職した会社の健康保険を任意継続することを検討するのもいいでしょう。
自治体による国民健康保険は、地域によって保険料に差があります。
国民健康保険は前年度の収入によって保険料が決まりますが、地域や年度によっても異なり、その差が約2倍以上になることもあります。
引っ越しを検討している場合は、転居先の自治体のホームページ等で保険料を確認するといいでしょう。
ここまで、フリーランスのエンジニアが加入できる健康保険や、保険料を抑える方法について紹介しました。
公的医療保険は義務となっているため加入しなくてはなりませんが、いざという時の備えになります。
ここからは各健康保険の詳細について把握して、ご自分に合った健康保険を検討しましょう。
フリーランスエンジニアやWebデザイナーは、自由な働き方ができるというメリットがあります。その半面、仕事上で起きるトラブルへの対応も、自分自身で全て行わなければなりません。
万が一のリスクに備え、フリーランスとして働いていくために必要な補償について紹介します。
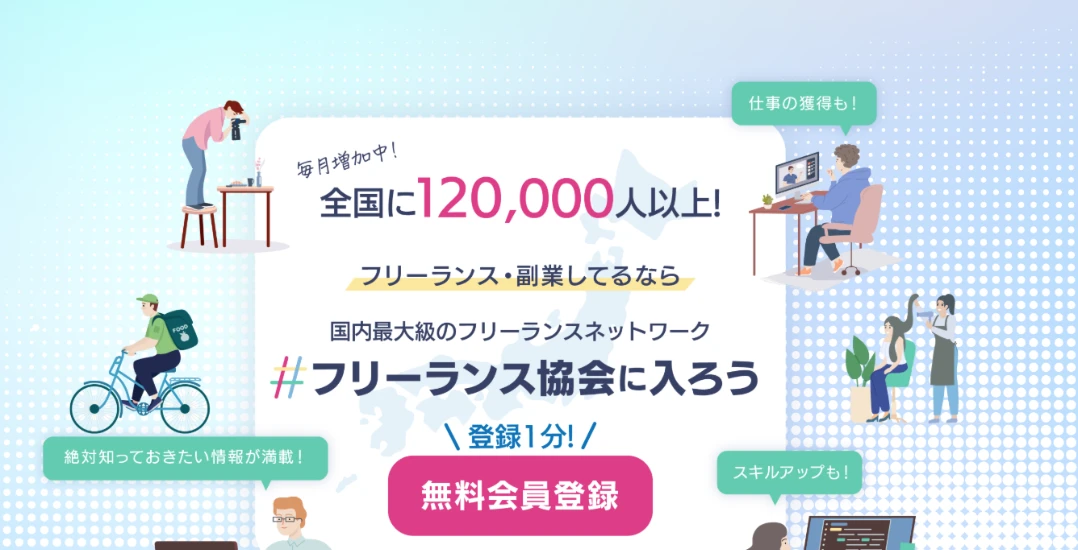
出典:フリーランス協会
プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会は、フリーランスのための非営利団体です。年間1万円の会費で賠償責任補償や弁護士費用保険などが自動付帯される「ベネフィットプラン」を提供しています。
加えて、収入補償や介護保険、福利厚生サービスを利用できることも魅力です。具体的には、「報酬未払い」「納品トラブル」「情報漏えい」など、フリーランス特有のリスクに対応した手厚い保険が特徴だといえるでしょう。
以下のボタンから公式サイトを開いて会員登録をすると、年会費5,000円のライトプランへ入会できます。一般会員と比べると一部サービスが制限されますが、5,000円もお得に加入できるため、ぜひこの機会に検討してみてくださいね。
フリーランス協会をチェック
賠償責任補償とは、業務上のトラブルで賠償請求された際などに補償が受けられる保険です。
フリーランスは、情報漏えい、著作権の侵害や納期の遅延など、さまざまな業務上のリスクが想定されます。このようなリスクを回避するためには、業務契約する際に結ぶ「業務委託契約書」を、入念に確認することも重要です。
事前に契約内容を確認し、さらに賠償責任補償の保険に加入することで、フリーランスの業務で想定されるリスクを大きく減らすことができます。
所得補償保険とは、病気やケガなどで働けなくなってしまった場合に保険金が支払われる、民間の任意保険です。
多くのフリーランスが加入している国民健康保険には、傷病手当金の制度がありません。個人事業主であるフリーランスは、雇用保険の加入も認められないため、失業保険などの補償も受けられないことになります。
さまざまな状況で働けなくなってしまうリスクに備え、所得補償保険への加入を検討しましょう。
労災保険は、労働者が仕事中などに被ったケガや病気に対し、補償を受けられる保険です。
フリーランスエンジニアやWebデザイナーの方は、労災保険に任意で特別加入することができます。特別加入した場合、ケガの治療などの療養費や治療のために休業した期間の給付などが受けられ、さまざまなリスクに備えることが可能です。
労災保険は、国が補償している制度のため、手厚い補償が受けられます。詳しい内容は、厚生労働省のホームページで確認しましょう。
ここでは、フリーランスが加入を検討できる「国民健康保険組合」に関するよくある疑問について解説します。保険料を抑えたい、手厚い保障を受けたいという方にとって、国保組合は魅力的な選択肢の1つです。
通常の国民健康保険との違いや、加入条件、保険料の目安などを分かりやすく説明していきますので、ご自身に合った保険制度を選ぶ参考にしてください。
フリーランスが国民健康保険料を抑えるには、いくつかの工夫があります。まず、所得控除を活用して課税所得を下げること。経費の適正計上や青色申告の特別控除を利用するのも効果的です。
また、所得が一定基準以下の場合、自治体による保険料の軽減・減免制度を申請できます。さらに、保険料が割安な国民健康保険組合への加入や、家族の扶養に入るという選択肢もあります。状況に応じて最適な方法を選びましょう。
国民健康保険料は自治体ごとに異なり、前年の所得や世帯人数によって変動します。たとえば、所得が300万円の場合、保険料は年間30万〜45万円前後になることもあるようです。(※自治体によって差あり)
このほか、均等割や平等割といった一律の金額も加算されます。正確な金額は市区町村の窓口またはホームページで確認できます。節税や軽減措置の活用で、保険料の負担を減らすことも検討しましょう。
出典:令和6年度 国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等)
年収500万円のフリーランスが国民健康保険に加入した場合、自治体にもよりますが、保険料は年間約45万〜65万円が目安です。
所得から必要経費や各種控除を引いた「課税所得」に基づいて算出され、これに所得割や均等割、平等割が加わります。
正確な額を知りたい場合は、住んでいる市区町村の保険料試算ツールや窓口で確認しましょう。節税や控除の活用で負担軽減も可能です。
原則として、日本に住むすべての人は何らかの公的医療保険に加入する義務があります。フリーランスが国民健康保険に加入しない方法としては、配偶者や親の健康保険の扶養に入ること、あるいは退職後に前職の健康保険を任意継続することが考えられます。
ただし、収入要件や期限があるため注意が必要です。いずれの方法も条件を満たせば合法的に国保に加入せず保険制度を利用できます。
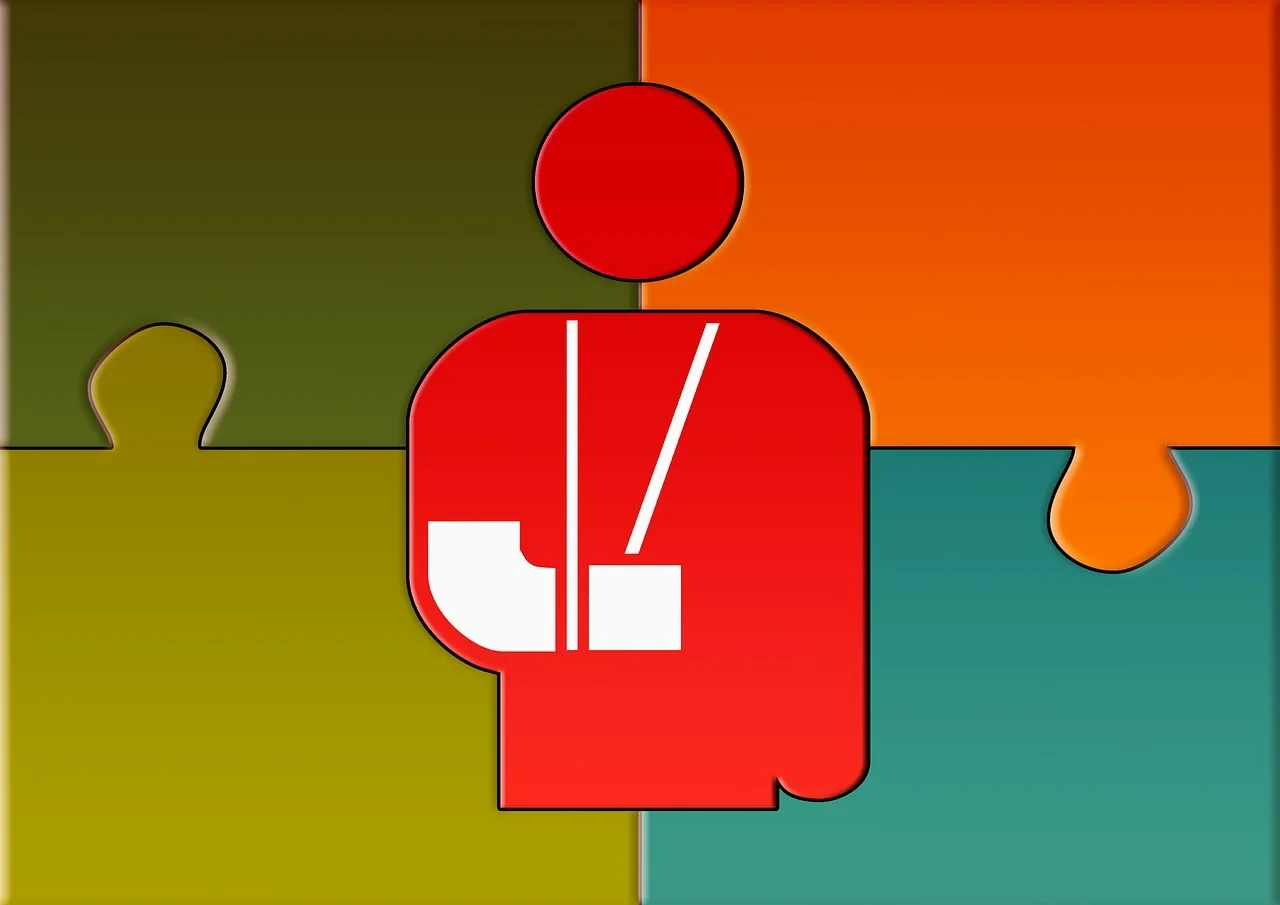
本記事では、フリーランスのエンジニアが加入できる健康保険や、保険料を抑える方法について紹介しました。
公的医療保険は義務となっているため加入しなくてはなりませんが、いざという時の備えになります。
各健康保険の詳細について把握して、ご自分に合った健康保険を検討しましょう。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く