40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
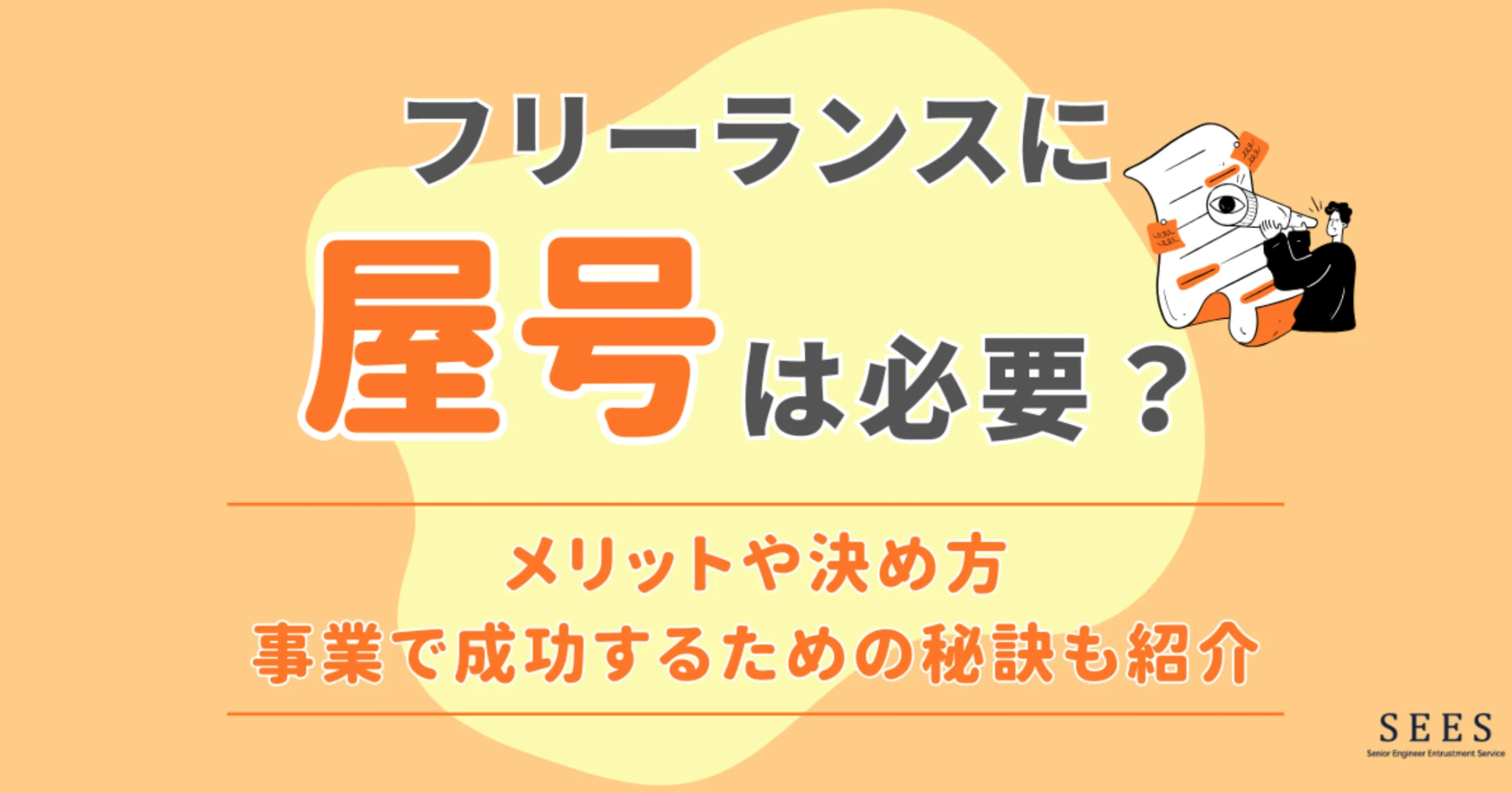
屋号とは、フリーランスや個人事業主がビジネス上で用いる商業用の名称のことです。
屋号は必要なのか、どのような屋号を付けるべきか迷っているフリーランスに向けて、付け方や必要性、メリット・デメリットをまとめました。屋号のネーミング例を一覧表にまとめているので参考にしてみてください。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
屋号は、フリーランスや個人事業主がビジネスで使用する名称です。ただ、法律で屋号の設定を義務づけられているわけではないため、フリーランスとして開業する際に、屋号が必要かどうかを考える方は少なくありません。
屋号を設定しておくと、本名を公表せずに活動できたり、取引先からの信用度を高めたりできる強みがあります。一方で、ネーミングに時間がかかることや、変更時の手間などデメリットも存在します。
もし、これからフリーランスや個人事業主として活動する場合には、屋号のメリットやデメリット、名称の決め方を理解しておくと、事業の成功に繋がる屋号がつけられるかもしれません。
本記事では、フリーランスに屋号は必要なのかについて、メリットや決め方、事業で成功するための秘訣を解説します。
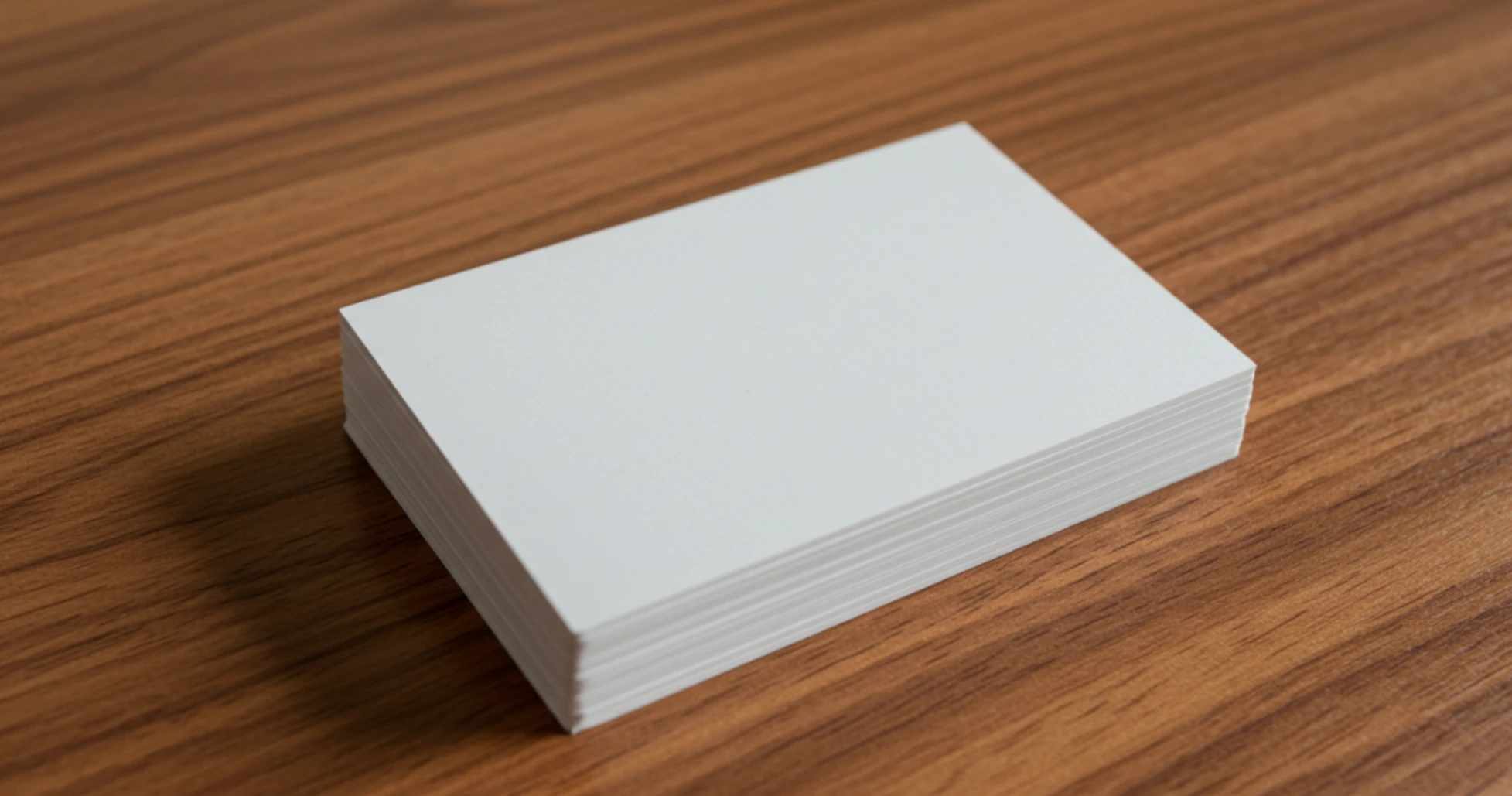
屋号は、フリーランスや個人事業主が名刺や請求書などで使用する「ビジネスネーム」です。法人の登記名(商号)とは異なり、自分の裁量で自由に決められます。
屋号を設定しておけば、SNSやWebサイトでブランディングを向上させる効果を狙えたり、フリーランスとして活動する際に「どのような仕事をしているか」を相手に伝えや少なるメリットがあります。他にも、経理作業の場面でも、屋号を統一しておくことで経費や売上の区別が明確になりやすく、銀行口座の開設時にもスムーズに事業用とプライベート用をわけることが可能です。
このようなメリットから、実務面やブランディング面で屋号を活用するフリーランスが少なくありません。

「雅号」や「商号」といった言葉は「屋号」と似ていますが、使われる目的や対象が異なります。これらの言葉を混合して認識していると、屋号をつける際にトラブルになりかねないため、それぞれの言葉の正しい意味を理解しておくことが大切です。
ここでは、屋号と似た言葉との違いについて、雅号と商号をそれぞれ解説します。
「雅号」は書家や美術家などのアーティスト、俳優や芸人などの芸能関係者などが名乗る名前のことです。
作品の作者名や芸能活動時に使用される要素が強く、ビジネスでの契約や税務手続きで使われるケースは稀です。たとえば、有名な役者がドラマ出演用に別名義を設定する場合などは雅号に近い使われ方です。
雅号を屋号と混同すると事務作業や契約書で混乱が生じるため、芸術活動とビジネス活動を明確に区別したいときは注意が必要です。
「商号」は、ビジネスマンが営業の際に使用する名称のことです。一般的には屋号はフリーランスや個人事業主、商号は法人に使われる認識となっています。
フリーランスや個人事業主が商号のような「○○株式会社」や「株式会社○○」で設定するのは違法となる可能性があります。そのため、フリーランスの段階では商号ではなく、屋号を用いて活動するほうが無難でしょう。

屋号は必須ではありませんが、結論として設定しておくと多くのメリットが得られます。そのため、これからフリーランスや個人事業主として活動する場合には、屋号を設定しておくのがおすすめです。
たとえば、名刺やWebサイトで屋号を掲げると、どのような分野の事業であるのかが伝わりやすく、取引先からの信用にもつながります。また、屋号で銀行口座の開設も可能であるため、事業資金とプライベートの資金をわけられます。
今後、法人化を検討している場合は、フリーランスで積み上げたブランド力をそのまま法人名へ活かしやすくなるというメリットもあります。

フリーランスが屋号を持つことで、事業の方向性を明確にしたり、信用度をアップさせたりしやすくなります。
ほかにも屋号を設定するメリットはあり、屋号を上手に活用すれば事業の成功にも繋がるため、屋号をつけるメリットを把握しておくことが大切です。
ここでは、フリーランスが屋号をつけるメリットについて、以下の5点を解説します。
フリーランスが本名を伏せたまま活動することで、プライバシーを守りながら事業展開ができます。
本名で活動してしまうと、どうしても個人情報が流出したり、SNS上でプライベートな交友関係が露見したりするリスクが高まるため、そのようなリスクを避けたい場合に、屋号によって身バレリスクを抑えられるでしょう。
また、屋号を前面に出すことで、日々の受注や問い合わせ対応などを一括管理しやすくなり、生活空間と仕事領域をきちんとわけられます。
銀行口座によっては屋号名義で口座の開設が可能です。
屋号付きの銀行口座を開設すれば、経理や請求業務で、プライベート用のお金との混同を防ぎやすくなります。また、税務申告時に公私の収支を区別しやすくなるため、確定申告や青色申告の書類作成も効率化します。
屋号口座を複数の銀行で作れば、用途ごとに資金管理を振り分けられるため、将来的にさまざまな事業をおこないたい場合に便利です。
「○○Web制作」や「○○Design」のように、屋号に業種やサービス名を盛り込んでおくと、「どのような事業をおこなっているのか」が屋号だけで理解してもらえます。打ち合わせや問い合わせの段階でも話がスムーズになり、新規顧客や取引先が安心して声をかけやすくなる利点があります。
また、SNSやブログのアカウントにも屋号が使えるため、発信内容との関連性を高めることでブランディングの向上が図れます。
確定申告や会計管理をおこなう際に、屋号を設定しておくと売上や経費を整理しやすくなります。また、個人名と混在すると経理ミスの原因になりやすいですが、郵便物や領収書の宛名を屋号に統一しておけば、事業に関する支出が見えやすくなります。
また、屋号名義での銀行口座も開設できるため、プライベート用の口座と用途を明確にわけられ、家計費と事業費を混同せずに管理することが可能です。
将来的に法人化を目指す場合、屋号を定着させておくと、そのまま社名として利用しやすい環境が整えられます。
取引先や顧客が屋号を認知していれば、法人名の変更にともなうブランディングの手間や混乱を最小限に抑えられます。また、事業拡大のタイミングで「株式会社○○」という形へスムーズに移行でき、これまで築いてきた実績や評判を引き継ぎやすくもなるでしょう。

屋号によるメリットは多い一方で、ネーミング作業に時間がかかるうえ、変更時の手間も大きいのがデメリットとして挙げられます。また、屋号が固定されることで新しいサービスや業種に進出しにくく感じるリスクがあるため、事前に注意点を理解しておく必要があります。
デメリットへの対策を講じておけば、後から「つけなければよかった」と後悔する事態を回避できるでしょう。
ここでは、フリーランスが屋号をつけた際のデメリットについて、注意点とその対策も解説します。
事業内容を的確に表現し、他社と差別化しつつ覚えやすい屋号を考えるには、相応の時間が必要です。複数案を比較検討したり、友人やビジネス仲間に意見を求めたりする過程で開業が遅れるケースもあります。
あらかじめ事業計画やターゲット顧客を明確にしておくと、屋号に盛り込む要素が定まりやすくなります。とくに、ロゴやWebサイトを作る場合、屋号を軸にデザインを進めることになるため、早期に決めておいたほうがスムーズでしょう。
一度決めた屋号を改名すると、開業届や銀行口座、WebサイトやSNS、名刺などのあらゆる部分で屋号の再登録や周知が必要です。結果的にブランディングを1からやり直すような事態に陥るリスクも否定できません。
大切な顧客や長期的に連携しているパートナー企業には念入りに案内する必要があり、改名の時期や発表タイミングにも気を遣うことになるため、早めの計画が不可欠といえます。
屋号に業種名を盛り込んでいると、別の事業領域に展開する際に「名前と事業実態が合わない」と感じられるかもしれません。屋号によって固定観念が強まるため、新規サービスや業務内容の拡大をするハードルが高まります。
そのため、屋号をつける際には、将来的な方向性を考慮して抽象度を適度に上げる選択肢もあるでしょう。将来的な事業範囲を狭めないためにも、業種を直接的に表現しすぎず、キーワード選びに余地を残す戦略も重要です。

屋号を設定するうえで大切なのは、目的・将来性・重複回避など多方面から検討することです。事業内容を簡潔に伝えられるか、覚えやすく印象に残るか、法人名と間違えられないかなど、確認しておきたい要素は幅広いです。
解説するポイントを理解し、どのような屋号にしていくかを検討していけば、失敗するリスクを最小限にできるでしょう。
ここでは、フリーランスの屋号を決める際の7つのポイントについて、解説します。
屋号に「Web制作」「デザイン」「カフェ」などのキーワードを含めると、新規顧客や取引先に伝わりやすくなります。また、「○○工房」「○○スタジオ」などの職人感をイメージさせる単語を入れるのも1つの戦略として有効です。
事業内容がわかりやすい屋号にしておけば、自分の強みや専門分野をイメージしてもらえ、結果的にクロージングまでのやりとりがスピーディーになる可能性が高められます。
事業をおこなう上で「認知度」は欠かせないポイントです。
屋号に短い単語やリズム感のある言葉を選ぶと、取引先に覚えてもらいやすいメリットがあります。また、発音しやすく、視覚的にも読みやすいと、顧客から口コミで紹介されやすくなり、新規の案件獲得にプラスに働く可能性もあります。
数名の友人や知人に口頭で説明し、どれだけスムーズに伝わるか確認したり、メモに書いてみてスペルミスをしないかチェックしたり、といったテストをおこなうとより覚えてもらいやすい屋号がつけられるかもしれません。
20文字を超える屋号は、名刺やSNSで省略されるおそれがあり、相手に全体を覚えてもらう目的であれば不適切です。長い名称を強引に使うと、WebサイトのURLも不格好になり、検索エンジンでURLが途中で切れて表示されるケースもあります。
そのため、屋号をつける際には、10文字前後を目安にし、略称を決めておくと業務やコミュニケーションがスムーズに図れるでしょう。
なお、特殊記号を多用するとSNSアカウントやメールアドレスで使えない場合があるため、シンプルさを重視するほうが無難です。
ポイント4.他社との重複を避ける
既に商標登録されている名称や、同業他社が有名ブランドとして確立している屋号を使用してしまうと、最悪の場合には法的トラブルに発展するリスクがあります。また、同じような名称が複数存在すると、Web検索やSNS検索で競合に埋もれてしまう懸念もあります。
インターネットや特許情報のプラットフォームで事前に確認しておき、設定したい屋号が被っていないか確認することが重要です。
出典:不正競争防止法 | e-Gov法令検索,商標法 | e-Gov法令検索
ポイント5.法人のような屋号にしない
「○○株式会社」「○○銀行」など、法人名を想起させる表現をフリーランスや個人事業主が用いるのは法律上の問題になる場合があります。また、顧客や取引先から「詐称ではないか」と疑いを持たれる危険性もあるため、避けておくのが無難といえます。
もし、将来的に法人化を予定している場合には、混乱なく屋号から商号へ移行できる名称を早期に検討しておくと、不必要な改名を回避できて便利です。
Webでの集客や情報発信をおこなう場合、屋号と同じドメインを取得できるか調べておくとブランド価値を統一しやすくなります。すでに使われている場合は単語を変えるか別の表記を検討する必要があるでしょう。
屋号に合うURLを確保できれば、オンライン上でのブランディングが格段に高まりやすくなります。
同業種でありがちな単語ばかり並べて屋号をつけると、競合に埋もれやすく、検索エンジンやSNS上でもほかと区別されにくくなる弊害があります。
屋号には自分だけの強みやストーリーを織り込むと、屋号そのものが魅力的なブランド要素になるため、オリジナリティを意識して決めることが大切です。たとえば、「自然素材を扱う工房なら、植物や動物にちなんだ名前を付ける」や「伝統文化を取り入れたいなら、地域の歴史や神社に由来するキーワードを活かす」といったアプローチも方法の1つです。
ユーザーが屋号を聞いただけで世界観をイメージできると、興味を持ってもらいやすくなり、他社との明確な差別化につながります。

業種や職種、自社の強みを踏まえて屋号をつけると、取引先からの認知度が高まったり、屋号だけで事業内容をイメージしてもらえたり、とさまざまなメリットが期待できます。ただ、ありきたりな名称にしてしまうと、競合に埋もれてしまうリスクもあります。
そのため、同業種の事業をおこなう競合がどのような屋号をつけているのかを調べておくと良いでしょう。
ここでは、フリーランスの屋号のネーミング例について、紹介します。
フリーランスエンジニアが屋号をつける場合、「○○Lab」「○○Tech」「○○Works」などのITや先端技術を連想させる単語を掛け合わせるのが一般的です。
近年では、AIやクラウドも注目されつつあるため、もし事業にその分野が含まれているならば「AI」「Cloud」などを含めると事業内容のアピールにもなるでしょう。
店舗事業の場合、「○○屋」「○○堂」「○○カフェ」などの親しみやすさを前面に出したネーミングが多い印象です。
屋号をつける際に、地域名を入れるとご当地感を打ち出せ、地元住民や観光客にアプローチしやすくなります。また、雑貨やスイーツなどの販売店なら扱う商品名を一部に盛り込むと、初めて利用する顧客から「どのようなお店か」が伝わりやすくなります。
「○○クリニック」「○○サロン」など、医療・美容系の専門性がわかる屋号を使うと、屋号を見たユーザーが安心しやすくなります。また、オーナーの名前を屋号につければ、責任者が明確になり、信頼感を抱きやすくなります。
歯科や内科、エステなどの分野がはっきりしている場合は、それを屋号に盛り込むと予約や問い合わせがスムーズになるでしょう。
「○○法律事務所」「○○税理士事務所」のように、業務内容がはっきりわかる屋号を使うほうが顧客の信用が得られやすくなります。事業内容も踏まえて、ユニークな名称にするよりも、堅実かつ権威を感じさせる表記が採用されることが多い傾向にあります。
士業は実績や資格が重視されるため、屋号で奇抜さを狙うよりも信頼と安定感を優先したほうが得策でしょう。

屋号によって事業の成功に結び付けたい場合には、大企業の成功事例に注目すると良いでしょう。
一般的に親しまれている企業やサービスは、その名称の覚えやすさやリズム感などの要素がバランスよく取り入れられていることがわかるでしょう。また、見た目のビジュアル要素も意識されている傾向にあります。
ここでは、成功している屋号の付け方について、以下の3点を解説します。
屋号をつける際に、発音や韻がキャッチーなものを織り交ぜると、口頭で紹介する際に取引先が屋号を覚えやすくなります。カタカナ表記やアルファベットを組み合わせるとポップになり、SNSでのハッシュタグとも親和性が高まるでしょう。
事業のロゴや名刺でビジュアル要素も合わせるとブランド力が増し、利用者からの口コミが広まりやすくなる利点もあります。
漢字やカタカナの画数を調べて、縁起を担ぐ形に整えるアプローチも根強い人気があります。日本では画数占いが人気であり、一部のユーザーは会社名や商品名を画数から選んでいることもあるため、馴染みのある決め方といえます。
仮に、運気や占いを重視していない方であっても、「画数が良い名前」という話題性が話のタネになり、取引先とのコミュニケーションが弾む可能性もあるでしょう。
伝統工芸や飲食店など特定の業界では、昔から引き継がれる縁起物や慣習を屋号に取り入れるケースがあります。特定の数字や神様の名前、地域に伝わる吉兆の言葉などを組み込むと、地元や業界の人にとって親近感を抱きやすくなります。
また、屋号にストーリー性を持たせていれば、由来を尋ねられた際に「このお店には、こんなストーリーがあるんだ」という興味を引き出し、店舗体験や商品の価値を高めるきっかけになることも少なくありません。

本記事では、フリーランスに屋号は必要なのかについて、メリットや決め方、事業で成功するための秘訣を解説しました。
屋号が決まると、名刺やWebサイトのデザインを統一しやすくなり、ブランディングの軸が明確になります。また、SNSのプロフィールやメール署名にも屋号を取り入れ、ロゴやカラーなど視覚的な要素をそろえると、事業の認知度を高めやすくもなるでしょう。
屋号をしっかり育てることで事業の信頼度と発展性が高まり、本名や個人情報を出さずに活動したい方にとっても有効な手段です。長期的な視点でネーミングを考え、自分が誇りを持てる屋号をつけ、より事業を拡大していきましょう。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く