40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
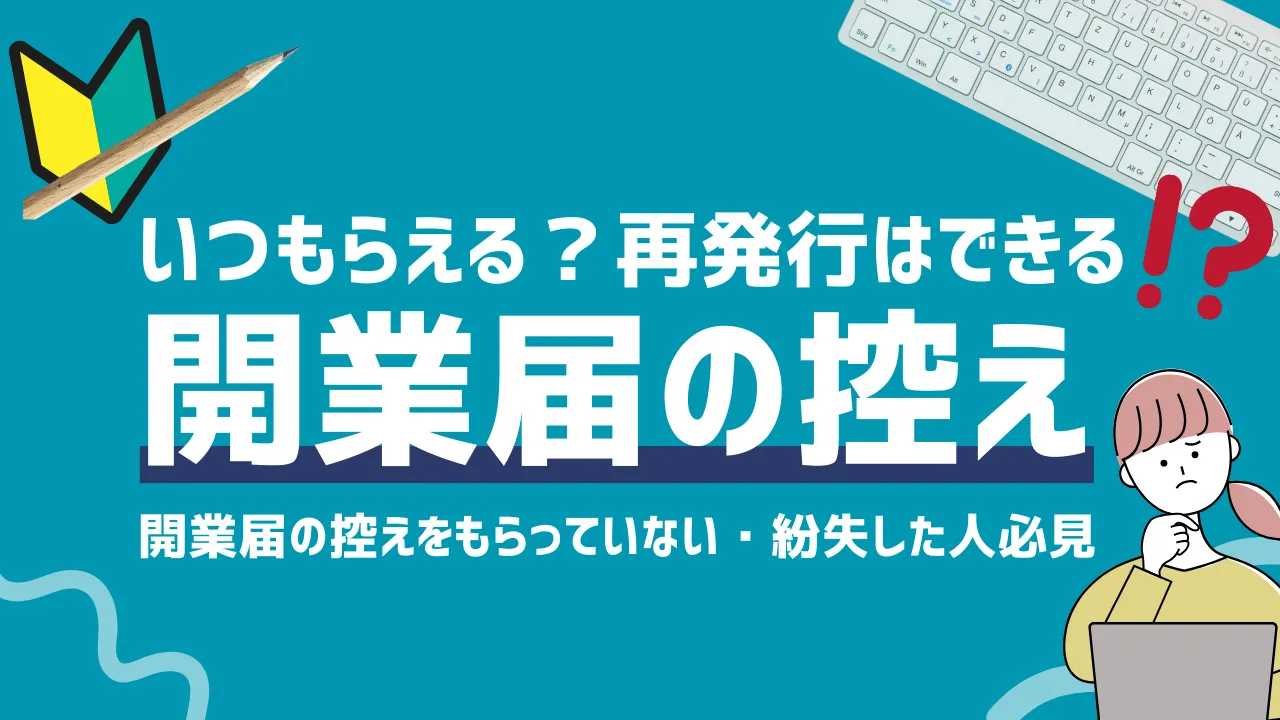
開業届の控えは、開業届を提出する時に「控え用のコピー」または「もう一部作成したもの」を添付すれば、税務署で受領印を押して返送してくれます。今回は、「開業届の控えはいつもらえるの?」「紛失した場合は再発行できる?」という疑問を抱える人に向けて、開業届の控えをもらえるタイミングやその方法、再発行方法について解説します。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
「開業届の控えを受け取った覚えがない。みんなはいつもらったの?」
「紛失してしまった場合は再発行できるのかな?」
という人も多いのではないでしょうか。
個人事業主として事業を営んでいることの証明となる「開業届の控え」は、開業届を提出する際にもらえます。しかし、控え用のコピーを添付する必要があったり、e-Taxの場合は控えをもらえなかったり、といった申請方法によって異なるので注意が必要です。
この記事では、開業届の控えがもらえるタイミングやもらう方法、紛失時の再発行方法について解説します。あわせて、開業届の控えが必要になる場面や、開業届の控えを確認する方法もまとめました。
この記事を読むと、開業届の控えに関する疑問や不安を払しょくできるでしょう。

株式会社や合同会社など会社を設立した場合、法務局で登記事項証明書を取得すれば証明できます。それに対して、個人事業主は、登記されるわけではないので、証明書がありません。
個人で事業を営んでいることを証明する際には、税務署からの受領印がある「開業届の控え」が個人事業主の証明書代わりに使われるのです。
開業届とは、自身が個人事業主として開業した事実を税務署へ知らせるための書類です。正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
開業届は事業を開始してから1ヶ月以内の提出が推奨されてはいますが、提出しないことによる法律的な罰則はありません。つまり、会社員を辞めて開業したからといって、必ずしも税務署へ開業届を出さなくても特に問題が起きることはないでしょう。
開業届の届け出をしていても、していなくても、フリーランスや個人事業主として得た収入に対する納税の義務があることに変わりはありません。開業届を出してないから納税の義務がない、などという都合のよいことはないということです。収入を得るのであれば、必ず確定申告を行う必要があります。
開業届は、確定申告を行う時に提出有無が関わってきます。会社員のときは確定申告のような手続きは会社側で行ってくれましたが、個人で事業を営む個人事業主であれば、そうはいきません。個人のやるべきことに含まれてきます。
▼この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます。
個人事業主の開業届とは?開業時にやることリスト付き!開業後に必要な準備や手続きも紹介

開業届の控えをもらえる方法や、タイミングは「開業届の提出方法」によって異なります。
開業届の提出方法には、「税務署へ直接提出する方法」のほか、「郵送」や「eTaxを利用してネット上で提出する方法」もあります。下記に開業届の提出方法ごとに、控えを受け取る方法やタイミングについてまとめたのでチェックしてみてください。
| 開業届の提出方法 | 受け取る方法 | 受け取るタイミング |
| 管轄の税務署へ直接提出 | 税務署の窓口で控え用のコピー、あるいは、もう一部追加で作成したものを添えて提出 ※当日その場で受け取れる | 開業届を提出した日 |
| 郵送で提出 | 開業届郵送時に控え用のコピー、あるいは、もう一部追加で作成したものと、返信用封筒を同封 ※1週間後に返送される | 開業届を提出した日からおよそ1週間後に返送される |
| e-Taxを使用して提出 | 開業届の控えはない e-Taxシステムから受信したメッセージが代用になる ※開業届の受付通知をダウンロード、または、印刷できる | 控えは発行されない 開業届がe-Taxシステムへ受理された日に受信通知が届くので、これが控えの代わりになる |
※ e-Taxとは、国税庁が運営する国税に関わる申告・申請・納税手続きを電子的に行えるオンラインサービスのことです。
開業届を管轄の税務署へ直接提出した場合は、控えを当日もらうことができます。
税務署の窓口で控え用のコピー、あるいは、もう一部追加で作成したものを添えて提出すれば、その場ですぐに受領印が押され、受け取ることが可能です。
ただし、不備があれば、控え用の開業届もあわせて修正する必要があるので、内容に相違がないようしっかりと確認したうえで記載しましょう。
開業届を郵送で提出する際に、控え用のコピーまたはもう一部追加で作成した開業届を添付すれば、税務署で受領印を押して返送してくれます。郵送の場合は、控えと一緒に返信用封筒を同封しておく必要があります。
開業届を提出した日から1週間ほど経った頃に自宅や事務所に到着します。郵送する際に、「開業届の控え」と「返送用封筒」を同封し忘れた場合は、控えが返送されないので注意が必要です。
開業届の控えは、紛失してしまう人も多いので、確定申告と一緒に保存しておくと良いでしょう。確定申告用のファイルを作成し、ひとまとめにして保管している人も多いです。
控えをもらった時にスキャナで読み込みをしてPDF化し、保存するのも1つの手です。デジタルで保存しておけば、無くしてしまった時にすぐにプリントアウトできるので安心できるでしょう。
e-Taxを利用して開業届を提出した場合は、控えが発行されません。
e-Taxを利用して開業届を提出した人が開業の事実を証明したい場合は、e-Taxシステムから受信した受付通知を印刷する方法と、電子申請等証明書を使用する方法の2通りあります。
書面で開業届の控えの提出を求められた際には、e-Taxシステムから受信した受信通知を印刷したものを提出すると良いでしょう。一方で、デジタル書類を求められた際には、電子申請等証明書を電子書類(xmlファイル形式)として送信します。
ただし、e-Taxシステムのメッセージボックスに届くメッセージは一定期間を経過すると削除されるので、印刷(プリントアウト)するか、PDF化してパソコンやスマートフォンに保存しておくと安心です。
e-Taxシステムから受信したメッセージの確認〜開業届のダウンロード方法まで画像付きで解説します。
(※2024年6月時点)





お知らせ・受信通知の一覧が表示されるので、開業届の通知を選択します。開業届のメッセージに「受信データ(XML)」と表示されるため、「ダウンロード(XML形式)」のボタンをタップしてダウンロードをしましょう。
「開業届の控えをもらい損ねた」「なくしてしまった」という方もいるでしょう。開業届の控えはさまざまなシーンで提出を求められるため、事業を営むうえで支障をきたす可能性があります。
ここでは、開業届の控えが必要な場合について具体的に解説します。この章を見て自身の事業に必要だと感じた方は、開業届の控えの再発行を検討しましょう。
開業届を税務署へ出したことがない方は、必ず控えをもらうために「控え用のコピー」または「開業届を2部」用意して、一緒に提出してください。
屋号で銀行口座を作る際に、金融機関から「開業届の控え」の提出を求められることがあります。
フリーランスに限らず、多くの人が銀行口座を個人で持っているでしょう。しかし、個人事業主で屋号を持っている人は屋号での銀行口座を開設できます。その屋号付き口座を開設する際に開業届が必要です。では、屋号付き口座が無いと何が不便なのでしょうか。それは確定申告と関係してきます。
確定申告では、事業での収入や経費のみを申告する必要があります。
通帳を個人用かつ仕事用としても使っていると、確定申告のときに1つ1つ個人で使ったものなのか、仕事で使ったものかを分ける必要があります。確定申告の時期である1, 2月くらいに1年前の通帳を見て、何の支払いだったかわからないこともよくあります。
確定申告をした経験のあるかたであれば共感するのではないでしょうか。1つ1つの収支を後から振り返ると正確に覚えていないこともあります。
プライベートの通帳と事業用の通帳を分けることで、どれが仕事用のものかがすぐにわかるので、確定申告の手間が格段に省けます。
事業用のクレジットカードを作る時にも、銀行口座開設時と同様に、開業届の控えの提出、あるいは提示が求められる傾向にあります。
クレジットカードといえば、普段使っている個人名義のクレジットカードを思い浮かべる方が多いでしょうが、実は法人用のクレジットカードがあります。
出費がかさみやすい開業初期費用の工面においても法人用クレジットカードは便利です。高額なものを購入しても、後払いが可能なため、開業時にお金が少なくても購入が可能です。
毎月安定した給料をもらえる正社員とは違い、個人事業主はクレジットカードの審査が通りにくい傾向があります。個人事業主としてクレジットカードの申し込みをする際、事業を行っている証明として、開業届の控えを求められることがあります。
そのため、開業届を出してないと、クレジットカードを作れない場合もあるのです。
▼この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます。
フリーランスにおすすめのクレジットカードを紹介|使い分けのメリット等も解説
個人事業主・経営者が事業を廃止するときに、それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取れる制度が「小規模企業共済」です。会社員で言うところの退職金のようなものです。
6カ月以上お金を積み立てることによって、廃業した場合に共済金を受け取ることができ、退職金代わりにすることができます。また、12カ月以上積み立てると、解約手当金を受け取ることもできます。
小規模企業共済に加盟する際には「開業届の控え」の提出が必要なため、加盟したいのであれば開業届を提出し、控えを受け取りましょう。

開業届の控えをもらってない場合は、税務署の申告書閲覧サービスを利用して、自分が提出した開業届を無料で確認できます。ただし、書類を提出した税務署でのみ可能です。
コピーはもらえませんが、紙に書き写したり、その場で確認できる写真であれば撮影が許可されていたりします。
税務署で閲覧申請をする際には、運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類が必要です。確認するためには本人確認が必要になってくるため、忘れずに持っていきましょう。
 開業届の控えをもらってない、または紛失してしまった場合、次の2通りの方法で控えを受け取れます。1つは税務署で再発行してもらう方法、2つめは、開業届を再提出する方法です。
開業届の控えをもらってない、または紛失してしまった場合、次の2通りの方法で控えを受け取れます。1つは税務署で再発行してもらう方法、2つめは、開業届を再提出する方法です。
ご興味がある方は、参考にしてください。
開業届の控えを再発行してもらう場合、税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出します。開示請求によって開業届のコピーがもらえるため、コピーにある受領印をもって控えとできます。
開示請求に必要なものは以下の3つとなっています。手続きをする前にしっかりと確認しておきましょう。
出典:開示請求等の手続|国税庁ホームページ
参照:https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm
ここでは、保有個人情報開示請求書の記入方法を紹介していきます。
「開示を請求する保有個人情報」の欄に「開業届」と記入し、「求める開示の実施方法等」には、「写しの交付」または「写しの送付を希望する」を選択します。
再発行までの期間はどれくらいかかるのでしょうか。窓口でも郵送でも、手続きから控えの受け取りまで、およそ2週間から1カ月かかります。
郵送でも請求することが可能となっているため、覚えておきましょう。
 ここでは、開業届を再提出して控えをもらう方法を紹介していきます。控えの再発行には時間がかかってしまいますが、再提出すればすぐに控えを受け取れます。ご興味がある方は、参考にしてみてください。
ここでは、開業届を再提出して控えをもらう方法を紹介していきます。控えの再発行には時間がかかってしまいますが、再提出すればすぐに控えを受け取れます。ご興味がある方は、参考にしてみてください。
開業届を再提出すれば、控えがすぐに手に入るメリットがあります。税務署の窓口で書類申請すれば、即日で控えが受け取れます。さらに開業届の提出は無料なため、再発行のように手数料がかかることはありません。
再提出した場合、受付日が再提出日になるため、実際の開業日と受付印の日付に乖離が起き、違和感が生じます。税務署から問い合わせを受けたり、受付日によって判断される制度は利用できない可能性も出てきたりするため、注意しましょう。
開業届は、同じ内容で再提出しても問題ありません。控えをもらってない場合や紛失の場合だけでなく、開業日を変更したいときにも再提出することもあるため、覚えておきましょう。
 まず、出さなくても問題ない人について説明します。
まず、出さなくても問題ない人について説明します。
それは継続した事業を行っていない人の場合です。
例えば、ネットオ―クションやメルカリなどで所持している不用品を売って収入を得る場合などです。
こういった不用品の販売で収益を得ることは継続的に事業として行うわけではないので、開業届を出す必要はありません。
継続的に収益を得るような事業を行っている人、またこれまでの章で述べてきたような開業届を出すことのデメリットを回避したいかたは開業届を出す必要があります。
つまり、法人用のクレジットカードを使いたい、補助金・助成金を申請したい、青色申告で確定申告をしたいというかたです。
 国税庁のwebサイトによると、フリーランスが開業届を出すのは「事業開始の事実があった日から1か月以内」と記載されています。
国税庁のwebサイトによると、フリーランスが開業届を出すのは「事業開始の事実があった日から1か月以内」と記載されています。
提出期限が土日・祝日に該当する場合は、その翌日が期限となっています。自宅近くに税務署があれば、直接、税務署の窓口へ行って開業届の書類をもらい、記入して提出するのがよいでしょう。
原則、事業開始から1か月以内ではありますが、開業届の提出がそれをこえたとしても罰則があるわけではないのでその点は安心してください。
ただ、1点注意すべきことがあります。それは、青色申告を予定しているかたの場合です。開業した年度から青色申告で確定申告を行いたい場合、開業してから2か月以内に「青色申告承認申告書」を提出する必要があります。これに遅れてしまうと、開業した年度は、青色申告ができず、白色申告をすることになるので注意しましょう。開業届を出すタイミングで、同時に青色申告認証申告書も提出することをオススメします。
 開業届はまず書類を入手して、それに記入して提出する、シンプルにそれだけです。
開業届はまず書類を入手して、それに記入して提出する、シンプルにそれだけです。
まずは開業届を入手します。開業届を入手するには、国税庁のダウンロードサイトからPDFファイルをダウンロードして印刷します。
開業届の書類には多くの入力項目があります。その中でも必ず記入しなければならない項目が以下です。
提出先の税務署と提出日の年月日を記入します。
自宅や事務所の住所を納税地として記入します。
自身の情報を記入します。個人番号はマイナンバーのことです。カードが手元にない場合は、住民票のコピーを取得するときに記載してもらうことができます。
新しくフリーランスとして開業する場合は開業に〇をして、他の欄は空欄とします。
不動産から所得を得る場合は不動産所得、山林による所得は山林所得です。その他は事業所得です。多くの方は事業所得が該当するでしょう。
フリーランスとして開業した日付を記入します。
新規での開業の場合は記入不要です。
青色申告承認申請書や課税事業者選択届出書も提出する場合は「有」をチェックします。
事業内容を記入します。
従業員を雇用する場合の記入項目です。フリーランスであれば、従業員を雇用する人は少ないでしょう。もしいる場合は記入します。
従業員がいる場合に該当します。そうでない場合は「無」をチェックしましょう。
⑫給与支払を開始する年月日
従業員への給与の支払いを開始する年月日を記入します。
顧問税理士がいる場合は、氏名・電話番号を記入します。
必要事項の記載が終わったら、記入した開業届を印刷してください。自宅にプリンターがない場合には、USBメモリなどにデータを入れて、コンビニエンスストアで印刷しましょう。
開業届の記載が完了し印刷が終わったら、書類を税務署へ提出しにいきましょう。提出する場所は、開業届の「所轄の税務署名を記入する」の欄に記入した税務署です。控えにも必ず受付印をもらうのを忘れずにしましょう。控えに税務署の受付印がない場合、補助金の申請などのとき、開業届の証明として使えなくなってしまいます。
参考:書き方
▼この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます。
freee開業で開業届を簡単に作成してみよう!使い方についても紹介
 開業届の控えは、届け出の提出方法によってもらえるタイミングが異なります。
開業届の控えは、届け出の提出方法によってもらえるタイミングが異なります。
税務署へ直接提出した場合は即日、郵送で提出した場合は、約1週間後に返送されてきます。
控えをもらうためには、控え用のコピーを一部添えて開業届を提出してください。そうすると、コピーに受領印が押され、控えとして受け取れます。
郵送の場合は、返信用封筒を同封すると返送してもらえるので忘れずに同封しましょう。控えをもらってないとあわてることのないように、控えは必ずもらうようにしてください。
 国税庁のオンラインサービスであるe-Taxを利用して開業届を提出した場合、控えは発行されません。
国税庁のオンラインサービスであるe-Taxを利用して開業届を提出した場合、控えは発行されません。
ただし、メッセージボックスに受信通知が届くため、送信した開業届の電子データと受信通知をプリントアウトして保管すれば、控えとして利用できます。
 開業届の控えに関して、もらい方や、受け取るタイミング、なくした場合の再発行方法などさまざまな疑問が浮かぶ人も多いでしょう。フリーランスや個人事業主には、会社員の時のような上司・先輩が存在しないため、気軽に相談できません。
開業届の控えに関して、もらい方や、受け取るタイミング、なくした場合の再発行方法などさまざまな疑問が浮かぶ人も多いでしょう。フリーランスや個人事業主には、会社員の時のような上司・先輩が存在しないため、気軽に相談できません。
ここでは開業届の控えに関する疑問や不安を払拭するために、よくある質問に対してQ&A形式でお答えします。
「開業freee」で作成した開業届を2部ダウンロードすれば、一部を控え用として保管できます。
提出方法を選択する際に「スマホで電子申告」を選んだ場合は、e-Taxシステムに届く「受付通知」を開業届の控えとして使用することが可能です。
開業届の控えは、個人事業主が事業を営んでいることの証明になるため、あらゆるシーンで必要になります。
例えば、個人事業主の事業用ビジネスカードを開設する時や、屋号付きの銀行口座を作る時、融資を受ける時などに開業届の控えを求められることがあります。
開業届の控えがなければ、事業を継続するうえで支障をきたす可能性があるので、はやめに用意しましょう。開業届の控えを紛失してしまった、あるいは、もらっていない方は再発行の手続きを行って、受け取る必要があります。
開業届の控えは、コピーでも問題ありません。しかし、税務署の受領印が確認できるものでなければならないので、開業届を出す際に2部提出して両方に受領印を押してもらいましょう。
開業届をネットで提出した場合は、控えをもらうことができません。
ただし、e-Taxシステムにログインして、受信通知から開業届の受付メッセージをダウンロードや印刷すると、書面の控えと同様のものとして使うことができます。
開業届の控えを再発行する方法を知っておこう
開業届の控えは、個人事業主として事業を営んでいることを証明する重要な書類の1つです。
「屋号で銀行口座を作る場合」や「事業用のクレジットカードを作る場合」「融資を受ける場合」「キャッシュレス決済を導入する場合」などさまざまな場面で、開業届の控えの提出を求められます。開業届の控えをもらったら、紛失しないように大切に保管しましょう。
なお、開業届の控えは、税務署へ開業届を出す時に「控え用のコピー、あるいは、もう一部用意」して、一緒に提出しなければもらえません。郵送の場合は、返送用封筒も同封しなければ、開業届の控えを受け取れないので注意しましょう。
e-Taxで提出した場合は、開業届の控えは発行されないものの、e-Taxシステムにログインして、受付通知を印刷または、ダウンロードすることで代用可能です。
開業届を税務署に提出する前に、控えについて知らなかった方は、再発行する方法をチェックし、開業届の控えを受け取りましょう。
▼この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く