40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
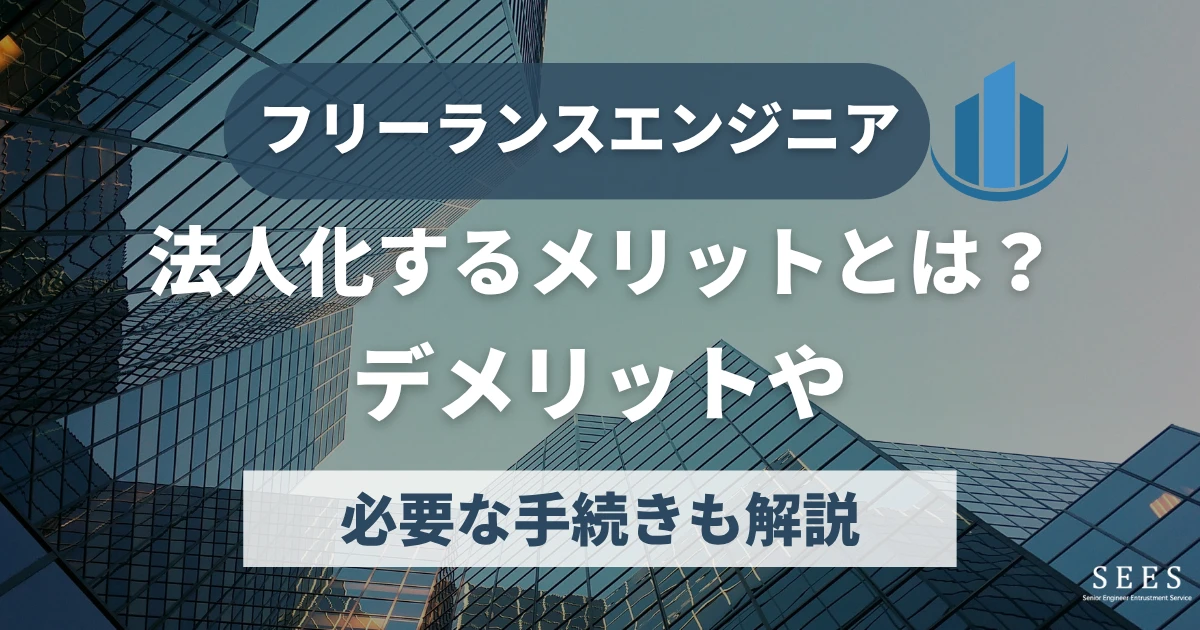
フリーランスエンジニアは、法人化することで個人事業主よりも経費の幅が広がったり、社会保険に加入できたりとメリットが数多くあります。一方で、デメリットも存在するため注意が必要です。本記事では、フリーランスエンジニアが法人化するメリットについて、デメリットや必要な手続きも交えて解説します。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
フリーランスエンジニアとして働いていると、節税や社会的信用の獲得を目的に「法人化すべきかどうか」を検討する機会が増えていきます。とくに、売上や所得が一定水準を超えてきた場合や、今後の事業拡大を視野に入れている場合は、法人化が前向きな選択肢になる方も多いでしょう。
ただ、法人化には手続きや費用、運営上の負担もあるため、タイミングを誤るとデメリットがメリットを上回る可能性も否定できません。
法人化する際は、タイミングが適切なのか、メリットを活かせるのかを考え、適切な手順で手続きを進めることが大切です。
本記事では、フリーランスエンジニアが法人化するメリットについて、デメリットや必要な手続きも交えて解説します。

法人化とは、個人事業主として活動している方が、会社を設立して、法人の名義で事業をおこなうことを意味します。
このように、法人化したからといって、働き方のスタイルやサービスの提供内容が変更されるわけではありません。あくまで、事業の「形式」を個人から法人へ移行するというイメージです。
フリーランスが法人化することによって、社会的な信頼性が高まり、取引先の対応が変化する可能性があります。一方で、設立・運営にはコストや手続きが発生するため、タイミングや目的を明確にしたうえで判断することが重要です。

フリーランスが法人化する際に、一般的には「合同会社」と「株式会社」の形態 が選ばれます。ほかにも、合資会社や合名会社がありますが、それらは一人では新設できません。
「合同会社」と「株式会社」は、それぞれ設立にかかる費用や社会的な信用、運営の柔軟性などに違いがあります。
どちらの会社形態を選ぶかによって、今後の事業運営に大きく影響するため、それぞれの特徴を比較することが大切です。
選択を誤ると、不要なコストが発生する以外にも運営上の制約を抱える可能性もあるため、事前に比較検討し、自身のビジネススタイルに合った形態を見極めましょう。
ここでは、法人化するための会社形態を解説します。
合同会社とは、出資者と経営者が同一人物になる会社形態です。株主総会や取締役会といった形式的な制度が不要で、出資者がそのまま経営に関与するため、意思決定が速く、スピード感をもって事業を進められます。
株式会社に比べると設立費用が安く、運営面でも柔軟性が高いため、フリーランスや少人数経営者に人気があります。
ただし、社会的信用の面では株式会社に劣るとされる場面もあり、企業間取引や資金調達では不利になるケースも否定できません。
株式会社は、株式を発行することで出資者と経営者を分離できる社会的な信用が高い会社形態です。第三者からの出資や将来的な上場、外部人材の採用にも対応しやすいため、事業拡大を見据えた経営に向いています。
ただし、合同会社に比べると設立費用は高めで、株主総会や決算公告などの義務も多くなります。設立時の手続きも複雑なため、税理士や司法書士など専門家のサポートが必要になる場面もあるでしょう。

フリーランスが法人化することによって、経費の範囲が変更され、自身の給料を役員報酬にできるなど、多くのメリットを得られます。とくに、将来的に事業規模の拡大を考えていたり、継続的に高い売上を維持していたりする場合は、法人化によって事業が成長する機会につながる場合も多いです。
メリットを理解したうえで、自身が今後事業をどのように拡大させていきたいかを基準に、法人化するかを検討しましょう。
ここでは、フリーランスが法人化することのメリットを解説します。
法人では、個人事業主では認められなかった支出も節税対象となる場合があり、資金をより効率的に活用できます。
たとえば、個人事業主の場合は、自宅を事業で使用していないのであれば、家賃の一部を経費にできません。一方、法人化して物件の名義を法人にすることで、自宅が社宅の扱いになり、事業に使用していなくても経費の計上が可能になります。
このように、法人化は個人事業主のときよりも経費の幅が広がり、課税所得を圧縮できるため、納税時の負担を軽減することが可能です。
フリーランスが法人化することで、自身の収入を「役員報酬」として設定することが可能になります。これにより、自身の収入も給与所得として扱われるため、所得分散による節税効果や、社会保険料の計算における調整がおこないやすくなります。
ただし、経費にできるのは下記の3つです。いずれかに該当しない場合は、経費として扱われません。
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同じ日に、同じ金額の役員報酬を支払う方法 | 毎月の給与 |
| 事前確定届出給与 | あらかじめ税務署に提出したスケジュール・金額通りに支払う給与 | ボーナス |
| 業績連動給与 | 会社の業績に応じて変動する役員報酬 | インセンティブ |
法人から受け取る役員報酬は、個人側で給与所得控除が適用されます。給与所得控除を活用することで、年収が一定額を超える場合でも、所得税率の急増を抑えられます。
この制度により、課税対象となる所得を大幅に圧縮でき、実質的な所得税の負担軽減が可能です。個人事業主の収入は給与ではないため、この制度は適用されず、法人化することで得られるメリットです。
個人事業主は収入が増えるほど税金の負担が増えるため、制度を活用することで節税につながります。
法人化した場合、たとえ従業員が自分一人でも、健康保険組合や厚生年金などの社会保険への加入が義務づけられます。国民健康保険や国民年金と比較して保険料の負担は増えるものの、保障の内容が充実しており、傷病手当金や出産手当金などの制度も利用が可能です。
厚生年金に加入することで、将来的な年金の受給額が増加し、フリーランスが持つ老後の不安も軽減できます。
雇用保険や労災保険などの制度も利用できるため、万が一のときにも収入がゼロになるリスクを抑えられるでしょう。
個人事業主の会計期間は、1月1日〜12月31日までと定められています。そのため、確定申告は定められた3月までにおこなわなければなりません。
一方の法人の場合は、会社の決算月を自由に設定することが可能です。
これにより、自社の繁忙期を避けて決算月を設定でき、余裕を持ったタイミングで決算処理をおこなえます。税務署への申告や納税のタイミングもある程度自分でコントロールできるため、資金繰りの安定化にもつながるでしょう。
法人企業は、法務局に登記された実体として公的に認められており、個人事業主と比べて対外的な信用度が格段に高まります。
個人事業主に比べて、法人格を有することで、事業所の契約や融資の申し込みなど、あらゆるビジネスシーンで申請が通りやすくなります。
企業からの見え方や評価も変わるため、大手企業や官公庁との取引を目指す場合、法人格が必須条件となることも少なくありません。
有限責任とは、会社が倒産した場合に、出資者は出資した金額を上限として責任を負い、それ以上の責任は負わないという制度です。
法人はこの「有限責任」で運営されるため、事業で損失や借金が発生した場合でも、原則として代表者の個人資産までは責任がおよびません。
個人事業主であれば、すべての債務が自己責任となるため、場合によっては家財の差し押さえや個人の借金につながる可能性があります。

フリーランスエンジニアが法人化することで得られるメリットは大きいものですが、同時に無視できないデメリットも存在します。
とくに、費用面の増加や制度の複雑化などがネックとなり、かえって運営上の負担が増すケースも少なくありません。
法人化は、目的と実情に合わなければ逆効果となる可能性もあるため、慎重に検討する必要があります。
ここでは、フリーランスエンジニアが法人化することのデメリットを解説します。
フリーランスが法人を設立すると、代表者1人の会社であっても健康保険組合や厚生年金などの社会保険への加入が義務づけられます。保険料は国民健康保険よりも割高になるケースが多く、年間で数十万円単位の支出が発生することもめずらしくありません。
事業を始めたばかりで売上が安定しない場合や、役員報酬を多く設定した場合には、社会保険料の負担が重くのしかかるため、慎重に試算したうえでの報酬の設定が必要です。
法人を設立するためには、定款の作成や公証役場での認証、法務局への登記申請などの手続きが必要です。設立には初期費用もかかり、合同会社でも6万円以上、株式会社であれば15万円前後が発生します。
加えて、慣れない手続きに不安がある場合は司法書士や税理士への依頼を検討する方もいるでしょう。司法書士や税理士に依頼することで、その分コストが上乗せされます。
法人化の際はコスト面や手続きの煩雑さを理解しておかなければ、実際に準備を始めてから後悔するかもしれません。
法人を設立する際には、登記上の「本店所在地」を指定する必要があります。
自宅での登記が可能な場合もありますが、賃貸物件によっては「法人登記不可」とされているケースがあり、別に事務所やバーチャルオフィスを用意しなければなりません。
事務所を用意することで賃料や通信インフラの整備などが必要になり、追加コストとしてかかります。その結果、個人事業主のときよりも固定費が増えてしまい、負担になる可能性があります。
法人は、たとえ赤字決算であっても、「法人住民税」として最低7万円程度の税金を毎年納める必要があります。そのため、利益が出ていない場合でも一定額の納税義務は避けられません。
とくに設立初年度や売上が不安定な時期においては、必ず支払う税金が負担となるケースも多くあります。
資金に余裕がない場合には、無理に法人化を急がず、タイミングを慎重に見極めることが大切です。
法人では、役員報酬は事業年度の開始時に設定し、その後は原則として1年間変更ができません。自由に報酬額を変更した場合、経費として認められない可能性があるため、納税時のリスクが生じます。
そのため、法人化後に売上の低下が発生しても、事前に設定した役員報酬を支払わなければなりません。
報酬額を決める際は、経費としての効率を踏まえたうえで、余裕を持った金額設定をおこないましょう。

法人化には多くのメリットがある一方で、タイミングや事業規模によってはコスト面での負担が重くなるケースもあります。
そのため、法人化するか悩んだ際は「売上」や「所得」、「人材の雇用予定」などを判断基準として検討することが重要です。
以上の3つを踏まえて、フリーランスが法人化するか悩んだときの判断基準を解説します。
フリーランスエンジニアの年間売上が1,000万円を超えると、2年後から消費税の納税義務が発生します。
個人事業主の場合は、そのまま消費税を支払う必要がありますが、法人化することで設立から2年間は条件を満たすことで消費税が免除される制度を利用できます。
法人の消費税が免除される条件は以下のとおりです。ただし、インボイス制度に登録する場合は、下記の条件を満たしても消費税の納付義務があるため注意しましょう。
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 設立時 | 基準期間がない |
| 資本金が1,000万円以下(※1) | |
| 設立後 | 設立1年目の前期半年で売上が1,000万円を超えていない |
| 特定期間における課税売上高または給与等支払額が1,000万円以下(※2) |
(※1)参考:国税庁「納税義務の免除」
(※2)参考:国税庁「特定期間の課税売上高による免税事業者の判定」
課税所得が330万円を超えると、所得税率が20%に引き上がります。あわせて、住民税10%と個人事業税も課税されます。そのため、個人事業主の場合は課税所得が330万円を超えたタイミングで、税金の負担が30%を超えてしまうでしょう。
一方で法人化することで、法人税や法人住民税などを合わせた実質税率が、400万円以下の課税所得で「約23%」、400~800万円以下であっても「約25%」となります。
このように、課税所得が330万円を超えるのであれば、法人化する方が納税時の負担を軽減できます。
フリーランスとして事業を拡大し、将来的に従業員の雇用や業務委託の依頼をする予定がある場合、法人化することで社会保険や労務管理体制を整備しやすくなります。
採用活動でも、「法人であるかどうか」は応募者からの大きな信頼要素の1つです。法人化しておらず、社会保険の加入ができないのであれば、応募を諦めてしまう優秀な人材がいるかもしれません。
法人であれば福利厚生の制度設計も自由度が高く、採用力を高める一環として有効に働くでしょう。
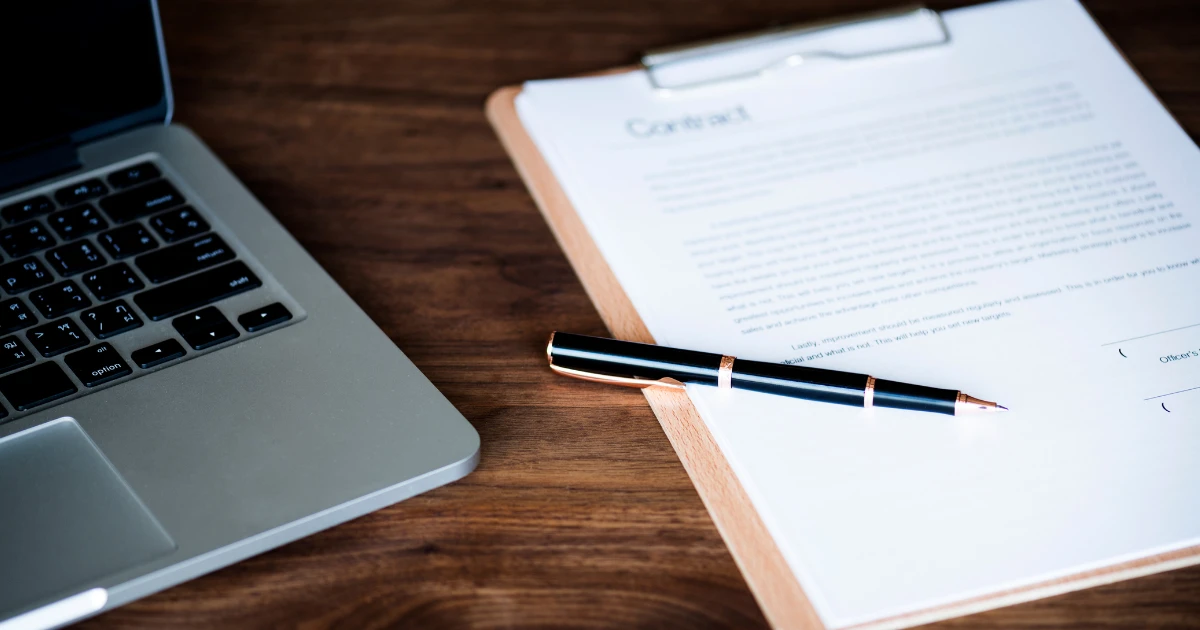
フリーランスエンジニアが法人化を成功させるためには、登記手続き以外にも、その後の税務・社会保険・社内体制の整備まで一貫した準備が必要です。
どれか1つでも不備があると、業務開始後に大きなトラブルにつながる可能性があるため、あらかじめ全体の流れを把握しておくことが重要です。
ここでは、フリーランスエンジニアが法人化する際に必要な手続きを解説します。
法人を設立するには、まず会社設立の意思決定を担う「発起人」を選びます。発起人は通常、フリーランス本人が担うことが多いです。あわせて、社名・所在地・事業内容・出資額などを定めて、「定款」を作成しましょう。
定款とは、会社の根本規則が記載された「会社の憲法」ともいえる重要な文書であり、将来のトラブルを防ぐためにも内容をしっかり精査することが大切です。
なお、株式会社の場合は、この定款を公証役場で認証してもらう必要があります。
定款の作成が完了したら、設立事項で定めた資本金の金額を、発起人の個人口座に払い込みます。この資本金は、登記申請時の添付書類として通帳のコピーや払込申請書で証明します。
資本金額は法人口座開設時や取引先の与信審査においても確認されるため、安易に決めず慎重に検討しましょう。最低で1円から法人の設立が可能ですが、将来的な信用や融資を考えると、最低でも30〜100万円程度は用意しておくことが現実的です。
会社を設立する際は、必要書類を用意しましょう。
すべての書類が揃ったら、管轄の法務局にて設立登記を申請します。
登記申請が受理された日が法人の設立日となり、その日から法人格を持った会社として活動できるようになります。なお、登記完了までは約1週間程度かかることが一般的です。
設立登記が完了した後は、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場などに所定の届出を提出しましょう。
具体的には、以下の書類の提出が必要です。不備があると税務上の優遇措置が受けられない場合もあるため、早めに専門家に確認を依頼すると安心です。
| 書類 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 所轄税務署 | 税務署:2か月以内 都道府県税事務所や市町村役場:自治体によって異なる |
| 都道府県税事務所 | ||
| 市町村役場のいずれか | ||
| 青色申告承認申請書 | 所轄税務署 | 3か月以内 |
| 給与支払事務所の開設届出書 | 所轄税務署 | 1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 所轄税務署 | 規定なし |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 所轄税務署 | 設立第1期の確定申告書の提出期限まで |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 所轄税務署 | 設立第1期の確定申告書の提出期限まで |
フリーランスエンジニアが法人化した場合は、代表者1人でも社会保険への加入が義務づけられており、設立後は健康保険組合や厚生年金の加入手続きが必要です。
これにより、個人事業主のときより多くの保険料を毎月納付する必要があるため、キャッシュフロー計画に組み込んでおく必要があります。
保険料の計算方法や納付期限を理解していないと、延滞金が発生する可能性があるため、設立初期のうちに手続きの流れを整理しておきましょう。
役員報酬は、法人の事業年度が開始する前に金額を確定し、定款や株主総会議事録などに正式に記録しておく必要があります。
報酬の設定は節税や社会保険料に大きく影響するため、経営計画や手元の資金、将来的な資金繰りなどを見据えて慎重に決定することが重要です。
設定した金額は原則として1年間変更できないため、税理士と相談しながら、キャッシュフローに問題のない役員報酬を定めましょう。

法人化は登記を済ませれば終わりというものではなく、法人としての事業運営を円滑にスタートさせるための準備も欠かせません。
たとえば、法人口座の開設や各種書類の法人仕様への切り替え、契約関係の整備など、業務の仕組みを法人運営に合わせて変更する必要があります。
こうした準備が不足していると、法人化後に事務処理の負担が増え、トラブルにつながる可能性があるため、事前にしっかり体制を整えておきましょう。
ここでは、フリーランスエンジニアが法人化する際の準備を解説します。
法人化後は、帳簿の作成や申告内容が複雑になり、会計処理や税務申告の専門知識が欠かせません。
フリーランスエンジニアとして開発に集中したい場合は、税理士との顧問契約を結んでおき、税務面の業務を委託することで負担を減らせます。
設立登記や定款作成をスムーズに進めたい場合も、司法書士に依頼することで、申請漏れの可能性を減らせ、安全に法人化できます。
なかには、設立から運営までをワンストップで支援してくれる事務所もあり、活用すれば大幅に負担が軽減されるでしょう。
法人設立時には、資本金の金額や会社名、本店所在地を決める必要があります。
資本金は1円から設定可能ですが、社外からの信用や銀行口座開設時の審査を考慮すると、現実的には30〜100万円以上が妥当です。
会社名は商標登録されている他社と被らないよう、事前に検索しておくと安心です。
所在地は、自宅か登記が可能な賃貸物件を新たに契約しましょう。その際、郵便物の受け取り体制が整っているかを確認しておくことで、事業に必要な荷物や書類も受け取りやすくなります。
法人の銀行口座を開設する際は、基本的には以下の書類を用意しましょう。ただし、金融機関によって必要な書類は異なるため、手続き前に確認しておくと安心です。
法人口座は、開設先によって審査の厳しさが異なります。とくに、メガバンクや地方銀行では取引実績や所在地、事業内容まで細かく確認されるケースも少なくありません。ネットバンクであれば、メガバンクよりも法人口座の開設にあたり、審査がゆるやかな傾向があります。
早めに複数の金融機関を比較して、選択肢を決めておき、必要な書類を整えておくとスムーズに申請できるでしょう。
法人化後は、請求書や名刺、契約書類などを法人名義に切り替える必要があります。
請求書にはテンプレートに法人番号や所在地、法人名、代表者名を明記しておきましょう。
今まで名刺を持っていた場合も、法人化後は法人名義で再作成し、ロゴや肩書きのデザインを見直すことで、新たな取引先を作る際も信頼を得やすくなります。
代表印や銀行印、角印などの会社印も、法的文書や金融手続きに不可欠なため、早めに用意しておくことが大切です。
法人化することで、領収書や請求書の保存義務、帳簿の記帳方法などが個人事業主のころに比べて煩雑になります。そのため、経理作業や書類管理の体制を見直さなければなりません。
たとえば、クラウド会計ソフトを導入して、定期的に帳簿を入力できる体制を整えることで、日々の経理作業の負担を軽減できます。
法人化後も、ルールに沿った正確な書類管理ができていなければ、税務調査時に大きなリスクとなるため注意が必要です。

本記事では、フリーランスエンジニアが法人化するメリットについて、デメリットや必要な手続きも交えて解説しました。
フリーランスエンジニアが法人化することで、節税や信用力の向上、社会保険の充実など、多くの恩恵を受けることが可能です。しかし、法人化はメリット以外にも、経営にかかるコストや法的な義務が増えることも否定できません。
安易に法人化するのではなく、自身の売上やライフスタイル、将来設計を踏まえて慎重に検討しましょう。
メリットとデメリットを正しく理解したうえで、しっかり準備を整えておけば、法人化することで個人事業主から経営者として成長できるはずです。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く