40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
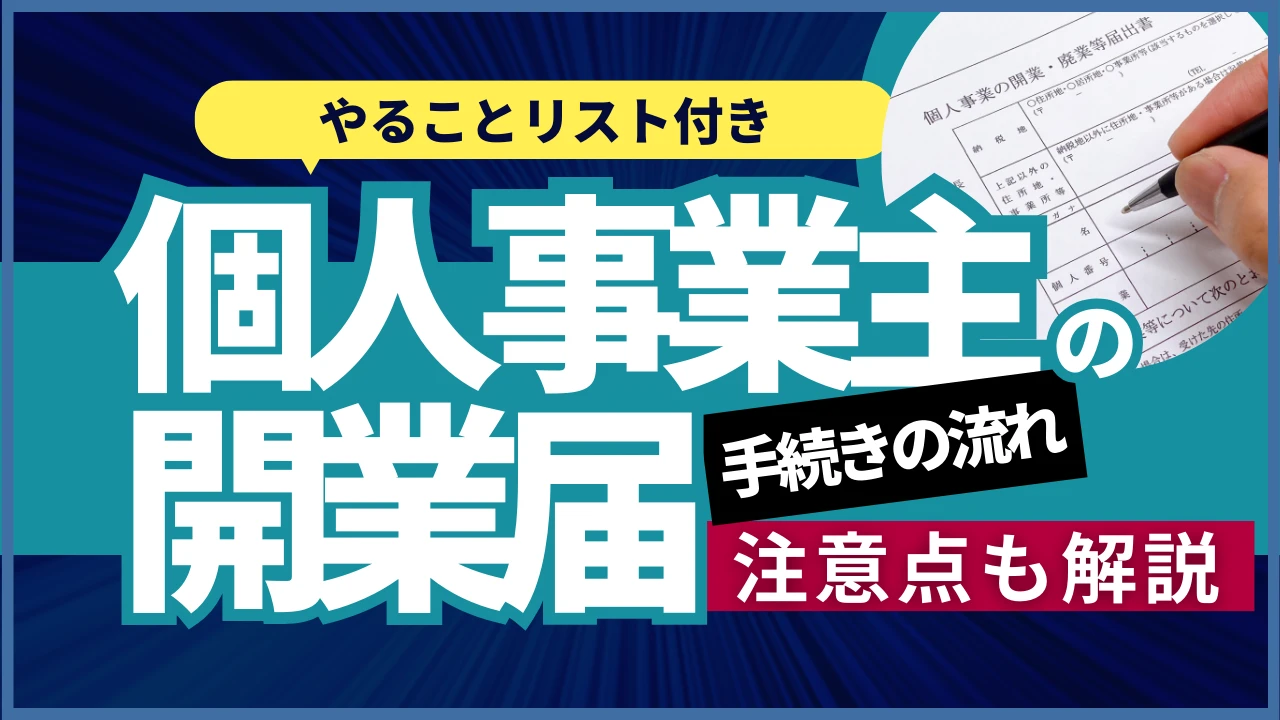
開業届とは個人で事業を営むことを開始した旨を税務署に届け出る書類のことです。個人事業主として活動していくためには、開業届の提出や国民年金への切り替え、青色申告の申請などやるべきことがたくさんあります。個人事業主として安心して事業を開始するために必要な情報をまとめているのでぜひチェックしてみてください。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
開業届とは、個人が事業を開始した旨を税務署に届け出る書類です。個人事業主として活動するためには、開業届の提出や厚生年金から国民年金への切り替え手続きなどやるべきことがいくつかあります。
ここでは、個人事業主が開業時にやるべきことをリスト付きで紹介します。あわせて、開業前に知っておくべきことや開業日の決め方、開業届を出さないとどうなるのかといった気になるポイントを網羅的にまとめました。
これから個人事業主として活動していきたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

個人事業主の開業届とは、個人事業主が事業を開始したこと(おもに事業内容と事業所の場所)を税務署に届けるための書類を指します。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
開業届は、所得税法 第229条により、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。ただし、この期限を過ぎてしまってもペナルティが課せられたり、税務署から提出を催促されたりすることもありません。
開業届を提出しなくても特に罰則はありませんが、開業した年の事業収支をすべてまとめて税務署に確定申告する必要があります。
事業によって一定以上の収入を得て確定申告を行わない場合は、脱税行為にあたるため、追徴課税や刑法の対象となってしまいます。
個人事業主として開業する際、提出が必須といえる書類は、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」と、都道府県の税務署に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」の2種類あります。
出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」,独立行政法人中小企業基盤整備機構「個人事業の開業手続き」

出典:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」
税務署へ提出する「個人事業開業・廃業等届出書」は、一般的に「開業届」と呼ばれる書類です。開業から1月以内に居住するエリアを管轄する税務署に提出をする必要があります。
開業届は国税庁のホームページ(個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用))からダウンロードするか、最寄りの税務署で入手できます。
なお、国税庁の「国税局・税務署を調べる」のページを開くと、郵便番号・住所あるいは、地図から簡単に自宅の最寄りの税務署を調べることができます。
| 名称 | 個人事業の開廃業届出書(開業届) |
| 提出する時 | ・新たに事業を開始したとき ・事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転したとき ・事業を廃止したとき(廃業届) |
| 対象者 | 新たに事業所得、不動産所得、山林所得を得る事業を開始した人 |
| 提出期限 | 事業の開始などの事実があった日から1ヶ月以内 |
| 書類の入手方法 | ・最寄りの税務署の窓口 ・国税庁のサイトからPDFをダウンロード |
| 提出方法 | ・最寄りの税務署に持参または郵送 ・e-Taxを利用しての電子申請 |
開業届と似た書類に都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」があります。こちらは提出しなくとも罰則などはありません。提出の有無に関わらず、個人事業税は納付手続きが行われます。
開業届を出す際には、あわせて「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
義務付けられているわけではありませんが、提出しないと青色申告控除などの優遇措置が受けられなくなります。事実上の必須提出書類です。
「個人事業税の事業開始等申告書」は各都道府県によって提出期限や方法が異なるので、「事業開始等申告書+都道府県名」と検索して確認しましょう。
 開業時には、開業届の届け出以外にもやるべきことがたくさんあります。ここでは、個人事業主になる人がやるべきことを漏れなく対応を進められるようにリスト化しました。
開業時には、開業届の届け出以外にもやるべきことがたくさんあります。ここでは、個人事業主になる人がやるべきことを漏れなく対応を進められるようにリスト化しました。
【やることリスト】
| 事業計画を立てる | |
| ローンを検討している場合は契約しておく | |
| 国民年金や国民健康保険に切り替える | |
| 開業届を提出する | |
| 青色申告承認申請書を提出する | |
| 許認可申請を行う | |
| 資金調達をする | |
| 銀行口座を開設する | |
| Webサイトや名刺などを準備する | |
| インボイス制度について理解を深める | |
| 利用できる補助金・助成金がないかチェックする |
以下もぜひ参考にしてみてください。
まず、開業すると決断した段階で、事業計画を立てることを推奨します。扱う商品やサービスはもちろんのこと、価格設定、ターゲット、販売形態、集客方法など事業内容を具体化すると良いでしょう。
自分が提供するサービスや製品を選んでもらうために、競合他社との差別化を図る必要があります。競合分析を行い、市場での立ち位置などを把握しておきましょう。
金融機関などからの融資を希望している場合は、事業計画書を作成し、計画した内容を落とし込みます。
個人事業主になると会社員の時よりも審査に通過しにくくなる傾向にあるため、カーローンやクレジットカードの契約を検討している方は、会社員のうちに手続きを済ませておくと安心です。
とくに、在籍確認が必要な場合、会社員であれば勤め先に連絡が入り、申請した企業で働いていることを証明できます。一方、個人事業主は、企業や組織に属さず、個人で事業を営むため、第三者に事実確認を行うことができません。
個人事業主は会社員のように毎月安定した収入を得られるわけではないので、万が一の事態に備えて、クレジットカードやカードローンを1枚持っておくと安心できるでしょう。
会社員から個人事業主になる場合、社会保険から国民年金や国民健康保険に切り替える必要があります。
会社を退職した日から14日以内に市町村役場で切替手続きを行いましょう。なお、会社員として働きながら副業をする場合、社会保険の切り替え手続きは不要です。
個人事業主として開業する場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署へ提出しましょう。
原則、事業を開始して1ヶ月以内に提出することが義務付けられています。ただし、1ヶ月を過ぎた場合でも罰則やペナルティが課されることはありません。
開業届は、税務署へ直接持参する方法と、郵送する方法、「e-Tax」というシステムを用いてWeb上で提出する方法があります。「個人事業の開業・廃業等届出書」は、国税庁の公式サイトからダウンロード、または、税務署の窓口で受け取れます。
詳しくは、後述する「【個人事業主】開業届の書き方と手続きの流れ」にてご確認ください。
確定申告で最大65万円の青色申告特別控除を受けたい方は、「所得税の青色申告承認申請書」を開業日から2ヶ月以内に提出しましょう。
青色申告を行うには、開業届を先に提出しておく必要があります。青色申告を行うメリットや具体的な手続きに関しては「【最新】フリーランスが青色申告を行うコツ!やり方や対象者、注意点を個人事業主・フリーランス向けに解説」をご確認ください。
開業にあたって、許認可申請が必要な業種(事業)もあります。許認可申請とは、特定の事業を行ううえで必要な手続きのことで、所定の行政機関に申請をして許可や認可を取得します。
許認可が必要な事業として、建設業や車の運転、食品の製造・販売、危険物の取り扱いなどが挙げられます。
資金調達が必要な場合は、金融機関などに求められた書類を用意し、申請する必要があります。個人事業主の事業資金の借入先としては、下記の4つが挙げられます。
| 借入先 | 詳細 |
| 日本政策金融公庫 | 政府系金融機関の1つである日本政策金融公庫が実施する融資制度 |
| 自治体の制度融資 | 地方自治体で実施している融資制度・補助金制度 |
| 民間金融機関(銀行や信用金庫)の融資 | 民間の銀行・信用金庫による融資 |
| ビジネスローン | 貸金業者が提供するローン商品 |
上記のほか、ファクタリングやクラウドファンディングなどのサービスもあるので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
なお、個人間融資は違法な高金利で貸付けられたり、違法な取り立てなどの被害に遭ったりといったトラブルも発生しており、危険性が高いので注意が必要です。
出典:個人事業主が利用できる融資の種類は?他の資金調達方法も紹介 | みずほ銀行,個人事業主向けの融資制度・補助金制度などをご紹介!カードローンによる事業資金の借り入れについても解説
屋号での事業用銀行口座を開設したい方は、開業届を提出した後で手続きをします。
屋号とは、個人事業主がビジネスにおいて使用する「個人事業の名前」のことを指し、開業届に自分で決めた屋号を記載して提出します。国税庁では、下記のように記述されています。
引用:屋号・雅号の入力について屋号・雅号の入力について
屋号又は雅号とは、個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。
よって、個人事業者の方においては、商店名等を入力してください。
雅号とは、著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける別名のことです。
屋号付きの銀行口座があれば、個人名義の口座に振り込みをするよりも、顧客やクライアントが安心感を持てるでしょう。
個人事業主として事業を営むために、Webサイトや名刺などを必要に応じて準備すると良いでしょう。
会社員の場合は、営業担当者が仕事を獲得してくるケースが多いですが、個人事業主は自分で営業活動をして案件を取ってこなければなりません。
その際にWebサイトや名刺があれば、自分の強みを相手により伝えやすくなったり、名前や事業内容を覚えてもらえたりするのに役立ちます。
営業活動が苦手な方は、フリーランス向けのエージェントを活用するのも良いかもしれません。「SEES」ではフリーランスエンジニア向けの案件を豊富に取り扱っているので、エンジニアとして活躍していきたい方はぜひチェックしてみてくださいね。
SEESでフリーランス向けの案件を探す
インボイス制度は、個人事業主として活動していくうえで、押さえておかなければならない制度の1つ。2023年10月1日から導入が開始され、何らかの影響を受けたフリーランスの方も多いのではないでしょうか。
インボイス制度は、経過措置を設けており、段階的に控除額が変わってくるので今後の動向についても理解を深めておきましょう。
| 期間 | 内容 |
| 2023年10月1日 | インボイス制度導入開始 |
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
出典:インボイス制度について|国税庁,2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
地方自治体の中には、個人事業主向けの融資制度や補助金・助成金制度を実施しているケースもあります。
地方自治体が実施する融資制度や補助金・助成金制度は、金融機関による融資に比べ、低金利で借入できる傾向にあります。さらに、返済期間が長く、返済方法が柔軟である場合が多いので、お住まいのエリアで利用できる制度がないか確認しましょう。
「お住まいのエリア+融資制度」「お住まいのエリア+助成金制度」などと検索すると、地方自治体(都道府県、区市町村)の公式サイトが表示されるので、チェックしてみてくださいね。

 開業届を提出して個人事業主になる最大のメリットは、節税効果の高い青色申告での確定申告を行えることだと言えるでしょう。
開業届を提出して個人事業主になる最大のメリットは、節税効果の高い青色申告での確定申告を行えることだと言えるでしょう。
ほかにも個人事業主になることのメリットは、複数あるので、開業届を提出すべきか悩んでいる方はぜひチェックしてみてください。
納税は国民の義務ですので必ず行う必要がありますが、事業運営上は税負担は軽減したいところです。この税負担軽減の方法として、節税をすることは可能です。
個人事業主の所得税および住民税の納付額は確定申告により決まります。この確定申告の際に、節税できる方法が青色申告の利用です。
青色申告を利用する場合には、開業時に「個人事業開業・廃業等届出書」、「青色申告承認申請書」の提出を行っておく必要があります(前述)。この手続きを行ったうえで、確定申告時に青色申告を利用し、所得の確定と経費の計上を行います。
大まかに言えば、収入である事業所得から経費および各種の所得控除をひいた額が所得税の対象となります。可能な限り経費と所得控除を利用することで、課税対象額を減らすことができ、節税へと繋がります。青色申告を行うことで経費として計上できる範囲を広げたり、特別控除の利用が可能となるため、節税対策として重要なのです。
なお、確定申告時に青色申告を利用して最大65万円(※)の青色申告特別控除を受ける場合には、複式簿記による帳簿の作成が必要となります。複式簿記による帳簿の作成、記帳は、会計用のソフト、アプリ、サービスを利用すると効率的です。
※最大の控除を受けるためには、一定の条件があります。
青色申告を利用しない場合には、自動的に白色申告となり、特別控除額は最大10万円です。
【青色申告で節税が可能】
開業届を提出すると、個人名ではなく「屋号名」を名義とした銀行口座を開設できます。屋号とは、国税庁によると「個人事業者の方が使用する商業上の名のこと」と明記されています。
個人名の銀行口座を事業用口座として使用しても特に問題はありませんが、「取引先が報酬の振り込みをする際に、個人名よりも屋号名の方が信頼を得やすくなる」といったメリットがあるのです。
また、事業用とプライベート用の口座を分けることで、経理作業がスムーズに進むことも利点の1つです。
銀行口座の開設時に必要な書類は、銀行によって異なりますが、開業届の控えの提出を求められる場合もあるため、屋号での口座開設を考えている人は、開業届を提出した方が良いでしょう。
開業届を出すと、対外的に自分の職業を証明できる点がメリットです。会社に勤めている場合は、勤め先から社員証や在職証明書を発行してもらうことができますが、フリーランスの場合はそのような証明書はありません。
そのため、銀行などから融資を受けたり、ローンを組んだりする際にも職業の証明ができないため審査に通りにくくなってしまうのです。
開業届の控えがあれば、職業を証明することができるので、クレジットカードの発行や融資の審査、保育園の申請なども行えるようになります。
個人事業主として融資を受ける、あるいは共済に加入する、保育園にお子さまを預ける必要があるといった場合は、開業届を提出しておいた方が良いでしょう。
出典:横浜市「横浜市へ提出する就労証明書について(令和6年度)」
出典:札幌市「就労証明書」
 ここでは、開業届の書き方や、提出する際に必要なもの、手続きの流れについて解説していきます。
ここでは、開業届の書き方や、提出する際に必要なもの、手続きの流れについて解説していきます。
なお、税務署の窓口で書類を受け取り、そのまま必要項目を記入して提出する場合は、窓口の担当者が教えてくれるので、スムーズに届け出ることができるでしょう。
「個人事業開業・廃業等届出書」は国税庁によりフォーマットが定められています。参考リンクの国税庁ページよりフォーマットはpdf形式でダウンロードが可能です。
主な入力項目と注意点には下記があります。国税庁のサイトに入力例がありますので、参照しながら記入するとよいでしょう。控えもフォーマットに沿って作成してください。
| 届出の区分 | 「開業」の事務所・事業所の「新設」を選択します。 |
| 納税地 | 自宅をオフィスとする場合は、住所を記載します。 |
| 氏名/生年月日 | 氏名を記入します。生年月日も忘れずに記入しましょう。 |
| 個人番号(マイナンバー) | マイナンバーカード、あるいは通知カードに記載されているマイナンバーを記入します。 |
| 職業 | 特別な決まりはないので、客観的に分かる名称で記入します。 ただし、業種によって税率が異なるので、注意が必要です。 |
| 屋号 | 自分で自由に付けることが可能ですが、変更には開業届の再提出が必要です。 |
| 開業日 | 実際に開業した日を記載します。提出日ではありません。 |
| 事業の概要 | 職業欄に記入した内容について、より具体的に記載します。 |
【開業届を提出する際に必要なもの】
開業届を提出する際に必要なものは、基本的に「個人事業の開業・廃業等届出書」と「マイナンバーカードが確認できるもの」の2点です。
青色申告を行う場合は、一緒に「青色申告承認申請書」も用意しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。
また、税務署の窓口に開業届を提出する場合は、なりすましを防ぐために本人確認書類による本人確認が行われます。郵送する場合は、国税庁のホームページからダウンロードできる「本人確認書類(写)添付台紙」に本人確認書類の写しを添付する必要があります。
なお、以前の開業届には押印欄が設けられていましたが、近年は廃止されており、開業届の提出時の押印は不要となっています。しかし、提出書類を書き間違えた際には、二重線と修正印による対応が求められるため、万が一の場合に備えて印鑑を持って行くと良いでしょう。
開業届を提出する際の流れは、「書類を受け取る→必要項目に記入する→提出する」の3ステップです。
開業届の提出方法は、「税務署の窓口」「郵送」「e-Tax」の3つから都合の良い手段を自由に選べます。基本的に開業届の提出において、費用は発生しませんが、郵送する場合のみ送料と切手代がかかります。
また、開業届をe-Taxで提出すると、書面で控えを残すことはできません。 その代わり、e-Taxで提出した後に税務署からメッセージボックスにメッセージが送られてくるため、そちらを控えとして利用します。
開業届の控えは、「屋号で銀行口座を作る場合」や「事業資金の融資を受ける場合」「小規模企業共済に加入する場合」などさまざまなシーンで提出が求められるため、メッセージを削除しないように、大切に保管しておきましょう。
開業届を提出すると開業日が確定します。開業日は事業の開始日であり、さまざまな手続きで必要となる重要な日付です。例えば、この開業日は税金の起算日ともなります。提出日が開業日となるのではなく、開業届の開業日に入力した日付が有効となります。確定申告をまたがなければ日付をさかのぼって、提出日より前の日付での申請が可能です。
また、開業届の内容に誤りがあった場合や記載内容を変更したい場合は再申請が可能です。再申請は別にメリットがあるわけではありません。できれば手間を減らすために、手続きは一度で終わりにしたいところです。
 開業届を提出して個人事業主になる前に知っておくべき注意点が6つあります。
開業届を提出して個人事業主になる前に知っておくべき注意点が6つあります。
【提出前に知っておきたい4つの注意点】
雇用保険の失業手当をもらっている場合も注意が必要です。個人事業主として働き始めたタイミング(開業日)で資格が失効します。
求職活動をしながら開業の準備をしている段階では、失業手当をもらうことができますが、開業届を提出したら、開業の準備期間が終わったとみなされ、受給できなくなります。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」4. 開業届の対象職業や所得によって税率や課税対象が異なる
所得税において配偶者の扶養に入っている場合、個人事業主として一定以上の収入額があれば扶養枠から外れます。
健康保険組合の扶養条件などによって異なり、「個人事業主として開業した時点で扶養から外れる」あるいは「一定の利益を超えると外れる」といったルールが設けられているので、事前に確認しておきましょう。
納税の手続きも大きく違うため注意が必要です。会社員は年末調整を行っておけば、源泉徴収として会社が手続きを行ってくれることが普通です。
個人事業主は毎年2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う必要があり、その後納税額が確定します。青色申告を利用したい場合は、事前に手続きを行っておく必要があるため要注意です。
開業届を作成する際に注意しておきたいのが「職業」の欄です。個人事業税の「税率」や「課税対象」は、職業の種類や所得によって異なるため、事前に把握しておく必要があります。
国税庁では非課税にあたる職業であっても、都道府県税の区分において課税対象となる場合があるので、管轄の市町村での取り扱いもあわせて確認しておきましょう。
下の画像は、一例として東京都の場合を掲載しているので、参考程度にご覧ください。

「freee開業」「マネーフォワード クラウド開業届」などのクラウドサービスを利用することで簡単に開業届を作成できます。
画面のガイダンスに従って入力することで書類が作成でき、あとは印刷して提出するだけです。しかも、先述のサービスは無料で利用できますので、気軽に試せる点も魅力だといえるでしょう。
 個人事業主に関する悩み事の相談先は、それほど多くないので、不安や疑問を解消できずに困ってしまう方も多いでしょう。
個人事業主に関する悩み事の相談先は、それほど多くないので、不安や疑問を解消できずに困ってしまう方も多いでしょう。
ここでは、個人事業主の開業に関するよくある質問に対して、Q&A形式で回答するので、気になる項目があればぜひチェックしてみてください。
【よくある質問】
開業届は、年間の事業所得(収入から経費などを差し引いたもの)が目安として48万円以上の場合に提出する必要があります。
ただし、副業で副収入を得ている会社員は、48万円ではなく、年間で副業の利益が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。
個人事業を営んでいる事業者は、税務署に開業届を提出しなければ、「個人事業主」にはなれません。個人事業主として事業を営むのであれば開業届を提出する必要があります。
また、一定以上の収入を得ながら、開業届を提出していない人は、確定申告で事業所得を申告しなければ脱税にあたるため注意が必要です。
個人事業主として開業する方法は、自宅の最寄りの税務署に開業届を提出するだけですので、非常に簡単です。開業届は「国税庁の公式ホームページからダウンロードする」、あるいは「税務署の窓口で直接受け取る」ことができます。
開業届を提出すること以外にも、税金や社会保険の手続きや、青色申告承認申請書の提出なども同時に進めなければならないので、本記事の前半で解説している「開業時の個人事業主のやることリスト」をチェックして必要に応じて対応をしましょう。
開業届をダウンロードしたり、提出したりする際に費用は発生しません。0円で開業の手続きが完了するため、法人設立と比較して非常に簡単だといわれています。
ただし、郵送で提出する場合は、封筒と切手代がかかるので、費用を抑えて開業したい方は、税務署への直接提出、あるいはオンライン提出を選択しましょう。
開業届の提出先は税務署の窓口です。確定申告と同様になります。居住する地域の所轄の税務署で手続きをおこないましょう。
下記の国税庁のサイトにて居住地の管轄税務署が検索できます。郵送による提出も可能です。
出典:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
開業届を出さず事業を行い、確定申告を行わないと脱税にあたります。追徴課税の発生や最悪のケースでは刑事罰の対象ともなります。ただし、事業による収入が一定額以下の場合は不要です。
開業届は本来は開業後1月以内に提出するように定められています。提出が遅れても直接的な罰則はありません。しかし、確定申告までに手続きが終わっていない場合は、青色申告などが利用できませんのでご注意ください。
開業届を出していれば、登録住所に手続きのお知らせおよび入力用紙などが送られてきます。これに従って確定申告を行うことで、申告漏れを防ぐことができます。
事業に必要なものであれば、開業日前に仕入れたものでも経費として計上することができます。開業届を出す前の経費は、「開業費」として計上できるのでご安心ください。
明確に決められているわけではありませんが、開業費として認められるためには、開業日の数ヶ月前〜1年前程度の間の支出が妥当とされています。随分前の仕入れを経費として扱うのは難しいと考えられるため、開業を検討している方は開業日から逆算して計画を立てましょう。
個人事業主の開業に関する相談先として、税務署や商工会・商工会議所などが挙げられます。「freee開業」や「マネーフォワード クラウド開業届」のように開業届の作成〜提出までをサポートしてくれるサービスもあります。
 個人事業主として開業する際には、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」、「青色申告承認申請書」の二つを税務署に必ず提出しましょう。提出していない場合には確定申告時に損をしてしまう可能性があります。
個人事業主として開業する際には、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」、「青色申告承認申請書」の二つを税務署に必ず提出しましょう。提出していない場合には確定申告時に損をしてしまう可能性があります。
また、同じ税務署に提出する書類として「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」、「青色事業専従者給与に関する届出手続」があります。こちらは必要に応じて提出します。
税務署以外にも行う必要があるのが年金、公的医療保険、確定拠出年金の切り替えなどの個人に関わる手続きです。個人事業主の場合は自分で手続きする必要があります。
開業する業種によっては官公庁に「許認可」が必要となる場合もありますので、こちらも確認しておきましょう。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く