40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
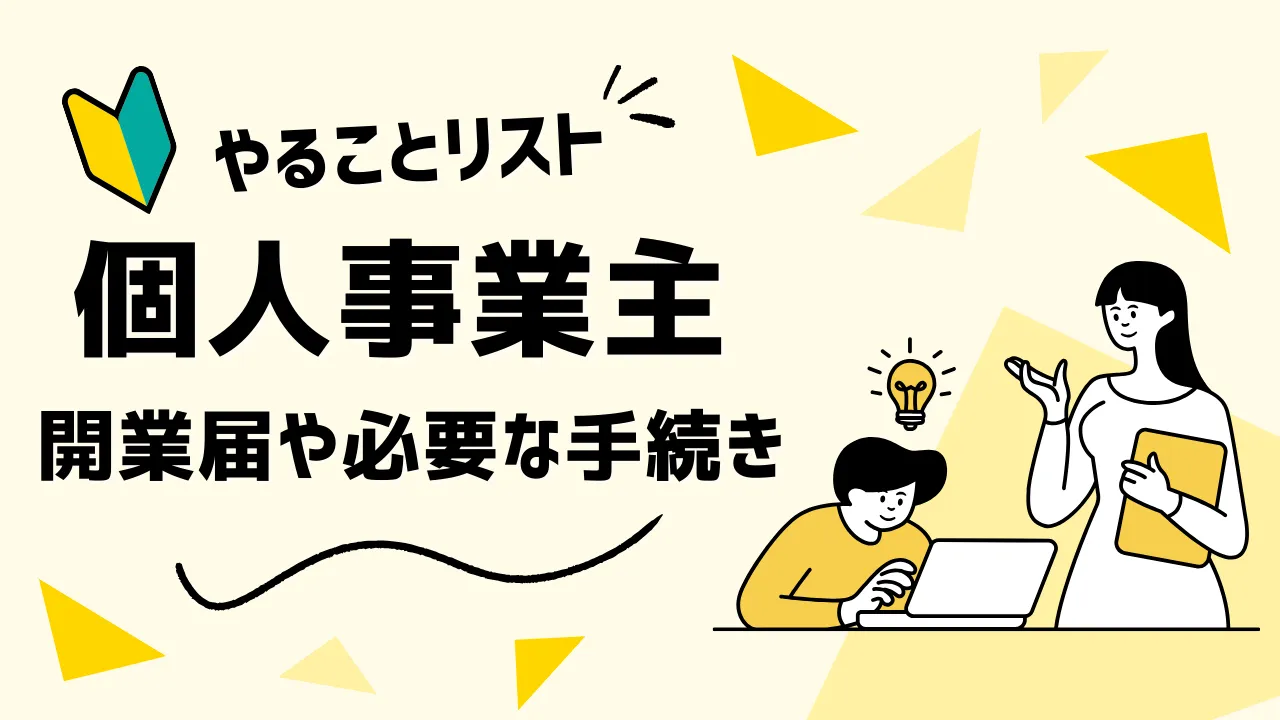
個人事業主とは、株式会社や合同会社のような「法人」を設立せずに個人で事業を営む人のことを指します。管轄の税務署に「開業届」を提出すれば、個人事業主として活動することが可能です。
今回は、個人事業主の定義やフリーランス・自営業との違い・個人事業主になるメリットデメリットについて紹介します。個人事業主になるために必要な準備や手続き、納める税金などもまとめたので、個人事業主について理解を深めることができるでしょう。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
消費税法の基本通達1-1-1において個人事業主は、「事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者」、同第2条1項3号では「事業を行う個人」と定義されています。
個人事業主とフリーランスは、基本的に同じような働き方・ワークスタイルですが、「開業届」の提出の有無に大きな違いがあります。
個人事業主として事業を開始する場合は、税務署へ「開業届」を提出する必要があります。一方、フリーランスとして活動する場合は、とくに開業届の提出義務はありません。
なお、フリーランスを支援する非営利団体の「フリーランス協会(正式名称:一般社団法人 プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会)」では、フリーランスを「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」と定義しています。
フリーランスが税務署へ「開業届」を提出した際には、フリーランスではなく、個人事業主となります。
出典:一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
自営業者も個人事業主と同じように、会社に属さず独立した状態で事業を営む人のことを指します。
ただし、自営業の場合は、法人化して事業を経営しているケースがほとんどです。たとえば、株式会社や合同会社のように法人化した形態の事業者を意味します。
なお、自営業者が法人組織に所属している場合は、定款の作成や法務局での設立登記が必要となります。

個人事業主になると、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、「収入を増やせる」「自由な働き方ができる」「節税につながる」といった個人事業主になるメリットについて6つにわけて解説します。
出典:J-Net21「起業マニュアル 個人事業のメリット・デメリット」
関連記事:フリーランスで働く13個のデメリット|メリットについても詳しく解説
個人事業主は、実力次第で大きく稼ぐことができます。スキルや技術力が高ければ、その分、高単価な案件を多く受注することが可能です。
会社員の場合は、仕事の成果がすべて給与に直結するわけではなく、基本給の額面を大幅にアップさせることは難しいでしょう。
個人事業主は、努力した分「収入」という目に見える形で反映されるので、達成感や、やりがいを得られたり、モチベーションアップにつながるはずです。
個人事業主は、働く時間・場所・人などすべて自分のスタイルやルールで決められます。組織に属していると、就業規則や社内ルール、上司の指示に従って働く必要があります。
個人事業主は、働く場所にも縛りがないので、セキュリティ面を十分に管理できるなら、カフェやホテル、旅先、コワーキングスペースなどで仕事をすることが可能です。
労働時間や、働く場所、休暇などをすべて自分で自由に決めたい人には、”個人事業主の働き方”が合っているといえるでしょう。
会社員の場合は、一定の年齢になると「定年」となり、退職する必要があります。個人事業主は、年齢制限がないので、身体が元気であればいつまでも働き続けられるのです。
実際に、シニアエンジニア向けの案件紹介サイト『SEES』では、40代以上・年齢不問案件を専門に取り扱っています。
定年退職後であっても実績や能力を持ち得ていれば、そのスキルを求める企業も多いため、個人事業主として、長く活躍できるでしょう。年齢に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
「定年後も働きたい」という方は、ぜひ『SEES』の案件をチェックしてみてください。
青色申告承認申請書を提出し、青色申告者になると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
本記事の『個人事業主が経費にできるもの』にて詳しく解説していますが、材料や商品の仕入れはもちろんのこと、事務所の家賃や水道光熱費なども経費として扱うことができるため、節税にもつながるでしょう。
青色申告は、白色申告よりも手間がかかりますが、経理ソフトを使用して記帳し、確定申告をすることで、慣れない手続きもスムーズに進められます。
個人事業主は、”会社員と比べて社会的な信用の確保に手間がかかる”といった欠点がありますが、屋号があれば一定の信頼を得られる場合があります。
屋号とは、事業を営む際に使用する「名称」のことで、屋号を付けるか付けないかは任意となっています。
屋号を付けることで事業をわかりやすく伝えられたり、取引先や顧客からの信用を得られたりするので、なるべく付けた方が良いでしょう。
個人事業主になるには、税務署に「開業届」を提出する必要があります。
開業届の提出は、「税務署の窓口へ直接持参する方法」、「書類を郵送する方法」「e-Taxを使用してオンラインで提出する方法」の3つから選択でき、面倒な手続きは不要です。手続きする際の手数料や印紙税などの費用も一切発生しません。
自営業で株式会社を設立する場合は、登記申請が必要となり、定款認証費用5万円と登録免許税15万円の合計20万円がかかります。
それに加え、別途資本金も必要になるため、個人事業主は比較的簡単に開業できるといえるでしょう。

個人事業主になることで、自由な働き方ができたり、年収アップが期待されたりとさまざまなメリットがあることがわかりました。
しかしその反面、事務作業や営業などすべて自分ひとりで行わなければならないといった欠点もあります。
ここでは、個人事業主になるデメリットを4つにわけて紹介するので、個人事業主になってから後悔しないために、チェックしておきましょう。
個人事業主は、売上管理や、経費の支払い、確定申告の記帳などをすべて自分で行わなければなりません。
会社員の場合は、税金が毎月の給与から天引きされ、年末調整も会社が行ってくれるため、煩わしい事務作業は不要で業務に専念できます。
個人事業主は、”受注した業務を遂行する”こと以外に、営業業務や事務作業、確定申告に向けた準備など、日頃から仕事に直接関係のない業務を行う必要があります。
個人事業主は、社会保険料を全額負担する必要がある点が会社員との大きな違いだといえるでしょう。
会社員から個人事業主になると、社会保険のうち、労災保険と雇用保険に加入できなくなり、健康保険と年金保険の保険料が全額自己負担になるのです。
個人事業主になる際には、加入できる保険の種類や特徴を把握したうえで、健康保険や年金の見直しが必要です。
個人事業主は、企業や組織に所属していないため、第三者への身元保証が行えません。その結果、社会的な信用が低いとみなされ、クレジットカードやカーローン、住宅ローンの審査に通過しづらくなるのです。
銀行などの金融機関からお金を借りるハードルが会社員より高くなるので、融資を希望している方は個人事業主になる前に申し込みをしておきましょう。
また、お子様を保育園に預けて働きたいと考えている方は、入園審査に通過してから個人事業主になった方が良いかもしれません。
自宅で働くことの多い個人事業主は、「自宅に居る=自宅保育ができる」と捉える自治体もあり、激戦エリアの場合、入園選考に落ちてしまう可能性があるからです。
個人事業主は、確定申告の帳簿が必要だと先述しましたが、それ以外にも営業や事務作業も必要になります。
自分の仕事をスケジュール通りに完遂することはもちろんのこと、同時に下記のスキルや業務も求められるので、幅広く器用にこなさなければなりません。
なお、どんなに高いスキルを持ち合わせていても、待っているだけでは依頼はきません。受け身姿勢ではなく、自発的に行動できる人でなければ大きく稼ぐことは難しいでしょう。
「営業や事務作業が苦手」「本業だけに専念したい」という方は、営業代行や経理代行などのサービスを利用すると、理想の働き方を実現できるかもしれません。
案件紹介サイトやSNSなど無料で案件を獲得できるサービスは、積極的に活用しましょう。

個人事業主として事業を開始する場合は、手続きや契約などの事前準備が必要です。どれもしっかりポイントを押さえて進めれば難しいことはないので、1つずつこなしていきましょう。
【個人事業主になるためのやることリスト】
個人事業主であっても、従業員を一人でも雇用した際には、雇用保険や労災保険に加入する必要があります。
また、業種によっては常時雇用している従業員が5人以上いる場合、健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入しなければなりません。
個人事業主になるには、税務署へ開業届を提出する必要があります。開業届は、所得税法第229条によって「事業を開始した日から起算し、1ヶ月以内に提出しなければならない」と定められています。
このように提出期日が定められているものの、期限を過ぎてしまった場合に何らかのペナルティが課せられることはなく、税務署から提出を促されることもありません。
副業や一時的な収入の場合は事業にはあたらないため、開業届を提出する必要がない場合もあります。
出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
個人事業主の確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類が存在します。
青色申告を行うためには、複式簿記での記帳が必要となり、手間がかかりますが、最大65万円の控除を受けられるので、「青色申告承認申請書」を提出して青色申告を選択した方が良いでしょう。
| 白色申告 | 青色申告 | |
| 帳簿のつけ方(記帳方式) | 単式簿記 | 青色申告特別控除65万円/55万円の場合、複式簿記 |
| 確定申告時の提出書類 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 (貸借対照表・損益計算書) |
| 必要な手続き | なし | 「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出 |
| 特別控除額 | なし | 最大65万円/最大55万円/最大10万円の3段階 |
| 赤字の翌年への繰越 | 原則不可 | 3年間可能 |
申告書は、国税庁の「所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロードあるいは、所轄の税務署の窓口で受け取ることができます。
日本ではすべての国民が公的医療保険に加入する義務があります。そのため、会社員や個人事業主、フリーランスなど、働き方に関わらず、必ず加入する必要があるのです。
個人事業主は、厚生年金保険や雇用保険、労災保険などには、基本的に加入することができません。そうした理由から国民健康保険への加入が必須だといえます。
ただし、例外的に勤務していた会社の健康保険の継続(最長2年間)を選択することが可能です。前職の健康保険の継続を選択する場合は、退職から20日以内に手続きを済ませなければなりません。
また、厚生年金から国民年金への変更手続きも必要になります。
事業用銀行口座の作成やクレジットカードの新規発行は、必須ではありませんが、個人事業主として本格的に活動を開始する前に用意しておくことを推奨します。
その理由は、個人事業主の所得と経費を、事業用銀行口座やクレジットカードで管理すると、お金の流れを把握しやすくなるからです。
会計ソフトと利用明細を連携させると、日々の会計処理にかかる手間を減らすことができたり、確定申告の際に正確性の高いデータで申告できたりといったメリットもあります。
個人事業主として事業を開始する前に、事業計画を立てて、「事業計画書」を作成した方が良いでしょう。事業計画書の作成は、必須ではありませんが、資金調達を検討している場合は、金融機関や投資家、起業家支援サービスへの提出が必要になるため、用意しておくとスムーズです。
事業計画書に含める内容は、下記のとおりで、事業内容をはじめ、収益見込みや今後事業をどのように運営していくかを示します。

副業を行い「事業所得」を得ている会社員は、「開業届」を税務署に提出し、開業する必要があります。
年間の事業所得が48万円を超える場合は、確定申告を行う必要があるので、理解を深めておきましょう。


| 勘定科目 | 費用の例 |
| 租税公課 | 個人事業税や固定資産税、自動車税といった税金 |
| 荷造運賃 | 宅配便や郵便物の梱包材や送料など |
| 水道光熱費 | 水道料金、電気料金、ガス料金など |
| 旅費交通費 | 公共交通料金、タクシー代、駐車場代、宿泊費など |
| 通信費 | 電話代、インターネット料金、切手、サーバー代など |
| 広告宣伝費 | 名刺、パンフレット制作費など |
| 接待交際費 | 顧客との飲食やお祝い金、贈答品など |
| 損害保険料 | 火災保険、自動車保険など |
| 修繕費 | 事務所や自動車の修繕など |
| 消耗品費 | 事務用品や電球、USBメモリなど |
| 減価償却費 | パソコンやカメラ、自動車など、高額な固定資産を一定期間にわたり計上する費用 |
| 福利厚生費 | 慶弔見舞金、慰安旅行、従業員の健康診断費など |
| 給料賃金 | 従業員、スタッフに支払う給料 |
| 外注工賃 | 外注スタッフなどに支払うギャランティ |
| 利子割引料 | 借入れした運転資金やローンなどの利息 |
| 地代家賃 | 事務所の家賃や駐車場代など |
| 貸倒金 | 売掛金や貸付金などの回収できなくなった金額 |
| 雑費 | クリーニング代やゴミ処理費用など、どの項目にも該当しない少額の費用 |
| 専従者給与 | 青色事業専従者(家族など)に支払う給料 |
「事業に必要な出費」は、基本的に経費として扱うことができます。
経費は、確定申告で収入から差し引いて計上すれば、節税につながるので、少額の経費であってもしっかりと管理しましょう。
| 具体例 | 基準 |
| 自宅兼事業所で支出する家賃や公共料金、固定資産税など | 事業として使用している部分の床面積 |
| 車両の経費として支出するガソリン代や車検費用など | 総走行時間のうち、事業として使用している時間 |
| 仕入れた食材を自宅でも使用している場合など | 一回あたりの消費単価を設定し、消費した回数をカウントする |
個人事業主になるために必要な資格や条件はないので、基本的には誰でもなれます。会社員や専業主婦、法人経営者、学生など、すでに何らかの肩書がある人でも、開業届を税務署へ提出することで個人事業主になれます。
ただし、公務員や副業を禁止している会社に勤めている人は、個人事業主になれません。
また、個人事業主は事業の業務だけではなく、営業から経理業務まで幅広い仕事を一人で遂行します。スケジュール・体調・金銭などの管理をすべて行わなければならないので、セルフマネジメント力のある人でなければ、個人事業主として長く活躍し続けることは難しいでしょう。
個人事業主になる場合には、先に挙げた4つの税金を納める際に損をしないために、事前に準備を行っておく必要があります。その事前の準備(=やらなくてはならないこと)は大きく下記の3つです。
・税務上の手続き(届出の提出)
・開業準備期間中に使った経費の集計
・節税対策の準備
個人事業主となるタイミングで、税務のためにしておかなくてはならない手続きです。開業の届出と青色申告の申請が事実上の必須の手続きとなります。また、必要に応じて付随する申請も行っておきましょう。
個人事業主として働く場合、開業届は必須と考えて提出しておきましょう。正確には届を出さずとも個人事業主として働くことはできるのですが、税制上の損が発生してしまいます。
開業届と同時に提出するべきなのが青色申告の申し込みです。こちらも損をしないための事実上必須の手続きとなります。
付随する3種類は自分の事業での必要性を確認して、必要に応じて提出しましょう。
いわゆる開業届と呼ばれる書類です。この開業届の提出は、国に対して事業を始める宣言ともなるものです。また、個人事業主にとっては、業務・就労の証明ともなるため、開業届の写しは重要となる書類です。入力のフォーマット、入力内容については下記の国税庁のサイトなどからご確認ください。
参考:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
フリーランスエンジニアの場合は、開業届の事業の種類がITエンジニアなどとなります。ネットワークエンジニア、サーバーサイドエンジニアといった、さらに細分化したエンジニア職種を記載してもよいです。
※個人事業主の開業届に関してはこちらにまとめています。ご参照ください。
こちらは個人事業主が確定申告において、節税のために重要となる青色申告を行うことを申請する書類です。青色申告に関しては、後述していますが、個人事業主が節税を行う上で多くの優遇を受けることができる制度ですので、必ず手続きをしておきましょう。
確定申告の直前の提出では間に合わなくなることもあり得ます。入力のフォーマット、入力内容については下記の国税庁のサイトなどからご確認ください。
青色申告はフリーランスエンジニアにとって行政の手続き上で必須ではありません。しかし、利用しなかった場合には支払う税金額が増えてしまうため事実上必須となっています。
以下の3種類の書類については、必要に応じて提出を行います。いずれも従業員を雇う場合(青色専従者は家族や親族を雇う場合)に必要となる書類です。フリーランスエンジニアとして、一人で働く場合には基本的に提出は不要です。必要となったときに後から提出もできます。
参考:国税庁「[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
参考:国税庁「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
参考:国税庁「[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続」
上記の手続きに関して、届出先は居住地域の管轄税務署です。
下記の国税庁のページから検索しましょう。
近年ではこれらの個人事業主になる際に必要となる書類を作成することのできるサービスも登場しています。
freee開業、マネーフォワード クラウド開業届などのクラウドサービスは、PCからインターネットに接続できる環境があれば無料で利用可能です。画面のガイダンスに従い入力を行うことで、手続き書類が簡単に作成できます。
これらのクラウドサービスは会計用のサービスと連動しており、個人事業主としての事業状況をまとめる場合には会計用のクラウドサービス利用も非常に便利です。ただし、こちらは基本有料です。
ここまでにも何度か本文中に登場したのですが、個人事業主となる方に確定申告時に必ず利用していただきたい制度が青色申告です。
青色申告とは、個人事業主が事業における取引を帳簿に記帳し、その記録から確定申告を行うことを指しています。この青色申告を行う場合には、前述の「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。開業届と同時に提出しておくのが一番間違いのないタイミングです。
青色申告の中でも、簡易簿記による記帳と、複式簿記による記帳が存在します。複式簿記の場合、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができるのが大きなメリットです。
青色申告を利用するメリットとして、下記の3点があげられます。
・青色申告特別控除
青色申告の最大のメリットは確定申告時に、青色申告特別控除を受けることができることです。所得に対して課税が行われるのですが、控除は課税時に所得から除外する部分にあたります。より平たく言えば、控除分は税金がかからなくなるわけです。
青色申告特別控除では最大65万円が控除対象です。ただし、複式簿記による記帳および電子による確定申告が条件となります。複式簿記による確定申告で書面での手続きの場合は55万円が控除対象です。
青色申告を行わない場合には、自動的に白色申告となります。帳簿は簡易簿記でよいものの、特別控除は最大10万円となってしまいます。
・少額減価償却資産の特例
青色申告特別控除を行う場合には、少額減価償却資産の特例を受けることもできます。
少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の償却資産は購入・使用開始した年度に一括して経費計上できるというルールです。特例を利用せずに固定資産として複数年にわたって分割で経費計上することも可能です。
少額減価償却資産の特例の利用には期限があり、令和4年3月31日までとなっています。(2021/11/9時点。過去にも延長をしているため、最新の情報は下記の国税庁のサイトをご覧ください。)
参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
少額減価償却資産の特例を利用することで、経費計上のタイミングをコントロールできます。利益の大きい年度に経費計上を実施すれば、利益との相殺ができ、節税が可能です。
・青色事業専従者給与の計上
青色事業専従者給与とは、個人事業主が配偶者や親族に支払った給与を経費として、所得から控除できるルールです。青色申告を行う場合にのみ利用可能です。こちらも従業員給与を経費とできるため、節税につながります。
なお、事前に青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の提出が必要です。
青色申告を行う場合の具体的な手続きについて記載します。
1.青色申告承認申請書の提出
確定申告を行う年の3/15までに青色申告承認申請書を税務署に提出しておきます。
青色申告を開始する年からでよいのですが、事実上開業年に手続きすべきです。
なお、特例として「その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内」での提出が認められます。
参考:国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」
2.複式簿記による記帳
事業の収支を複式簿記により記帳を行います。フリーランスエンジニアとなったばかりで簿記の方法が分からない場合には、会計ソフトウェアを利用することをおすすめします。
会計ソフトウェアではガイダンスに沿って入力を行っていくことで、自動的に複式簿記での対応が可能です。freee会計などのクラウド型のサービスの利用が非常に便利です。
3.青色申告用の確定申告書類を作成し、確定申告を提出
開業届を出していれば、税務署より確定申告の連絡がきます。
入力用紙も同封されていますので、こちらを利用してもよいでしょう。
確定申告の書類作成についても、各種の会計ソフトウェアに機能が備えられていることが多いです。フリーランスエンジニアにこれからなる場合にはこちらのご利用をおすすめします。
書類の作成ができたら、税務署へ直接提出するか郵送で提出しましょう。
e-Taxという国税電子申告・納税システムを利用した確定申告も可能です。こちらの利用にはアカウントの作成が必要となり、その際マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(Android端末・iPhone)が必要になります。手元に用意してから手続きを進めるとスムーズに提出できるでしょう。
これから個人事業主となるための開業準備期間中の経費は、開業費として確定申告で計上できます。この開業費については税制上の優遇が受けられます。
こちらは開業年にしか利用できないため、申告しておかないと損をしてしまいます。
 開業準備はどんなことをする?
開業準備はどんなことをする?フリーランスエンジニアの開業準備として必要なのは、主に下記2点でしょう。
・上記の開業届などの書類の準備
・事業に必要な環境の準備
書類の準備については、「税務とかかわるフリーランスになるための手続き」をご参照ください。
事業に必要な環境の準備とは、仕事をする場所や道具、名刺、ホームページの準備などを示しています。人によって変わる部分ではありますが、フリーランスエンジニアであれば仕事道具として、机、イス、パソコン、ネット回線などが必要となってきます。
また、クレジットカード、ローン、銀行口座などの準備も行っておきましょう。
これらは社会的信用のある会社員のうちにやるべき手続きです。
開業費とは、開業までの準備活動で使った経費のことです。
経費として認められるものとしては、下記のようなものが挙げられます。
・打合せ費用
・手土産代
・調査期間の通信交通費
・パソコンなどの機器購入代
・セミナー参加費
・事務所家賃
下記の10万円の制限があるため、例えばパソコンでも10万円を超えた場合は経費の対象外となることにはご注意ください。
経費の対象外となるものとしては、下記があげられます。
・10万円以上のもの(一点で10万円以上)
・敷金・礼金
・仕入代金
これらの経費対象外となるものは、固定資産として計上する必要があります。
個人事業主となるタイミングで開業費を計上しておく理由は、開業費は繰延資産として扱われ税制上の優遇を受けることができるからです。
繰延資産は任意償却が可能です。開業から5年間の任意の年度に経費にできます。つまり、黒字が出た年に経費として計上することで、所得との相殺を行い課税対象額を減らし、節税することができるのです。
納税は日本国民の義務です。フリーランスエンジニアとて例外ではありません。働いてお金を稼いだら、納税する必要があります。納税をしない場合は、脱税行為となり、犯罪を犯してしまうことになります。
ただし、個人事業主の場合は納税額が減るように確定申告上の調整はできます。節税は個人事業主が事業を行ううえで損をしないための手段なのです。
個人事業主の場合は、所得に対して税がかかります。
ですので、所得を抑えることが節税につながります。
一般に所得は下記の式で求められます。
所得 = 売上 - 経費
確定申告時には、まずは経費として申告できるものをできるだけあげておくことが節税となります。それ以外にも、節税のための方法があるため、以下に記載します。
・青色申告特別控除
先にも記載していますが、確定申告時に青色申告を行うことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。青色申告の手続きを行っていないと、自動的に白色申告となり、最大10万円の特別控除のみが対象となります。
またこちらも前述のとおり、青色申告特別控除の申請時には少額減価償却資産の特例を受けることもできます。経費計上のタイミングのコントロールとなるため節税につながります。
・青色事業専従者給与の計上
青色事業専従者給与の計上とは、個人事業主が配偶者や親族に支払った給与を経費として、所得から控除できる制度です。こちらも事前の申請が必要です。
・家事関連費の区分計上
家庭と事業で利用するものの一部の利用料を経費として計上できます。例えば自宅兼仕事場の場合、家賃を仕事で使った割合分経費として計上可能です。
・小規模企業共済への加入
小規模企業共済は個人事業主や中小企業の経営者向けの退職金積立制度です。こちらの積立費用は経費に計上できるため、所得控除扱いになります。
・法人成り
個人事業主が事業を法人化することを法人成りといいます。一般的には会社を起業することを示します。法人成りをすると、個人事業主とは税制の適用が変更されるため、節税になることがあります。所得が一定額を超える場合は、法人成りしたほうがよいとされています。
その他にも、下記のような節税方法があります。
・倒産防止共済
・確定債務の計上
・重損失の繰越控除
・ふるさと納税
フリーランスエンジニアが事業に関して払わなくてはならない税金は下記の4つです。
また、下記の二つについても、フリーランスエンジニアは自分で納める必要があります。
事業に関する税ではないため本記事では深くは触れませんが、開業に向けて手続を行っておきましょう。まずはこれらの税金の概要について確認していきます。

「所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。」
参照:国税庁「所得税のしくみ」
所得税は事業者が国に対して納める税金です。税率は累進課税という制度をとっており、所得金額が大きければ大きいほど税率が上がる仕組みとなっています。
所得税の税率については国税庁「所得税の仕組み」ページよりご確認ください。
会社員の所得税に関して、収入は給与と賞与の合計額です。基本的には下記の式で表されます。
(給与収入 ー 給与所得控除ー 所得控除) * 税率 ー 税額控除
一方で自営業の所得税では、収入は事業所得です。ベースとなる式は下記です。
(事業所得 ー 経費 ー 所得控除) * 税率 ー 税額控除
会社員と比較して、経費が控除対象となることが大きな違いです。
また、自営業者の場合はエンジニアでもエンジニア以外でも計算式は同じです。青色申告については後述しますが、事前に手続きを行っておくことで控除額を増やせます。
住民税は、所得に対して居住する都道府県、市区町村に納める税金です。
個人市県民税とも呼び、所得を対象として課税されます。納税先となるのは基本的に住民票をおいている都道府県、市区町村です。都道府県民税と市町村民税に分かれますが、同時に納付するため両者をあわせて住民税と呼びます。
詳細なルールについては、居住する都道府県、市区町村によって変わるため、居住する市区町村のサイトを検索するのがよいでしょう。なおフリーランスエンジニアの場合は納税方法が会社員とは異なります。
会社員は特別徴収として、給与から天引きされる形で12分割して支払を行います。一方の個人事業主の場合は確定申告後に市区町村から納税通知が来ます。この納税通知に対し自分で手続きを行って住民税を納めることになります。年4回の分割での支払となります。一括納付も可能ですが、特に割引などはありません。
「個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。」
個人事業税は、個人事業のうち地方税法で定められた特定の業種向けの税金です。70業種が存在し、全国共通となっています。会社員には存在しない個人事業者向けの税金です。業種については上記の東京都主税局の「個人事業税」のサイトを参考としてください。
前年度の所得が290万円以下の場合は、全額控除となるため適用対象外です。各都道府県に納める税金のため、詳細や該当/非該当については居住する都道府県の税務署までお問い合わせください。
特にフリーランスエンジニアの場合、扱う案件および契約形態によって適用対象かどうかが変わります。詳細については所轄地域の税務署へ確認することをおすすめします。
個人事業主は顧客から受け取った消費税を間接税として納税する義務があります。
ただし、個人事業主の場合は売上高に関する適用条件があります。前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は、その年の消費税の納税義務は免除されます。フリーランスエンジニアに限らず、個人事業主に対する消費税のルールです。
なお、所得が1000万円を超えない場合は免税事業者となり、顧客から消費税をとっても納付の義務はありません。上記の条件を満たす場合、下記の式で消費税額が算出可能です。
顧客より受け取った消費税 - 仕入に払った消費税
消費税についてはこちらの記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

ここでは、個人事業主に関するよくある質問に対して、Q&A形式で回答していきます。気になる項目があれば、ぜひチェックして疑問や不安を解消しましょう。
個人事業主とは、会社や組織に属さずに事業を継続・反復して行う個人のことです。税務署に「開業届」を提出している人のことを指します。「開業届」を提出し、事業の開始を申請すると法律上、個人事業主として開業したことになります。
個人事業主とフリーランスの大きな違いは、税務署へ「開業届」を提出しているか否かです。
フリーランスは、会社や組織に雇用されず、個人として独立して仕事を請け負う人を指します。
個人事業主もフリーランスのように会社や組織に雇用されず、個人で事業を行う人のことを意味しますが、開業届を提出しています。
個人事業主になるメリットとデメリットは下記のとおりです。
【メリット】
【デメリット】
なお、メリットデメリットは、本記事の『個人事業主になる6つのメリット』『個人事業主になる4つのデメリット』にて、詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
個人事業主は、所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することで廃業扱いとなります。提出期限は廃業後1ヶ月以内です。
廃業届は、税務署に直接提出する方法のほか、郵送にて提出することもできます。
出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
個人事業主になるためには、税務署に「開業届」を提出する必要があります。開業届に加え、青色申告承認申告書を提出すれば、節税などメリットが得られるでしょう。
個人事業主になること自体は、非常に簡単ですが、個人事業主になってからは、確定申告に向けた事務作業、お金の流れの把握、営業、進捗管理などさまざまな業務に追われます。
「自分に合う案件を探す時間がない」「案件の探し方が分からない」という方は、株式会社Miraieが提供する案件紹介サイト『SEES』をご活用ください。
SEESは、エンジニア向け案件のほか、デザイナーやディレクター講師など幅広いIT系案件を保有しています。年齢不問・業務委託契約を掲載しています。理想の働き方を実現できるでしょう。
自分の持ち得ているスキルや、希望の報酬、勤務地などに絞り込んで検索することが可能ですので、案件探しにお役立てください。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く