40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
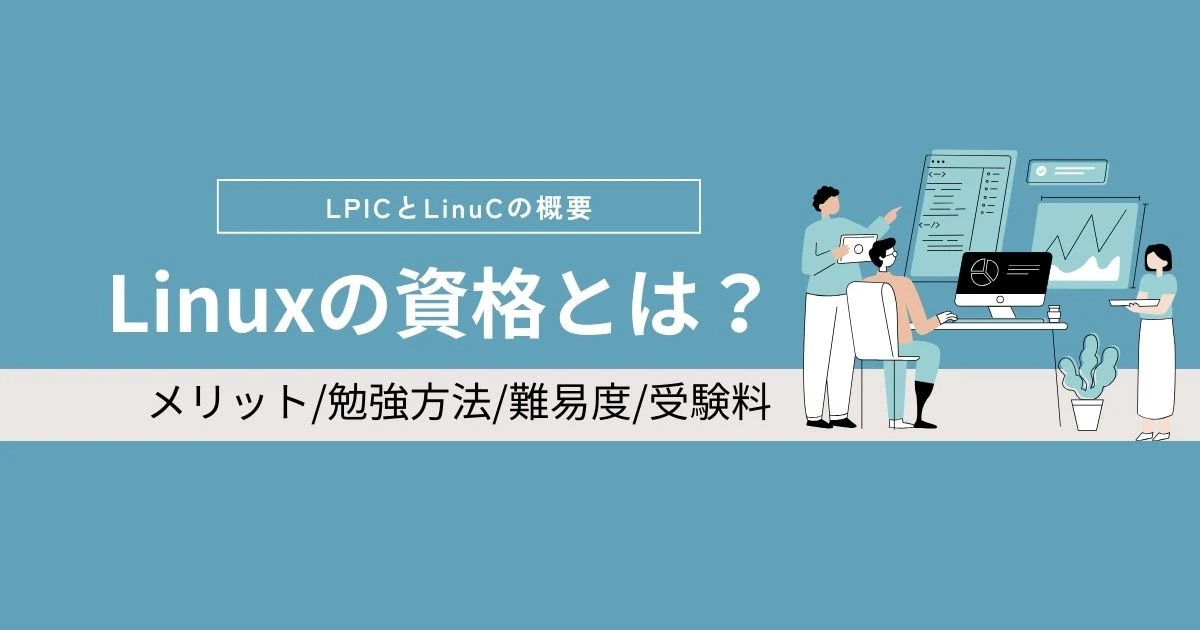
「Linuxの資格は意味がない」という声もありますが、実際にはLinuxのスキルを持つエンジニアは非常に高い需要があります。今回はLinuxの資格を取得するメリットや、意味がないと言われる理由について解説します。「LinuC」と「LPIC」の違いやそれぞれの試験内容、勉強方法、難易度、おすすめの参考書、受験料、有効期限についてもまとめました。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
サーバーOSとして多くの企業で採用されている「Linux」。クラウドや仮想化、コンテナなどの最新技術にも欠かせないOSであるため、Linuxの資格を持つエンジニアは非常に高い需要があります。
この記事では、Linuxの代表的な資格「LinuC」と「LPIC」を中心に、試験内容や勉強時間・方法、受験料などを紹介します。併せて、Linuxの資格を取得するメリットや、取得後のキャリアパスについてもまとめました。
資格の難易度がひと目でわかる一覧表も作成したので、自分に合う資格試験がどれか判断できるでしょう。
| 試験 | 試験時間 | 出題数 | 出題形式 | 勉強期間目安 | 難易度 | |
| LPIC-1 | 101試験 102試験 | 各90分 | 各60問 | 多肢 選択式 記述式 | 3か月~ 半年程度 | 低 |
| LPIC-2 | 201試験 202試験 | 各90分 | 各60問 | 多肢 選択式 記述式 | 半年~ 1年程度 | 中 |
| LPIC-3 | 300試験 303試験 305試験 306試験 | 各90分 | 各60問 | 多肢 選択式 記述式 | 半年~ 1年程度 | 中 |
| LinuC レベル-1 | 101試験 102試験 | 各90分 | 各60問 | 多肢 選択式 記述式 | 1か月~ 3か月程度 | 低 |
| LinuC レベル-2 | 201試験 202試験 | 各90分 | 各60問 | 多肢 選択式 記述式 | 3か月~ 半年程度 | 低 |
| LinuC レベル-3 | 300試験 (混在環境) 303試験 (セキュ リティ) 304試験 (仮想化と 高可用性) | 各90分 | 各60問 | 多肢 選択式 記述式 | 半年~ 1年程度 | 高 |
| LinuC システム アーキ テクト | SA01試験 SA02試験 | 各90分 | 各40問 | 多肢 選択式 記述式 | 半年~ 1年程度 | 高 |



Linuxにはさまざまな試験があり、難易度ごとにグレードがわかれている試験も多いです。Linuxの資格を取得することで、エンジニアとしてのLinuxのスキルをわかりやすく証明できるようになるでしょう。
また、Linuxの資格取得のために勉強することで、業務で必要なLinuxの知識やスキルを身につけていくことができます。そのため、技術力の向上にもつながるでしょう。
エンジニアとして転職活動をする場合や、フリーランスとして案件獲得を目指す場合など、どれだけエンジニアとしてLinuxのスキルを持っていたとしても、それを表すことができなければうまくいきません。
しかし資格を取得しておけば、自身のスキルを客観的に証明できるようになります。たとえばLinux関連の資格を持っていれば、インフラ関係の案件で需要の高い人材と判断されやすくなるでしょう。
このように、Linuxの資格を保有しておくことで、自身のキャリアアップにもつながりやすくなります。
Linux関連の資格の中でも、LPICは世界共通の資格となっています。日本国内だけでなく、世界で通用する資格です。
そのため、LPICを取得しておけば海外での転職活動にも活かすことができるでしょう。将来エンジニアとしてグローバルに活躍したいと考えているのであれば、LPICを取得しておくことはおすすめです。
SEESでLinux関連の案件を探す

「LinuCレベル1」は、仮想環境を含めたLinuxシステムの基本操作やシステム管理が行えるレベルの、Linux技術者を認定する資格です。
LinuCレベル1を取得することにより、仮想マシンとコンテナを含んだLinuxサーバーの構築、運用・管理ができること、クラウドを安全に運用できること、オープンソースを業務に活用できることの裏付けになります。
LinuCはステップアップ式の資格となっているため、まずはLinuCレベル1の取得を目指しましょう。
LinuCレベル1の試験内容は、Linuxシステムの構築や運用、管理に関する60問ほどの問題を90分以内で解答していきます。
出題範囲は、Linuxシステムに関する基本操作やLinuxディストリビューションの知識、システムに欠かせないネットワークやセキュリティの基本設定などです。
また、クラウド構成技術に必要な仮想化とコンテナの基礎知識に加えて、オープンソースの深い造詣も求められます。
| 101試験 出題範囲 | ・Linuxのインストールと仮想マシン・コンテナの利用 ・ファイル・ディレクトリの操作と管理 ・GNUとUnixのコマンド ・リポジトリとパッケージ管理 ・ハードウェア、ディスク、パーティション、ファイルシステム |
| 102試験 出題範囲 | ・シェルおよびスクリプト ・ネットワークの基礎 ・システム管理 ・重要なシステムサービス ・セキュリティ ・オープンソースの文化 |
出典:LinuCレベル1 101試験 出題範囲 | LPI-Japan
出典:LinuCレベル1 102試験 出題範囲 | LPI-Japan
一般的な勉強時間としては、初心者であれば1ヶ月、経験者であれば3ヶ月程度が目安となっています。
初心者の場合は、Linuxの特性の把握に努めると良い結果につながりやすいため、未経験でもLinuCの資格は取得できます。
LinuCの資格を実務で活かすためには、暗記するだけの勉強法ではなく、仕事でどのように役立つかという点を意識して勉強すると就業後に差が出てくるでしょう。
「LinuCレベル2」は、仮想環境を含めたLinuxのシステム設計やネットワーク構築で、アーキテクチャに基づいた設計や導入、保守、問題解決が実現できるレベルのLinux技術者を認定する資格です。
LinuCレベル2を取得することにより、Linuxシステムの設計や構築、監視、トラブルシューティングができるスキルを証明できます。
また、仮想マシンやコンテナの管理運用ができること、セキュリティやシステムアーキテクチャの基本を理解し、サービス設計や構築、運用管理ができることの裏付けになるでしょう。
LinuCレベル2は、クラウド環境だけでなくオンプレミス環境においての知識も問われます。
主にLinuxによるシステムやネットワークの構築、応用的なサーバー構築などの問題が出題されます。異なるOSによる混在環境ネットワークの計画をはじめ、セキュリティ設定や一貫性の維持など1つ上のスキルが求められるでしょう。
また、プロジェクトをマネージメントする能力も問われるため、幅広い見識が必要になってきます。
| 201試験 出題範囲 | ・システムの起動とLinuxカーネル ・ファイルシステムとストレージ管理 ・ネットワーク構成 ・システムの保守と運用管理 ・仮想化サーバー ・コンテナ |
| 202試験 出題範囲 | ・ネットワーククライアントの管理 ・ドメインネームサーバー ・HTTPサーバーとプロキシサーバー ・電子メールサービス ・ファイル共有サービス ・システムのセキュリティ ・システムアーキテクチャ |
出典:LinuCレベル2 201試験 出題範囲 | LPI-Japan
LinuCレベル2の勉強時間は、レベル1をパスしたばがりの人であれば約3ヶ月~半年、Linuxの実務経験がある場合は約3ヶ月が目安です。
LinuCレベル2は2つの試験を合格することで認定されます。201、202試験を合格しなければなりませんが、取得する順番は問わないため、取り組みやすいものから挑戦していくといいでしょう。
2つの試験のボリュームが大きいことから、いかに勉強時間を確保するかが重要です。
「LinuCレベル3」は、「混在環境」「セキュリティ」「仮想化システムや高可用性システム」という、3つの分野での高度なスキルを証明できる資格です。
LinuCレベル3には「LinuCレベル3 300 Mixed Environment」「LinuCレベル3 303 Security」「LinuCレベル3 304 Virtualization & High Availability」の3種類があります。
これらの資格を取得することで、エンタープライズレベルでの仕事ができるLinux技術者であることの裏付けになります。
LinuCレベル3は、エンタープライズレベルでの技術力を認定する試験です。
試験内容は、Sambaを使ったユーザー管理やドメインコントロール、セキュリティやパフォーマンス調整などを行います。また、ファイルやプリントサービスをWindowsと統合した経歴が必要です。
さらにSambaとLDAP、OpenLDAPを用いた環境構築やキャパシティプランニングなども併せて出題されます。
| 300試験 出題範囲 | ・OpenLDAP の設定 ・OpenLDAPの認証バックエンドとしての利用 ・Sambaの基礎 ・Sambaの共有の設定 ・Sambaのユーザとグループの管理 ・Sambaのドメイン統合 ・Sambaのネームサービス ・LinuxおよびWindowsクライアントの操作 |
LinuCレベル3の平均勉強時間は、半年~1年程度が目安とされています。
LinuCの最難関とされるレベル3は出題範囲が広く、Sambaに関する基礎、共有の設定、ドメイン統合などから出題されます。またLinuCレベル3は、ほかのレベルと比べて合格基準が高く設定されているため、答えの精度を高めることが重要になるでしょう。
さらにキーボード入力問題も出題されるため、そちらの対策を練る必要もあります。
「LinuC英語版」は外国人技術者向けに英語で実施されているLinuCです。英語版のLinuCは日本を含めた全世界に配信されており、国内外を問わず英語受験のニーズに対応し、Linux技術者のグローバルな活躍を支援するものとなっています。
試験の内容やグレードなどは日本語のLinuCと全く同じですが、公式サイトでの説明なども全て英語になっています。
「LPIC-1」は、Linuxの基本操作や知識について問われるエントリーレベルの資格です。LPIC-1では、主にコマンドラインを使ってメンテナンスタスクを実行し、Linuxで基本的なネットワークを構成するスキルを測ります。
LPICもステップアップ式の資格となっているため、上位資格の取得を目指す場合でもまずはLPIC-1を取得する必要があります。
LPIC-1は、101試験と102試験から出題されます。
主な試験内容は、バックアップやリストアなどの簡単な保守作業、Linuxコマンドラインを扱うユーザーへの支援などです。またワークステーションのインストール設定やLAN接続、モデム経由でのインターネット接続なども含まれます。
基本はCBT方式ですが、キーボード入力問題も出題されます。
| LPIC-1試験101トピック | ・システムアーキテクチャ ・Linuxのインストールとパッケージ管理 ・GNUとUnixのコマンド ・デバイス、Linuxファイルシステム、ファイルシステム ・階層構造規格 |
| LPIC-1試験102トピック | ・シェルとシェルスクリプト ・インターフェースとデスクトップ ・管理業務 ・基幹システムサービス ・ネットワークの基礎 ・セキュリティ |
出典:Linux Professional Institute LPIC-1
勉強時間の目安
LPIC-1の平均的な勉強時間は、1ヶ月~3ヶ月ほどが目安とされています。
難易度はさほど高くないですが、Linux経験者でも予習なしでは合格できません。そのため、問題集などで今の実力を正確に把握し、苦手な部分を補うことが大切です。
またLPIC-1は、800点中500点ほどを上回れば合格できるとされていますが、出題範囲外の問題や難題が用意されているため、想定難易度以上の準備を行っておくと安心でしょう。
「LPIC-2」は、LPIC-1よりも実践的な知識が問われる上位資格です。中小規模の混合ネットワークを管理するスキルを認定します。
LPIC-2ではネットワークやストレージ管理、Webサーバーやメールサーバー、ドメイン、ディレクトリ構成など、幅広い範囲の問題が出題されます。また、実務経験が3年程度ある人を対象としているため、実機での試験対策を行うのがおすすめです。
LPIC-2は、中規模までのサイトを管理するスキルの資格です。
Linux、UNIX、Windowsが混在するネットワークの設計や、安全な稼働を行うための問題が出題されます。それぞれのLANサーバーやインターネットゲートウェイ、インターネットサーバーが対象です。
また、実務だけでなくアシスタントの監督をしたり、案件内容や予算についての助言やサポートなども試験範囲となっています。
LPIC-2認定を受けるには、 「201試験」と「202試験」の両方に合格し、「LPIC-1認定」を保持している必要があります。
| LPIC-2試験201トピック | ・容量計画 ・Linuxカーネル ・システムスタートアップ ・ファイルシステムとデバイス ・ストレージデバイスのアドミニストレーション ・ネットワーク構成 ・システムメンテナンス |
| LPIC-2試験202トピック | ・ドメインネームサーバー ・ウェブサービス ・ファイル共有 ・ネットワーククライアント管理 ・電子メールサービス ・システムセキュリティ |
出典:Linux Professional Institute LPIC-2
LPIC-2の勉強時間の目安は、LPIC-1を取得したばかりだと3ヶ月ほど、経験者であれば半年程度とされています。
LPIC-2の取得には、順不同ながら201試験と202試験の両方に合格する必要があります。条件として、1つ目の試験の合格から5年以内に2つ目にも合格しなければなりません。
LPIC-2からは、マネージメントに絡む問題も出題されるため、幅広くポイントを押さえることが重要です。
「LPIC-3」は、「混在環境」「セキュリティ」「仮想化とコンテナ化」「高可用性(HA)とストレージ」という、4つの分野での高度なスキルを証明できる資格です。
Linuxを扱う実務では、エンジニアによって専門分野がわかれるため、4つの専門分野での認定試験が設けられています。
LPIC-3は、300試験、303試験、304試験のいずれかを合格することで得られる資格です。
300試験は、Linux、Windows、UNIXによる混合環境においてのトラブルシューティングなどが出題されます。303試験では、システム設計とサーバー構築のスキルが問われ、セキュリティに関する知識も必要とされます。
実務に活かしやすい304試験は、仮想化や高可用システムがメインです。
| LPIC-3エンタープライズセキュリティ試験のトピック | ・暗号技術 ・アクセス制御 ・アプリケーションセキュリティ ・オペレーションセキュリティ ・ネットワークセキュリティ ・脅威と脆弱性の評価 |
出典:Linux Professional Institute LPIC-3 Security
LPIC-3の勉強時間は、半年から1年程度が目安とされています。
LPIC-3は、LPIC-2を取得した後、すぐに勉強を開始することで合格する確率が高まります。そのため実機を使った勉強が効果的であり、実務に活用しやすくなるでしょう。
LPICのレベルを問わず、高難易度の問題は2割ほどであるため、取り組みやすい8割の問題を正確に素早く解いていくことが合格へのカギとなります。
Linux Foundation認定システム管理者(LFCS)は、Linuxシステム管理のスキルセットを証明できる資格です。Linux Foundationが主催している資格で、グローバルな評価につながる資格となっています。
主に、Linuxシステム管理者やオープンソースのキャリアをスタートした候補者を対象としている試験となっており、日本語が理解できる試験管による監督で実施されます。
| 対象領域 | 運用の展開:25% ネットワーク:25 % ストレージ:20% 基本コマンド:20% ユーザーとグループ:10% |
出典:Linux Foundation認定システム管理者 (LFCS-JP)
Red Hat認定資格は、Linuxディストリビューションの中でもエンタープライズ向けである、Red Hat系のスキルを証明できる資格です。実技試験が実施されるため、他のLinux試験よりも難易度は高いと言えるでしょう。
なお、Red Hat認定資格にはテクノロジー別、役割別に非常に多くの資格が設けられています。ここでは「Red Hat 認定システム管理者(RHCSA)」と「Red Hat 認定エンジニア(RHCE)」の2種類を紹介していくため、参考にしてみてください。
「RHCSA(EX200)」は、Red Hatを使用した大規模システムの管理や、運用に関する知識を証明できる資格です。RHCSAでは、3時間の実技試験が実施されます。
前提資格はありませんが、準備として「Red Hat システム管理 I(RH124)」と「Red Hat システム管理 II(RH134)」の受験が推奨されています。
| 試験の学習ポイント | ・基本的なツールの理解と使用 ・シンプルなシェルスクリプトの作成 ・稼働中のシステムの運用 ・ローカルストレージの設定 ・ファイルシステムの作成と設定 ・システムのデプロイ、設定、保守 ・基本的なネットワーク操作の管理 ・ユーザーとグループの管理 ・セキュリティの管理 ・コンテナの管理 |
「RHCE(EX294)」は、Red Hat Ansible Automation Platformを使用したシステム管理や、多数のシステムでシステム管理タスクを実行するための知識やスキルを証明できる資格です。RHCEでは、4時間の実技試験が実施されます。
なお、RHCEを受験するには前提資格として、RHCSAを取得しておく必要があります。
| 試験の学習ポイント | ・Red Hat 認定システム管理者として担当するすべてのタスクを実行する能力 ・Ansible のコアコンポーネントの理解 ・ロールと Ansible Content Collections の使用 ・Ansible 制御ノードのインストールと設定 ・Ansible 管理対象ノードの設定 ・Automation content navigator による Playbook の実行 ・Ansible の Play と Playbook の作成 ・Ansible モジュールによる標準的な RHCSA タスクの自動化 ・コンテンツの管理 |
| 試験名 | 受験料(税込) |
| LPIC-1(101試験/102試験) | 各16,500円 |
| LPIC-2(201試験/202試験) | 各16,500円 |
| LPIC-3 | 各16,500円 |
出典:Exam Pricing 2023 - Linux Professional Institute (LPI)
| 試験名 | 受験料(税込) |
| LinuCレベル1(101試験/102試験) | 各16,500円 |
| LinuCレベル2(201試験/202試験) | 各16,500円 |
| LinuCレベル3(300試験/303試験/304試験) | 各16,500円 |
| LinuCシステムアーキテクト(SA01試験/SA02試験) | 各27,500円 |
出典:LinuC(リナック)の受験ご案内|LPI-Japan
 LPIC試験とLinuC試験は、それぞれ取得までの有効期限が定められています。
LPIC試験とLinuC試験は、それぞれ取得までの有効期限が定められています。
どちらの試験も、レベルによっては2科目の合格が必要になり、順番を問わず期限内に合格しなければ資格取得になりません。期限を超えてしまうと、1つ目の試験の有意性がなくなってしまうため、注意が必要です。
ここでは、LPIC試験とLinuC試験を受ける際の注意点を紹介します。
LPIC試験のレベル1とレベル2においては、2科目に合格する必要があります。
たとえば、レベル1の101試験に合格した場合、その日から5年以内に102試験に合格しなければなりません。5年を超えてしまうと、101試験の合格が無効になり、再び101試験からやり直すことになります。
さらに、LPICが持つ有意性を保つためには、認定日から5年以内に同等以上のレベルを取得することが求められます。
出典:LPI認定資格 LPICレベル3とは (1/5)|HRzine
LinuC試験においても、1つ目の試験の合格から5年以内に2つ目を合格しなければなりません。
LPICと同様に、有意性を維持するためには認定日から5年以内に再認定、または上位のレベルを取得する必要があります。5年を超過してしまうと効力が失われるため、認定日を忘れないようにすることが重要です。
なおLinuC、LPICともに、同じ科目を再受験する際は、受験日から7日後でないとできません。
 Linuxの資格勉強をする方法としては、参考書や問題集を利用する方法、認定パートナー制度を利用する方法などが挙げられます。
Linuxの資格勉強をする方法としては、参考書や問題集を利用する方法、認定パートナー制度を利用する方法などが挙げられます。
ここでは最後に、Linuxの資格を取得するための学習方法を紹介していきます。
LPIC、LinuCには、資格取得のための認定パートナーが存在します。LinuCであればLPI-Japanアカデミック認定校制度、LPICであればトレーニングパートナーを利用することで、それぞれの資格勉強のサポートを受けることができます。
試験によっては過去問題集が出版されているケースもあるため、活用してみると良いでしょう。問題集であれば、実際に本番を想定した勉強ができるため、自分のレベルを把握しながら学習を進めることができるでしょう。
「徹底攻略LPI問題集 Level1」は、LPICレベル1の出題傾向を反映した505問の問題を収録した問題集です。前半では101試験の対策問題、後半では102試験の対策問題が収録されています。
また、巻末には総仕上げとして全505問の問題を掲載しており、問題一つひとつに解説もついているため、初心者でもしっかりと学習を進めることができるでしょう。
「Linux教科書 LPICレベル1 スピードマスター問題集」は、LPICレベル1に対応した対策問題集です。LPICレベル1の試験の最新バージョンであるVersion5.0に対応した認定テキストです。
全504問の問題が掲載されており、LPICレベル1の出題範囲を万遍なく学ぶことができます。


Linuxは多くの企業がサーバーOSとして採用しているため、資格を取得して上手く活用すれば、需要の高いエンジニアになることができます。
本記事で紹介した学習方法を参考にして、将来のキャリアプランに必要性の高いLinuxの資格を取得しましょう。フリーランスエンジニア向けの案件紹介サイトである「SEES」では、Linuxのスキルを持つエンジニアを求める高単価の案件を多数保有しています。
たくさんの選択肢の中から、自身のスキルレベルや理想の働き方が叶う案件を見つけることができるでしょう。
▼この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く