40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
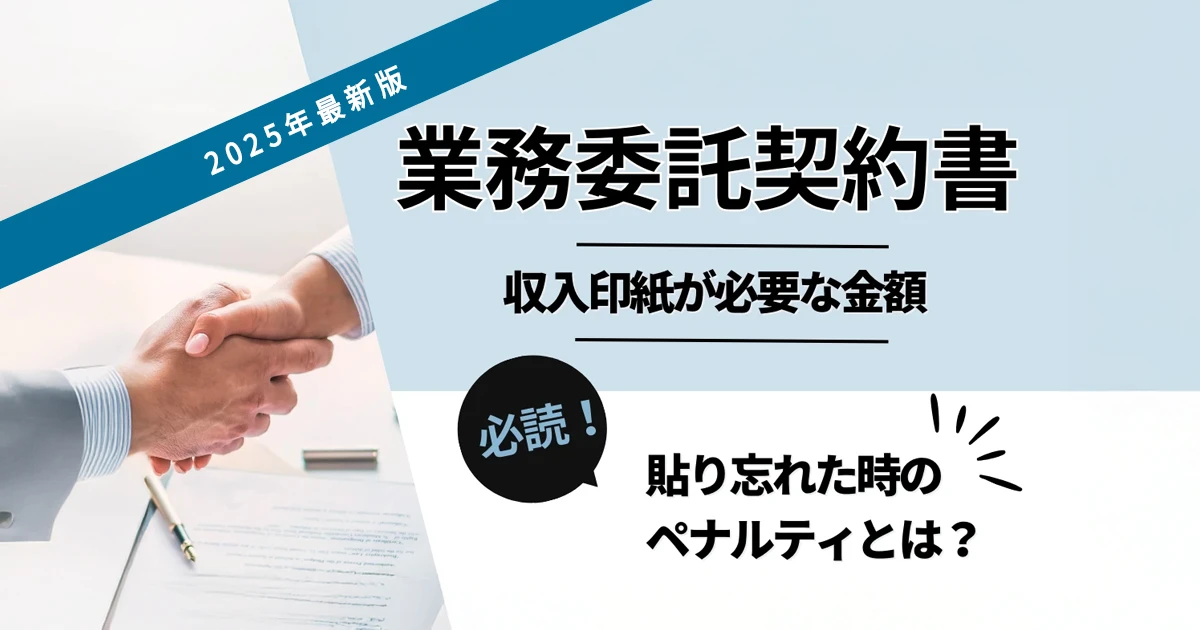
フリーランスが取り扱うことのある業務委託契約書ですが、収入印紙を貼り付けなければならないケースがあります。この記事では、収入印紙の貼り付けが必要な業務委託契約書の種類、印紙の金額について解説します。業務上、取り扱う機会のあるフリーランスの方は確認しておきましょう。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
業務委託契約書を作成する際に、収入印紙の貼付が必要な場合があります。収入印紙を貼付していなかったり、消印を忘れたりした場合、「過怠税(かたいぜい)」が発生する可能性があるので注意が必要です。
この記事では、業務委託契約の概要や業務委託契約書の収入印紙が必要なケース、具体的な金額について解説します。また、業務委託契約書に収入印紙を貼らなかった場合のペナルティもあわせて紹介します。
業務委託契約書を作成および利用する可能性のあるフリーランスの方は、リスクを回避し、ビジネスを円滑に進めるために確認しておきましょう。

そもそも、業務委託契約書とはどのような書面なのでしょうか。以下では、業務委託契約書について、基礎となる契約形態などの情報について説明します。
業務委託契約書は、業務を委託する側と受ける側が業務委託の条件を確認するための書面です。業務委託契約書に記載される内容には、業務内容や契約条件などの項目があります。
業務委託には「委任契約」と「請負」の2種類があるため、詳しく確認しておきましょう。
業務委託とは自社で対応できない業務を外部に委託することを指し、「委任(準委任)契約」と「請負契約」の2つに分かれます
委任契約は、法律行為を委託する際の契約です。委任契約では委託された行為の遂行に対して報酬が支払われることになり、結果や成果物に対する責任は発生しません。主に弁護士や行政書士、税理士などの士業への業務委託を行う際に利用します。
また、準委任契約は法律行為に該当しない事務処理が対象になり、委任契約と同じく業務の遂行に対して報酬が発生します。
一方、請負契約は委託された仕事を完成させることで報酬が支払われる契約です。請負契約の目的は契約内容の通りに成果物などを提供することであり、仕事の遂行が目的である委任や準委任とは性質が異なります。
出典:民法|e-Gov法令検索
 個人事業主やフリーランスとして活動していると、仕事をする際の契約が業務委託契約か雇用契約かの判断を下さなければならない場面に直面することもあるかもしれません。
個人事業主やフリーランスとして活動していると、仕事をする際の契約が業務委託契約か雇用契約かの判断を下さなければならない場面に直面することもあるかもしれません。
たとえば、新規の案件を獲得し、クライアント企業から業務委託契約と雇用契約の選択を迫られることや、自分がチームを組んで仕事を遂行する場合、依頼者と契約を交わす際に契約形態を判断する必要があります。
判断基準として下記の4つを意識すると、適切な選択ができます。
| 拒否権の有無 | 業務委託契約の場合は受託者に拒否権がありますが、雇用契約は、事業者からの業務の依頼を拒否できません。 |
| 指揮命令の有無 | 業務委託契約では受託者は事業者から「労働者の就労状況の管理を行う」指揮命令を受けません。しかし、雇用契約では事業者の指揮命令を受けます。 |
| 仕事の遂行方法の指示 | 業務委託契約は仕事の遂行方法を受託者が決めますが、雇用契約では事業者から直接指示を受けて遂行します。 |
| 労働時間や作業場所の指定 | 業務委託契約は労働時間や作業場所を受託者が決められますが、雇用契約では事業者から指定された場所・時間で仕事をします。 |
業務委託契約と雇用契約は異なります。
雇用契約は労働者が「労働に従事する」ことを約束し、使用者は労働に対して報酬を支払うものです。雇用契約を結ぶ場合、労働者は就業規則により定められた勤務時間や勤務場所で働くことが定められます。また、雇用契約には労働基準法などの労働法令が適用されます。
それに対して、業務委託契約は委託者と受託者間に労使関係がないため、契約で定める場合を除いて就業時間や勤務場所の拘束はありません。業務委託契約に適用される法令には、民法、独占禁止法、下請法といったものがあります。
出典:民法|e-Gov法令検索,経営Q&A~ 「With/After コロナに拡がる 新たな人材活用トレンド」 ~業務委託契約締結における留意点(雇用との違い)|日本政策金融公庫
受託者と委託者双方の合意があれば、口頭やメールで業務内容と条件を伝えて依頼した場合でも、業務委託契約は成立します。しかし、口頭やメールで契約した場合は、契約内容などの証拠が残りにくく、万が一問題があった際に大きなトラブルに発展する可能性があります。
これらの問題を避けることができる対策となるのが、業務委託契約締結の際に業務委託契約書を作成することです。書面にまとめることで契約内容が明確になるため、受託者と委託者の双方が安心して業務を遂行できるメリットがあります。
業務委託契約書を作成しなければ、委託者、受託者はさまざまなリスクを負うことになります。その一つが下請法違反のリスクです。下請け法とは、親事業者による下請事業者に対して、不当に代金を減額したり、不当な返品をしたり、支払を遅らせたりする行為を禁止する法律です。
仮に業務委託契約書を作成せずに契約をし、受託者に「契約した内容が下請け法に違反する」と訴えられた場合、契約書がなければ証拠が残らないため、どちらの意見が正しいのか判断できません。
トラブルが大きくなり、損害賠償が発生してしまう恐れもあるので、委託側・受託側どちらも自身を防衛するために、業務委託契約書を作成した方が良いでしょう。
業務委託契約書を作成せずに業務委託を行うと、偽装請負とみなされる恐れがあります。これも大きなリスクです。
偽装請負とは、契約上の契約形態が業務委託契約であるにも関わらず、委託元企業から労働者へ直接指示があるなど、実態が労働派遣であることを指します。
業務委託契約書がなければ、契約を証明することが難しくなるため、脱税目的の偽装請負というように疑われる可能性もあります。こうしたリスクを避けるためにも、業務委託契約書を作成し、契約内容を明記しておく必要があります。

業務委託契約書は通常、二部作成し、委託者と受託者が一部ずつを持つものです。この際、業務委託契約書に収入印紙を貼る必要がある場合があります。収入印紙を貼る理由は納税のためです。
業務委託契約書に印紙を貼る必要があるかどうかは、印紙税法で規定された2号文書・7号文書に該当するか否かで判断されます。2号文書と7号文書とはどのような書面なのか、確認してみましょう。
請負に関する契約書のことを、2号文書と言います。請負の業務委託契約書は2号文書に該当するため、印紙を貼り付けなければなりません。2号文書に課される税額は、契約金額によって異なります。
出典:第2号文書|国税庁,No.7102 請負に関する契約書|国税庁
「継続的取引の基本となる契約書」は7号文書にあたり、印紙の貼り付けが必要です。7号文書の要件は、特定の相手と継続的に生じる取引の基本となる契約書で、営業者間で交わされるものであることとされています。
7号文書には売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書、代理店契約書などが該当します。
ただし、契約書に記載された契約期間が3か月以内で、なおかつ更新の定めのないものは7号文書から除外されるため注意しましょう。
業務委託契約書を締結した後に契約内容を変更する場合、「覚書」や「念書」などの形式で契約内容を一部だけ修正する場合があります。
その時、覚書や念書にも印紙を貼らなければならないケースがあるため、注意が必要です。覚書や念書が課税文書にあたるかどうかは、「重要な事項」が含まれているかどうかによって決まります。
請負に関する契約書(2号文書)の「重要な事項」の一例としては、以下のような項目があります。
また、継続的取引の基本となる契約書(7号文書)の「重要な事項」は、以下の通りです。
2号文書・7号文書ともに、「覚書」や「念書」といった形で重要な事項を変更するための契約書を作成する際は、印紙の貼り付けが必要です。
出典:No.7127 契約内容を変更する文書|国税庁,令和6年6月 印紙税の手引き|国税庁
業務委託契約書の中には、2号文書と7号文書の両方に該当するものがあります。その場合、印紙は2号文書と7号文書どちらの規定に従えば良いのでしょうか。
文書の所属については、契約書に金額の記載があるかどうかという点が判断のポイントになります。契約書に金額の記載があれば、請負に関する契約書に該当するため2号文書と判断されます。
反対に、契約書に金額の記載がなければ継続的取引の基本となる契約書に該当し、7号文書に分類されます。
 業務委託契約書に貼る印紙の金額は、2号文書と7号文書でそれぞれ定められています。ここでは、課税対象となる文書に貼り付ける具体的な印紙税額について確認しましょう。
業務委託契約書に貼る印紙の金額は、2号文書と7号文書でそれぞれ定められています。ここでは、課税対象となる文書に貼り付ける具体的な印紙税額について確認しましょう。
第2号文書に貼り付ける印紙の金額は、契約書に記載された契約金額に応じて設定されています。2号文書の契約金額に対する印紙税額の一例は、次の通りです。
【金額一覧表】| 契約金額 | 印紙税額 |
| 1万円未満のもの | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 ※契約金の記載がない場合 | 200円 |
| 100万円超え 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超え 300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超え 500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超え 1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超え 5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超え 1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超え 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超え 10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超え 50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超え | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
7号文書の場合は2号文書のように契約金額で印紙の額が決まるのではなく、契約金額に関わらず一律で印紙税額が決まっています。7号文書に貼り付ける印紙の金額は、1通につき4000円です。
【金額一覧表】
| 契約金額 | 印紙税額 |
| 金額の定めによらない | 4,000円 |
ただし、契約期間が3ヶ月以内であり、更新の定めのない契約書の場合は除外(非課税)となります。
 第2号文書または第7号文書にあたる業務委託契約書には、収入印紙の貼付が必要となります。しかし、確認不足や誤認識によって、収入印紙を貼るべき業務委託契約書に貼付しなかった場合、ペナルティが発生します。
第2号文書または第7号文書にあたる業務委託契約書には、収入印紙の貼付が必要となります。しかし、確認不足や誤認識によって、収入印紙を貼るべき業務委託契約書に貼付しなかった場合、ペナルティが発生します。
課税文書の作成時に印紙を貼らなかった場合、過怠税と呼ばれる税が追加で課せられます。本来納めるべき印紙税の金額に加え、その2倍相当の金額が過怠税として課されるため、元々の印紙税額の3倍に相当する額を納税しなくてはなりません。
たとえば、7号文書にあたる業務委託契約書に収入印紙を貼付しなかった場合、本来納めるべき4,000円に加え、8,000円の過怠税が課せられ、合計12,000円を納めることになります。
また、4,000円の収入印紙が必要な書類に対して、200円の収入印紙を貼付した場合、過怠税は差額で計算されるため、差額の3,800円に加え、7,600円(合計11,400円)を徴収されます。
7号文書に該当する業務委託契約書であれば一律4,000円ですが、2号文書に該当する場合は納税額が高額になる場合もあります。2号文書では契約金額に応じて収入印紙の金額が高くなるため、過怠税の金額もそれに応じて高くなるためです。
収入印紙を貼付し忘れた場合、元々の印紙税額の3倍に相当する額を納めなければならないと前述しました。しかし、作成者が自ら所轄税務署長に対して印紙税の未納付を申し出た場合は、上記とは別の対応が取られることもあります。
その申し出が、印紙税についての調査があったことにより3倍の過怠税が課されると予知して行われたものでないことが認められれば、本来納めるべき印紙税の金額+その10%相当額(つまり元々の印紙税額の1.1倍)となります。
不注意によって収入印紙の貼付を忘れてしまった場合でも、業務委託契約書が無効にはならず、効力は変わりません。
業務委託契約書の内容に影響を与えることはないので、そういった心配は不要です。なお、印紙税法は刑法ではないので、刑事責任を問われることもありません。
収入印紙を貼付する際には、消印(けしいん)または割印を押すか署名が必要となります。消印なしで業務委託契約書に収入印紙を貼り付けただけでは、印紙税を納付したとみなされず、印紙不消印過怠税が発生する恐れがあります。印紙がはがされた場合に別の書面での利用を防ぐことが消印の目的です。
消印なしの収入印紙を指摘された場合、過怠税は収入印紙と同額ですので、収入印紙と消印はセットだと捉えて、忘れずに対応しましょう。
出典:印紙の消印の方法|国税庁
 ここでは、業務委託契約書への収入印紙の正しい貼り方について解説します。
ここでは、業務委託契約書への収入印紙の正しい貼り方について解説します。
収入印紙の貼り方と併せて、消印の押し方も紹介するので、両方のポイントをしっかり押さえたうえで対応を進めてください。
収入印紙を貼る場所や貼り方については法律上の決まりはありません。そのため、受託者と委託者双方の合意が取れていれば、どこに貼付しても構いません。
一般的な慣例では、契約書の左上に貼るとされているため、特に理由がなければ左上の空きスペースに貼り付けましょう。収入印紙の貼付欄が設けられている書類の場合には貼付欄に貼り付けます。
課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合は、印紙と書面にかかるように消印(割印)を押す必要があります。
消印の目的は印紙の再利用を防止することであるため、使用する印鑑はゴム印のようなもので問題ありません。消印は、契約書と収入印紙の縁(彩紋)にまたがるように、かつ消印の印影がわかるように押印しましょう。
また、消印を押す人は文書の作成者に限らず、代理人や使用人、従業員が代わりに押しても良いとされています。
印影ではなく署名も有効とされています。
出典:印紙の消印の方法|国税庁,No.7120 契約書の写し、副本、謄本等|国税庁

ここでは、業務委託契約書と収入印紙にまつわる押さえておくべきポイントを3つ紹介します。
収入印紙の負担に関しては、印紙税法上では課税文書を作成した人に対して印紙税の納税義務が課せられます。
業務委託契約の場合は、2人あるいは2社以上の当事者が課税文書を作成・保有するため、当事者双方が1通ずつ負担するのが一般的です。ただし、契約書の原本は1通のみでコピーを用いて保管するケースでは、原本を保管する側が収入印紙を負担するという場合もあります。
契約書を作成する前に当事者同士でどちらが負担するかを確認し、収入印紙に関するトラブルを未然に防ぎましょう。
平成十七年の参議院での政府答弁や平成二十年の福岡国税局による見解によって、電子契約の場合に収入印紙は不要であることが確認されています。このとき電子契約のように「電磁的記録を作成した契約行為について、印紙税の課税対象とならない」ということが明らかになりました。
電子契約を締結する行為は、「課税文書の作成」に該当しないため、印紙税は課税されないということにつながります。
ただし、法令上「電子契約は非課税」といったハッキリとした文言はみられず、その後に一般の利用者が広がったことから見解が変わらないとは限りません。電子契約にて業務委託契約を結ぶ場合には、直近の各種事例などを調べておくことをおすすめします。
出典:請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について|国税庁,印紙税に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院
覚書とは、業務委託契約書の内容を変更した場合にその変更事項を補足した文書のことを指します。この覚書にも収入印紙の貼付が必要になるケースがあるので注意が必要です。
書類に契約内容を変更する前後の金額が記載されている場合は、差額分の収入印紙を貼り付ける必要があります。一方で金額が記載されていない場合は、変更後の契約金額を基準とした収入印紙を貼り付けましょう。
 印紙の貼り付けが不要な書面は、非課税文書や不課税文書です。非課税文書とは、課税文書にあたる20種類の文書で以下の条件に該当するものを指します。
印紙の貼り付けが不要な書面は、非課税文書や不課税文書です。非課税文書とは、課税文書にあたる20種類の文書で以下の条件に該当するものを指します。
また、不課税文書は課税対象外の文書のことを指し、課税物件表の物件名欄に記載されていない文書は不課税文書となります。課税物件表については、出典のURLよりご確認ください。
出典:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁,課税対象となる文書の範囲|国税庁,[参考]|国税庁

業務委託契約書の収入印紙に関するよくある質問に対して、Q&A形式で回答します。疑問を持たれた方は、まずは下記の質問から確認して、解決にお役立てください。
7号文書に該当する業務委託契約書の収入印紙の金額は、一律4,000円です。2号文書にあたる書類かつ、契約金額が1万円を超えて100万円以下の業務委託契約書を作成する場合は、200円の収入印紙が必要となります。2号文書について、契約金額がより大きい場合には、収入印紙の額も高くなることが定められています。
このように業務委託契約書の内容や、契約金額などに応じて、収入印紙の金額は異なります。
請負契約にあたる業務委託契約を締結する場合は、収入印紙の貼付が必要になります。
委任契約、あるいは請負契約の契約金額が1万円未満の場合、収入印紙は必要ありません。
業務委託契約書に収入印紙は貼らなくていい場合と、貼付が必要な場合があります。その違いは、契約内容と契約金額によって異なります。
委任契約に該当する業務委託契約書の場合は、収入印紙が不要です。一方、請負契約の場合は、収入印紙の貼付が原則必要ですが、契約金額が1万円以下であれば、非課税となるため、収入印紙は不要になります。
業務委託契約書は、契約を締結する当事者の人数分の契約書を作成します。そのため、委託者と受託者双方が1通ずつ収入印紙の金額を負担するのが一般的だといえます。
業務委託契約書が継続的取引の基本となる7号文書にあたる場合は、収入印紙の金額が一律4,000円となります。
ただし、2号文書に該当する金額記載なしの業務委託契約書の場合、収入印紙の金額は200円です。
印紙税法の課税文書にあたる業務委託契約書に収入印紙を貼らなかった場合、過怠税が徴収されます。過怠税は、本来の納税額の2倍徴収されるため、本来の印紙税額とあわせて3倍の金額を納めることになります。
 業務委託契約書には、契約内容によって課税対象になる場合があります。契約内容により「2号文書」または「7号文書」に該当する場合は収入印紙を貼ることが必須です。業務委託契約を結ぶ場合は、契約書がどちらかに該当するかを確認しましょう。2号文書の場合は、契約金額に応じて印紙税額が異なりますが、7号文書は一律4,000円です。
業務委託契約書には、契約内容によって課税対象になる場合があります。契約内容により「2号文書」または「7号文書」に該当する場合は収入印紙を貼ることが必須です。業務委託契約を結ぶ場合は、契約書がどちらかに該当するかを確認しましょう。2号文書の場合は、契約金額に応じて印紙税額が異なりますが、7号文書は一律4,000円です。
なお、収入印紙を貼ったら消印を押すか署名をする必要があります。いずれかがされていない収入印紙は、印紙不消印過怠税が課せられるため、文書と収入印紙の模様部分にまたがるようにハッキリと消印を押さなければなりません。
業務委託契約書を作成する際には、収入印紙の「貼付の有無」「金額」「消印」の3点を押さえたうえで適切な対応をしましょう。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く