40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
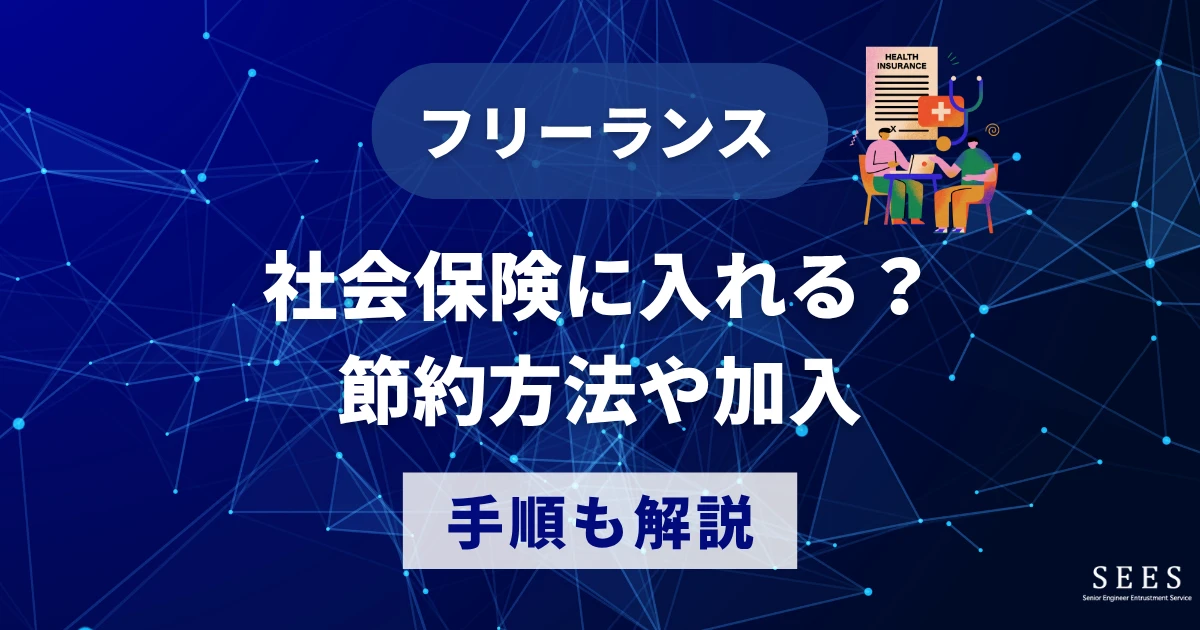
社会保険には、医療費の負担を減らす公的医療保険や老後の資金を補填する公的年金制度などがあります。フリーランスも社会保険に加入しなければ、将来的なリスクが発生しかねません。本記事では、フリーランスが加入できる社会保険や保険料の節約方法を解説します。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
社会保険とは病気やけが、高齢化といった誰にでも起こる可能性が高いリスクに対して、社会全体で備える制度です。具体的には、医療費の負担額を減らす「公的医療保険」や、老後の資金を補填するための「公的年金制度」などがあります。
会社員の場合は、社会保険の手続きや支払いを企業が代行しておこないます。
一方で、フリーランスとして独立した後は自身で社会保険の手続き・支払いをおこなわなければなりません。もし、国民健康保険や国民年金への切り替えを怠ってしまうと、病気の際に医療費を自己負担しなければならず、老後の費用も用意できないかもしれません。
このような事態を避けるためにも、フリーランスが加入する社会保険について理解を深め、然るべき対応をすることが大切です。
本記事では、フリーランスは社会保険に加入できるのかについて、保険料を節約する方法や加入の手順もあわせて解説します。

広義的な意味の社会保険とは、公的医療保険・介護保険・公的年金制度から構成される社会保険と、雇用保険・労災保険を束ねた労働保険を総称したものです。社会保険の制度を整えることで、高額な医療費や老後の資金、失業といった人生のリスクを、社会全体で支える目的があります。
社会保険は種類によって保障内容が異なるため、必要なときに利用するためにも制度への理解が欠かせません。
ここでは、社会保険の種類について解説します。
| 社会保険(広義) | 社会保険(狭義) | 公的医療保険 |
| 介護保険 | ||
| 公的年金制度 | ||
| 労働保険 | 雇用保険 | |
| 労災保険 |
公的医療保険は、加入者が病気やけがをした際に、原則として3割の自己負担で診療を受けられる制度です。市区町村が運営する国民健康保険と企業が運営する組合健保、全国健康保険協会が運営する協会けんぽなどがあります。
公的医療保険の保険料は被保険者の収入をもとに計算されます。会社員の場合は基本的に企業と折半で支払い、フリーランスの場合は全額が自己負担です。
介護保険は要介護認定を受けたときに、介護サービスを1〜3割負担で利用できる制度です。具体的には、自宅で暮らす要介護者の生活支援やリハビリ、入浴などのサポートを受けられます。
保険料は40歳以上になった誕生月から発生し、毎月、保険料としてまとめて徴収されます。会社員の場合は会社と折半で支払い、フリーランスの場合は全額が自己負担です。
公的年金制度は働いている世代が支払った保険料を年金給付に充てて、高齢者の生活をサポートする制度です。全国民が共通して加入しなければならない国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金にわかれています。
自身が年金を支払っていることで、65歳を迎えると老齢基礎年金の受給が可能です。
保険料は、国民年金が年間を通して一律となっており、厚生年金は被保険者の収入に対して、18.3%をかけて計算されます。負担割合は、会社員が会社と折半して5割であるのに対して、フリーランスは全額が自己負担です。
雇用保険は労働者が失業したり、育児休業を取得したりした際に、所得を補償し再就職を支援する制度です。具体的には、求職者が次の仕事を見つけるまでの生活を支える失業手当や、育児休業を取得した際には育児休業給付などが支給されます。
保険料は、厚生労働省が定める事業ごとの保険料率をもとに計算されており、会社と折半して支払っています。
なお、雇用保険は、雇用されている労働者のための制度のため、フリーランスは加入できません。
労災保険は、業務中や通勤途中に発生した事故や病気に対して治療費・休業補償・障害補償などをおこなう制度です。具体的には、通勤時の事故でけがをした際の療養費や、それが原因で就業できない場合の賃金の一部が補償されます。
保険料は事業主が全額負担するため、従業員の支払いはありません。
労災保険は雇用されている人のための制度のため、原則としてフリーランスは対象外です。ただし、2024年11月1日以降は、企業から業務委託を受けているフリーランスについては、任意で労災保険に加入できます。
なお、その際の保険料はフリーランスが負担しなければなりません。
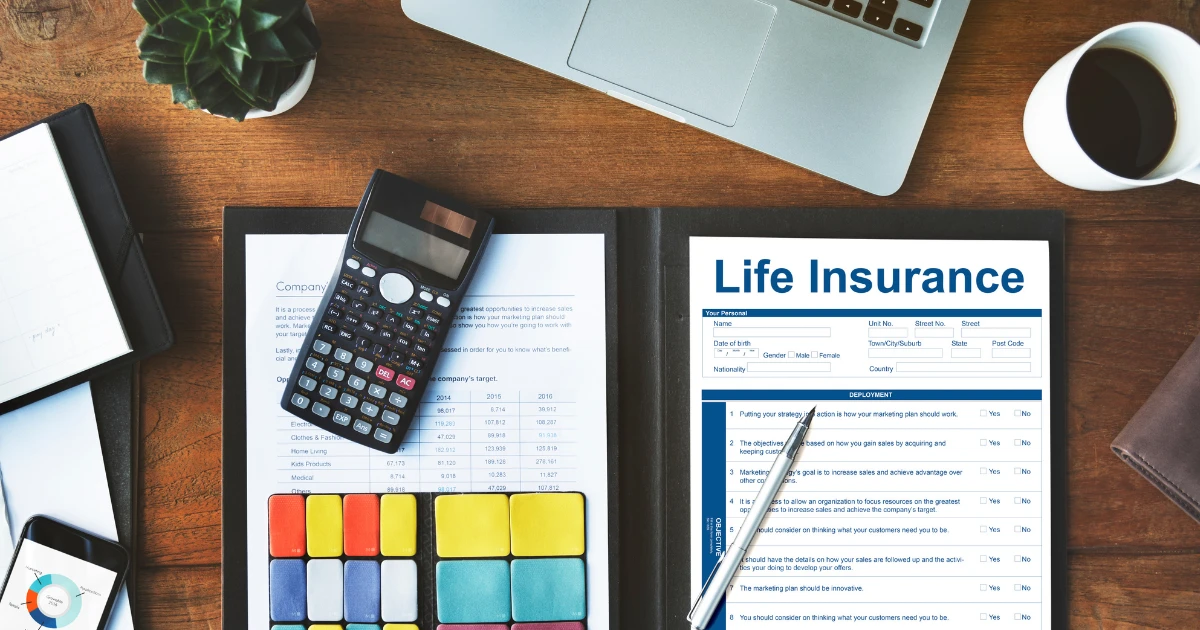
フリーランスが加入しなければならない保険は、公的医療保険・介護保険・公的年金制度の3つです。
日本はすべての国民が公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」となっています。このことから、年齢や職種などに関係なく、公的医療保険に加入する義務があります。
また、介護保険に関しても、社会全体で要介護者を支える目的として、40〜65歳の国民は加入しなければなりません。
さらに、公的年金制度は20〜60歳の方の加入が義務付けられています。
これらの社会保険を未納のまま放置すると、社会保障が受けられず、医療費の全額自己負担や、将来受け取る年金が減額されるおそれがあります。場合によっては、延滞金の支払いを求められたり、資産の差押さえが発生するリスクもあります。
事業を開始してから未払いによって不利益が生じないよう、独立したタイミングで確実に手続きをおこないましょう。
社会保険は働き方によって加入する内容が異なり、支払う保険料や給付内容に大きな差が生じます。具体的には、フリーランスは国民健康保険と国民年金を全額自己負担するものの、会社員や公務員は保険料を雇用先と折半します。
自身の状況にあわせて社会保険に加入しなければ、保険料を二重で支払ったり、保障が途切れたりして不要な費用が発生する可能性があるでしょう。
ここからは、フリーランスと会社員、公務員の社会保険上の違いを解説します。
フリーランスは、公的医療保険・介護保険・国民年金に加入する義務があります。保険料は全額自己負担となり、金額は前年の課税所得で決定します。
加入する公的医療保険は国民健康保険であり、扶養の概念はありません。家族も個別に保険料を納めなければならず、所得が急増した場合は、翌年度の社会保険料が跳ね上がるケースもあります。
収入の変動が激しい年は社会保険の免除や猶予などの対策を活用することで負担をコントロールできますが、申請を怠ると家計を圧迫するため計画的な対策が重要です。
会社員は公的医療保険・介護保険・公的年金制度・雇用保険・労災保険の5つに加入します。労災保険の保険料は会社が全額負担し、それ以外は折半のため、フリーランスよりも支払う金額は少ない傾向があります。
会社員の社会保険は給付内容も手厚く、傷病手当金や失業給付など独立後には利用できない補償も少なくありません。ただし、会社を退職した翌日から社会保険を離脱する必要があるため、タイミング次第では独立後の社会保険料と二重で支払うケースもあります。
公務員は公的医療保険・介護保険・公的年金制度に加入する義務があります。フリーランスと異なる点は、公的年金制度では国民年金以外にも、厚生年金へ加入する点です。
公務員は共済組合を通じて社会保険に加入しており、保険料は各共済組合が定める料率で計算された金額を支払います。
また、公務員は雇用保険や労災保険には加入できません。業務災害が発生した際は、労災保険の代わりに公務員災害補償制度が適用されます。

退職してからフリーランスとして独立する際は、保険証の切り替え期限や保険料が発生するタイミングを勘違いしていることで、保険料の二重払いや未納期間の発生などのトラブルにつながります。
とくに、公的医療保険は日割り計算がなく、月末に加入しても同月分の保険料が全額請求されるため注意が必要です。
不要な費用を発生させないためにも、社会保険の切り替えや発生するタイミングについての理解を深めましょう。
ここでは、独立後のトラブルを避けるための社会保険のポイントを解説します。
今のうちにチェックしておきましょう!
フリーランスとして独立する際は、退職日の翌日から14日以内に、国民健康保険と国民年金の加入手続きをおこなわなければなりません。
期限を過ぎた場合は無保険状態となり、病院にかかった際は医療費を全額請求されたり、将来的に年金の受給資格期間が不足して、受け取れる年金額が減るリスクがあります。
手続きには会社から発行される資格喪失証明書が必要になるため、受け取ってから役所へ足を運びましょう。
社会保険料は月単位で徴収されるため、月末に加入しても日割り計算にはならず、1か月分の満額が徴収されます。
もし、月の途中で退職して国民健康保険に切り替えた場合は、会社で支払う分の保険料とあわせて、国民健康保険料を二重に支払う必要があります。
このことから、なるべく社会保険料を増やさないためにも、月の最終日に退職し、翌月1日より新しい社会保険に加入できるよう切り替えがおすすめです。
40歳を迎えると、介護保険料が医療保険料とあわせて徴収されます。
前年の所得が大幅に増えていると、国民健康保険料だけでなく介護保険料も跳ね上がるため、社会保険の負担が大きくなります。
社会保険の負担が大きくなると想定されるのであれば、分割納付や減免制度を活用して、一度に支払う社会保険料を減らしましょう。

フリーランスが社会保険料を抑える方法は、正しく経費を計上して課税所得を少なくしたり、加入する健康保険を変更したりといった方法があります。また、青色申告の特別控除や法人化による給与所得控除、国保の減免制度など、活用できる節税策は多岐にわたります。
実質の負担を減らしながら必要な保障を維持する方法を把握しておけば、収入が変動する年でもキャッシュフローを安定させやすくなるでしょう。
ここでは、フリーランスが社会保険料を節約する方法を解説します。
フリーランスの方、個人事業主の方は必見です!
青色申告では、所得金額から最大65万円が控除される控除が受けられます。これは「青色申告特別控除」と呼ばれ、この制度を利用することで課税所得が減り、国民健康保険料の削減につながります。
青色申告は売上規模が大きいほど節税メリットが高まるため、フリーランスであれば早めに青色申告へ切り替えることがおすすめです。
ただし、青色申告をおこなう場合は、白色申告の単式簿記とは異なり、複式簿記で帳簿を記載しなければなりません。事務作業の手続きは煩雑になるため、会計ソフトを導入するといった対策も必要になります。
フリーランスは、事業に関係する支出を経費として計上できます。経費が増えれば課税所得を少なくできるため、翌年に支払う社会保険料の負担軽減が可能です。
ただ、事業と無関係な支出を経費として計上すると、申告に不備があったと判断され、加算税が追徴される可能性があります。税務調査が入れば虚偽の申告はバレてしまうため、正しい経費計上を意識しましょう。
フリーランスは法人化することで、国民健康保険だけでなく、全国健康保険協会に加入する選択肢が増えます。あわせて厚生年金にも加入できるため、確定申告時に正しく社会保険料の控除を申請すれば、課税所得を少なくできます。
なお、フリーランスが法人化した場合は、自身の収入を役員報酬として設定でき、法人全体の収益は圧縮が可能です。また、自身の社会保険料は役員報酬をもとに計算することによって、保険料の節約につながります。
国民健康保険組合とは国民健康保険の一種で、同じ事業の従事者で組織されている健康保険組合団体です。医師や薬剤師、弁護士など、さまざまな業界の国民健康保険組合があります。
国民健康保険組合に加入することで、収入にかかわらず、健康保険料が一定になります。前年度の収入によって社会保険料が増加しないため、収入の変動が大きいフリーランスでも不安を減らせるでしょう。
フリーランスは、怪我や病気などで働けない期間が長引けば、収入がなくなるケースもあります。
収入の減少により社会保険の支払いが難しい場合は、住んでいる地域の役所や年金事務所に問い合わせることで、国民健康保険の減免や国民年金の免除を受けられる可能性があります。
ただし、申請しても免除が確実に受けられるとは限らないため、必ず通ると思わず、可能な限り保険料を準備しましょう。

フリーランスは企業を退職した場合、国民健康保険と国民年金の加入手続きを自身でおこなわなければなりません。
会社が手続きした社会保険は退職日の翌日から失効するため、切り替えなければ、無保険期間中の医療費を自己負担しなければいけない、受給できる年金の金額が減少するなどのリスクがあります。
社会保険の加入手続きには、退職日の翌日から14日以内と期限も設けられているため、会社を退職し、必要な書類が手元に届いた場合は、なるべく早めに手続きをおこないましょう。
ここからは、フリーランスが社会保険に加入する手順を解説します。
国民健康保険へ加入する際は、住民票のある市区町村の窓口に資格喪失証明書と本人確認書類を持参しましょう。
手続きの際に必要な持ち物は、以下のとおりです。
国民健康保険の加入手続きは、以下の流れでおこないます。
手続きが遅れた場合は、未加入期間分の保険料を一括請求される可能性があるため、期限に遅れないようにしましょう。
なお、国民健康保険は住んでいる地域によって加入の流れや持ち物が異なるため、手続き前に各自治体のホームページを確認しておくことで漏れを防げます。
国民年金への加入手続きは、市区町村の窓口で手続きが可能です。
国民年金の手続きの際には、以下の書類からどちらかを持参しましょう。
国民年金の加入手続きは、以下の流れでおこないます。
国民年金は退職日の翌日から被保険者となるため、切り替えをしなければ未納期間が発生します。未納の期間が長くなれば、将来的に受け取れる年金の減少や、延滞金が発生する可能性が考えられるため、なるべく早めに手続きしましょう。
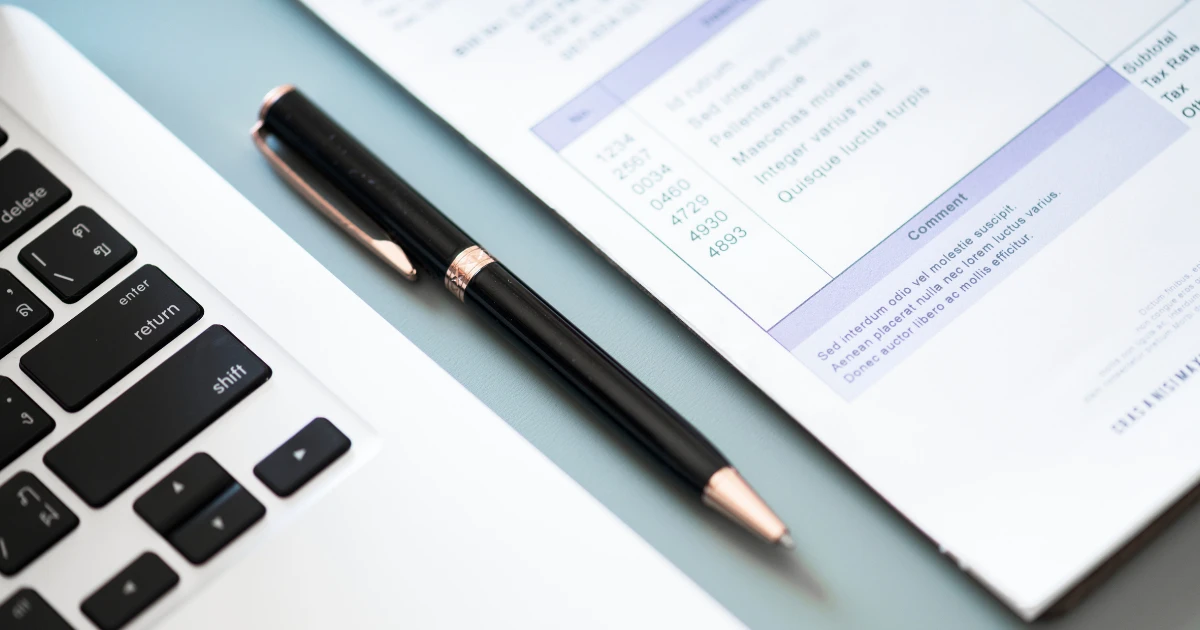
本記事では、フリーランスは社会保険に加入できるのかについて、保険料を節約する方法や加入の手順もあわせて解説しました。
会社員時代は社会保険の手続きや支払いを会社が代行してくれるものの、フリーランスになってからは自身で対応しなければなりません。期日内に手続きや支払いをおこなわなければ、延滞金の発生や医療費を全額自己負担しなければならないなどのトラブルにつながります。
社会保険料は必ず支払う費用だからこそ、フリーランスは正しい経費の計上や法人化といった対策で節約することが大切です。
社会保険についての知識を学んでおくことで、フリーランスとして働き始めてからも、手続きや支払いのミスによって、余計な費用が発生する心配がなくなります。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く