40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
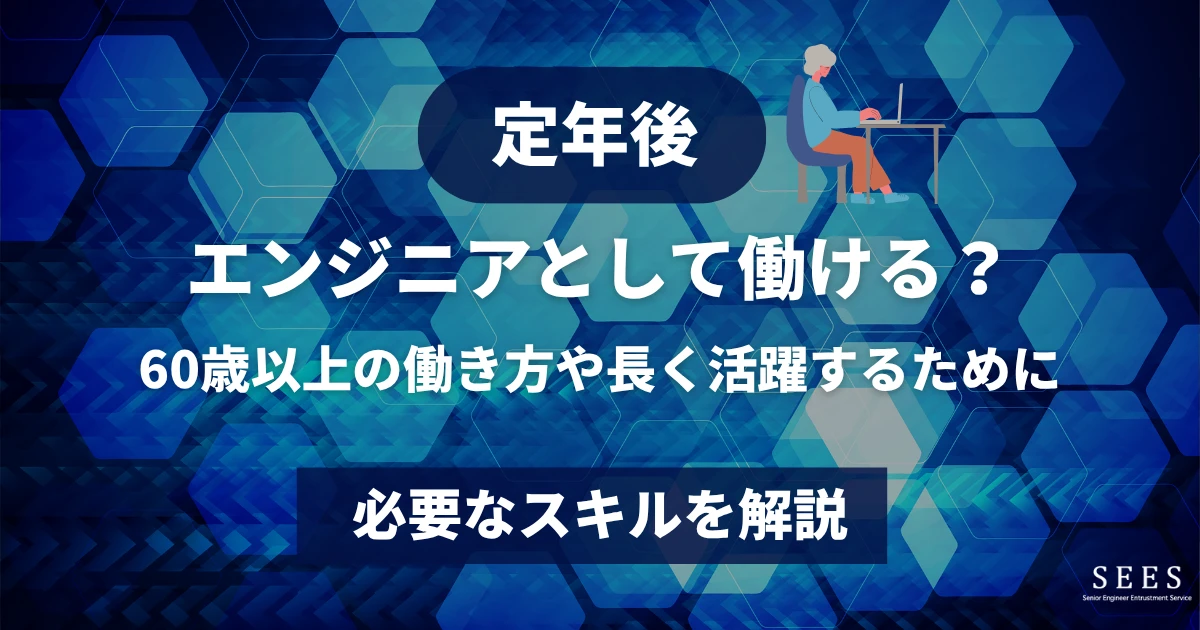
近年は、定年後もエンジニアとして活動する方が増えているものの、応募先の少なさや年齢などのさまざまな問題があり、一筋縄ではいかないのが現状です。本記事では、定年後のエンジニアについて、働き方や備えておくべきスキルを交えつつ解説します。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
50代に差し掛かると、「定年後の働き方」について考え始める方も少なくありません。近年は定年をむかえても働き続ける方が増えており、エンジニアのなかにも60代で活躍しているケースが多く見られます。
一方で、定年まで一線で活躍していたエンジニアであっても、定年後も同様に働き続けるのは難しいのが現状です。とくに、「年齢」に関係する定年後特有の壁を理解していないと、理想のキャリアを築きにくいでしょう。
定年後もエンジニアとして働く意志がある場合は、60代の働き方や必要な準備をおさえておくことが重要です。
本記事では、定年後のエンジニアについて、働き方や備えておくべきスキルを交えつつ解説します。

現在、エンジニアとして働いている方のなかには、20〜50代の現役世代に加えて定年をむかえた60代の方も活躍しているケースがあります。
60代は若い世代にはない「経験」を活かし、育成やマネジメント業務など、プロジェクトの中核を担う存在として重宝されています。
ただし、20〜50代と比べると求人や案件の数は限られており、希望通りの環境で働き続けるのは簡単ではありません。そのため、定年後もエンジニアとして活動を続けたい場合は、早めに準備を進め、スキルの再確認や磨き直しを意識しておくことが重要です。

近年は、年金への不安や物価高などを背景に、エンジニアをはじめ、さまざまな職業で定年後も働き続ける方が多い傾向にあります。
一方で、60代になると求人数が減少し、応募できる求人や案件を見つけにくいのが現状です。そのため、定年前と同様の働き方ができない可能性も十分にあります。
いざ退職したときに次の働き先をスムーズに見つけるためにも、事前に定年後の選択肢を確認しておくことが重要です。
ここでは、定年後のエンジニアの働き方について、以下4点を解説します。
近年は、定年をむかえたあとも、再雇用制度を活用して同じ企業で働き続けるケースが増えています。企業側でも高齢者雇用に対応するため、嘱託社員や契約社員としての再雇用枠を用意しているケースは少なくありません。
雇用条件が変わる場合もあるものの、慣れた職場で業務を継続できるため、心理的な負担が少なく安心して働けるのが大きなメリットです。
とくに、職場環境や人間関係に不安がない方にとっては、スムーズに定年後の働き方へ移行しやすい選択肢といえます。
環境を変えてエンジニアとして働きたい場合は、別の企業へ転職するのも1つの選択肢です。IT分野は慢性的な人手不足が続いており、60代でも即戦力として歓迎されるケースがあります。
一方で、年齢が上がるにつれて募集枠は限られ、競争も激しくなるため、十分な準備が欠かせません。
大規模プロジェクトの実績やマネジメント経験などは、若手にない強みとして評価されやすく、自分の武器を明確にすることが転職成功の鍵となります。
60代になると全体的に求人数が減少し、エンジニア職で絞るとさらに選択肢が狭まります。こうした状況では、正社員だけではなく、契約社員やパート・アルバイトといった非正規雇用も現実的な選択肢です。
正社員に比べて条件面は劣るものの、求人数は比較的多く、自分に合った働き方を見つけやすい傾向があります。
また、勤務時間を柔軟に調整しやすいため、フルタイムが難しい方でも得意分野を活かしながらスポットで働くことが可能です。
再就職先がなかなか見つからない場合は、フリーランスとして個人で働くのも1つの手です。業務委託案件の多くは即戦力を求めているため、実務経験やスキルがあれば60代でも採用される可能性があります。
また、請け負う案件数や単価によっては、正社員時代よりも年収が高くなることもめずらしくありません。
リスクはあるものの、時間や場所に縛られずに働けるため、無理せず働きたい方にもおすすめです。

定年後もエンジニアとして働く際は、豊富な経験や知見を活かせる一方で、年齢による制約がリスクとして見られる場面もあります。とくに、求人の選択肢や働き方の自由度は現役時代よりも狭まりやすく、定年後のエンジニアならではの注意点も存在します。
エンジニアとして活動を長く継続するためにも、事前にリスクを確認したうえで、対応策を考えることが重要です。
ここでは、定年後もエンジニアとして活動する際におさえておくべきリスクについて、以下4点を解説します。
年齢が上がるにつれて、全体的な求人数が減少する傾向があります。実際に、企業やプロジェクトのなかには、長期間の活躍を前提に人材を採用することが多く、60代は選考の対象外となるケースも少なくありません。
また、エンジニア職や分野ごとに細かく条件を加えると、応募できる求人や案件の母数が少なくなるため、該当する案件はごくわずかになります。
定年後に探しはじめても、希望する働き方が見つからない可能性が高いため、できるだけ早い段階から情報収集や準備を進めておくことが重要です。
60代で応募できる求人は、年収や勤務時間などの条件が現役時代よりも厳しくなる傾向があります。実際に、年収は40代後半から50代でピークに達し、60代以降は減少するケースも少なくありません。
また、60代になると求人数が減少するため、選択肢を増やすためにも希望条件はある程度緩めておくことが重要です。
それでも好条件を望む場合は、業務委託案件であれば年齢関係なく応募できるケースが多く、なおかつ高収入を目指しやすいでしょう。
SEESではシニアエンジニア開発案件も豊富!
定年後の働き方で注意しなければいけないポイントの1つが、年齢による衰えです。年齢とともに体力や集中力が低下しやすく、たとえ定年前と同じ作業であっても、自分が思うように働けない可能性があります。
とくに、フリーランスとして働く場合は注意が必要で、病気や怪我などで稼働ができないと直接収入に影響します。
長くエンジニアとして活動するためにも、定年後に「無理なく働き続けられるか」という点に注目し、求人や案件を探すことが大切です。
エンジニア業界は技術の進化が早いため、定年後も継続的に情報を追い続けることが求められます。ただし、加齢による体力や集中力の低下で、現役時代のように積極的に学習に取り組めないケースもめずらしくありません。
無理をして体調を崩しては本末転倒のため、自分のペースで学べる環境づくりが大切です。
余力のある状態で時間を確保するためにも、リモートワークの導入や働く時間を減らすなどの工夫をすることが重要です。
 >
>40〜50代で第一線のエンジニアとして活躍していても、定年後も同じ働き方ができるとは限りません。企業側は長期的に貢献できる若手人材を求める傾向があり、これまでと同じ条件では選考を通過しにくくなる場合があります。
そのため、定年前からキャリアや働き方を見直し、変化に備えて準備を進めておくことが重要です。
ここでは、定年後もエンジニアとして活躍するために取るべき行動について、以下5点を解説します。
60代になると、転職や独立のいずれにおいても選考の通過率が下がる傾向にあります。なかには、年齢が原因で選考の対象外となるケースもあり、応募できる求人や案件が限定的になってくるのが現状です。
こうした状況を避けるためには、できるだけ早い段階から行動を起こすことが重要です。たとえば、50代のうちに60代以降も雇ってもらえる企業に転職したり独立したりするのも良いでしょう。
早めに動くほど選択肢が広がり、希望の働き方を実現しやすくなります。
定年後もエンジニアとして活躍するためには、最新技術の動向を継続的に学び続ける姿勢が欠かせません。IT分野は技術が進化するスピードが早く、情報収集やスキルアップを怠ると、知識がすぐに古くなってしまいます。
このような状況に陥ると、周りのエンジニアとの差が開き、応募できる求人や案件の幅も狭まります。
とくに、60代は求人の選択肢自体が少ないため、限られたチャンスをつかむためには学びを継続する意識が今まで以上に重要です。
定年後もエンジニアとして働くためには、柔軟な働き方を受け入れる姿勢が欠かせません。とくに、60代になると応募できる求人数が減少し、勤務形態や報酬などの条件が希望通りにならないことも多いため、条件を緩めて探すことも大切です。
たとえば、正社員だけではなく非正規雇用も検討したり、時短勤務を受け入れたりするのも1つの選択肢といえます。
はじめから条件を絞りすぎず、応募可能な選択肢のなかから自分に合った求人や案件を見極めることで、定年後も無理なく働き続ける道が見つかりやすくなります。
定年後もエンジニアとして働くためには、若手にはない経験を活かせる立ち位置を意識することが重要です。
たとえば、長年の実務経験をもとに若手を指導したり、プロジェクト全体を統括するマネジメント業務を担ったりすることで、60代の強みを発揮しやすくなります。
一方で、開発の現場では若い人材の採用も進んでおり、作業者としての競争は激しくなる傾向があります。そのため、積み上げた経験や実績を付加価値として提示し、自分にしか担えない役割を目指すことが大切です。
60代でもエンジニアとして活躍する方は増えているものの、50代までと比べて求人や案件を見つけにくいというケースもめずらしくありません。
こうした状況の場合、シニア向けのエージェントを活用することで選択肢を広げることが可能です。非公開案件を紹介してもらえる可能性があり、自力では見つからない求人に出会えるチャンスもあります。
たとえば、40〜60代向けに特化したフリーランス支援サービス「SEES」では、幅広い分野の案件を豊富に取り揃えています。また、無料カウンセリングも実施しているため、案件探しで悩みがある場合は相談からはじめてみるのがおすすめです。

定年後も需要のあるエンジニアとして働き続けるためには、年齢や経験に見合った実践的なスキルを備えておくことが不可欠です。若手よりも即戦力として見られることが多いため、業務に直結するスキルに加え、現代の開発現場で求められるプラスアルファの力も求められます。
また、これまで使用してきた知識やスキルについても、情報が古くなっている可能性があるため、必要に応じて学び直しておくことも重要です。
ここでは、定年後も需要の高いエンジニアとして活動する際に必要なスキルについて、以下5点を解説します。
近年は、業界を問わずにクラウドサービスを利用している企業が増えています。オンプレミス中心の時代からクラウドへの移行が進んでおり、クラウド関連のスキルを備えたエンジニアの需要が高まっているのが現状です。
たとえば、AWSやAzureなどの基本的なサービスはもちろん、サーバーやネットワーク、セキュリティに関する知識があると、幅広く活躍しやすいでしょう。
たとえクラウド関連の分野ではないとしても、時代に合った技術を習得しておくことで自分の強みとなり、求人や案件への応募時に大きなアピール材料になります。
エンジニアとしてシステム開発に携わる場合は、セキュリティに関する知識が欠かせません。ネットワークセキュリティやアクセス制御に加え、クラウド特有のリスクにも対応できる幅広い理解が求められます。
近年はサイバー攻撃の手口が高度化しており、多くの企業が対策に追われていることから、プロジェクト内でもセキュリティに配慮した開発が必要です。
今後もエンジニアとして活動するのであれば、セキュリティ分野の知識は重要な強みとなるため、早めに学び直しておくと役立ちます。
エンジニアはチームで作業をする場面も多く、メンバー間での打ち合わせや進捗管理などが欠かせません。そのため、日常作業のなかでもコミュニケーションや情報共有をおこなうことも多く、これらのスキルがないと認識のズレや作業のやり直しにつながるおそれがあります。
また、チーム内での交流は最新トレンドやスキルに関する情報を得られる機会となるため、新しい発見にもつながるでしょう。
一見、当たり前のように思えるスキルではあるものの、年代を気にして距離を置かず、積極的に関わる姿勢を持つことが大切です。
60代のエンジニアは豊富な経験を活かし、若手育成やプロジェクトのマネジメントを担う場面が増えていきます。こうした役割はキャリアを重ねた世代ならではの強みであり、大きな付加価値となるでしょう。
しかし、育成やマネジメントスキルは短期間で身につくものではないため、キャリア後半に差し掛かる40代から意識的に経験を積むことが重要です。
また、自身の成功や失敗パターンを整理し、ロードマップやリスク管理の型を用意しておくことで、いざ教育をする際にもスムーズに対応できるでしょう。
エンジニアとして働くなかで、予期せぬトラブルにも対応できる力が欠かせません。原因を冷静に分析し、応急対応と合わせて根本的な解決策まで導ける力は、経験を積んだシニアエンジニアならではの強みといえるでしょう。
とくに、トラブル対処においては過去の類似事例から学んだ知見を活かせる場面も多く、ベテランエンジニアが重宝される場面でもあります。
エンジニア業界は技術の進化が早いため、新たな問題にも自走力と探究心を備え、粘り強く取り組む姿勢が大切です。
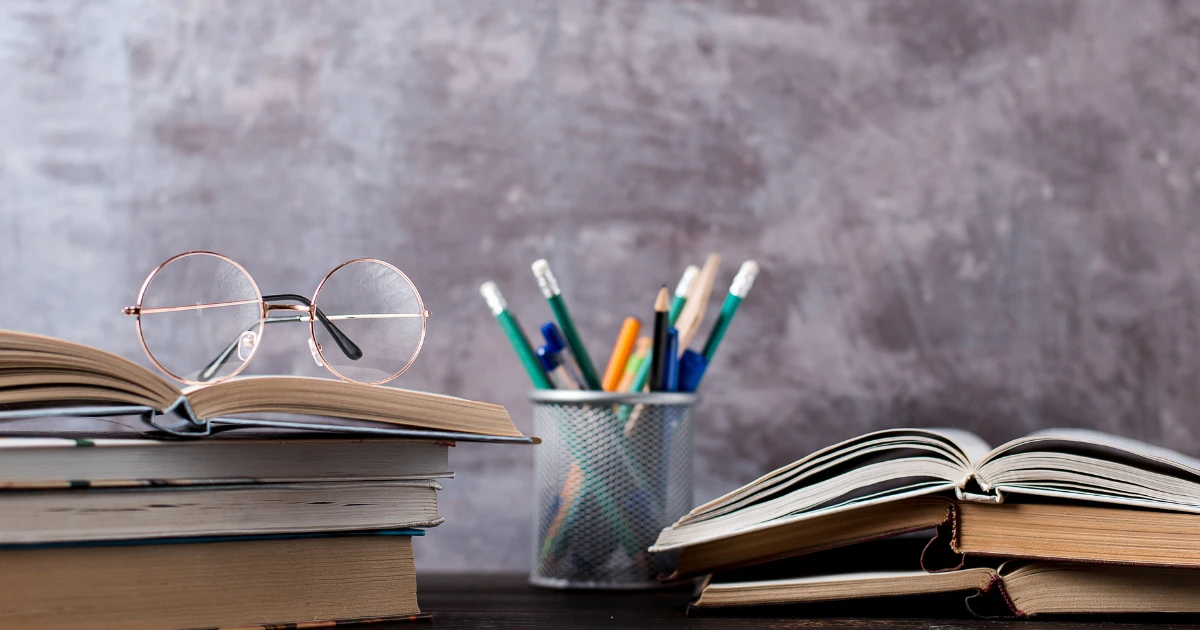
エンジニアとしてのキャリアが長いと、使用してきたスキルや知識が時代に合わなくなっている可能性があります。とくに、IT業界は変化が早いため、定期的なスキルの棚卸しと学び直しが重要です。
ただし、エンジニア業務で扱う知識は専門的であるため、どのように学習を進めるべきか迷うケースも少なくありません。こうした背景を踏まえて、自分に合った学習方法をあらかじめ把握しておくことで、定年後の準備を効率的に進めやすくなります。
ここでは、エンジニアの知識やスキルを再習得する方法について、以下4点を解説します。
技術コミュニティや勉強会は、現役エンジニアとして活動している方が多く集まる場でもあるため、より質の高い情報やスキルを習得できる傾向があります。アウトプットの場が整っているケースもあり、学習ペースを維持しやすいのも特徴です。
また、エンジニア同士の交流も生まれるため仲間ができ、1人で黙々と情報収集や勉強をするのが苦手という方にも適しています。
オンラインとオフライン問わず多くの勉強会が開催されているため、自分に合ったものをSNSやWebサイトで探してみると良いでしょう。
資格試験は、学習範囲が明確で期限が設定されているため、モチベーションを維持しつつ知識やスキルを習得したい方に適しています。公式教材が充実している試験も多く、学習計画を立てやすい点も魅力です。
また、業務で必要な知識やスキルに関する資格であれば、転職や独立の際に活かすことが可能です。
とくに、定年後は実績の可視化が重要になるため、一定の難易度がある資格を取得しておくことで、応募時のアピール材料として活かしやすくなります。
オンライン講座は、運営が用意する動画教材をもとに進められるケースが一般的であり、時間と場所を選ばずに学習を進められます。
たとえば、Udemyは講師数や教材数が多く、難易度別に学習教材が用意されているため、自分に適した教材を選びやすいでしょう。難易度別に分かれていると挫折しにくいため、講座を選ぶ際は注目してみるのがおすすめです。
もし、どの講座を選べば良いか迷った場合は、SNSやレビューサイトなどで利用者の声を参考にすると、ミスマッチを防ぎやすくなります。
エンジニアに関する知識やスキルを無料で学びたい場合は、技術ブログや動画共有サイトを活用する方法も1つの選択肢です。現役エンジニアとして活躍している方が発信していることも多く、なかには教材並みに有益な情報を得られる場合もあります。
ただし、Web上の情報には真偽が曖昧なものも含まれるため、内容を正しく見極める力が欠かせません。
とくに、技術の変化が激しいエンジニア業界では、情報の鮮度にも注意しながら、信頼できる発信者を選ぶことが大切です。

本記事では、定年後のエンジニアについて、働き方や備えておくべきスキルを交えつつ解説しました。
定年後もエンジニアとして働くことは可能であるものの、50代までと同じように活動を続けるのは難しい傾向があります。とくに、60代になると求人や案件数が減少する傾向があり、応募先を探す際は工夫が欠かせません。
また、定年後のエンジニアには即戦力として活躍できる人材が求められるため、実績はもちろん、状況次第ではスキルの再習得も必要です。
ただし、定年までの準備や努力次第では自分に適した働き先を見つけ活躍することは十分可能です。これからも長くエンジニアとして活躍するために、学び続ける姿勢と柔軟な働き方を意識してキャリアを築いていきましょう。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く