40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
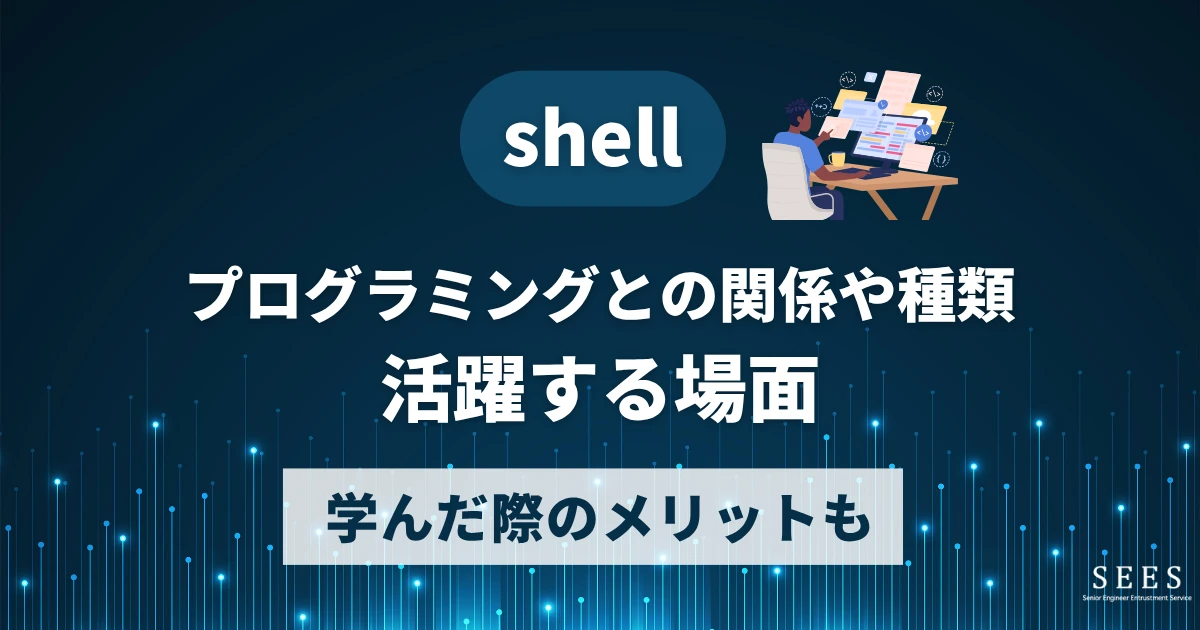
shellとは何か?仕組みやシェルスクリプトとの違い、代表的な種類や活用シーンをわかりやすく解説。メリットや注意点、実際の案件例も紹介し、エンジニアが学ぶべき理由を徹底解説します。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
shell(シェル)とは、開発業務やシステム運用のなかで、ユーザーがコマンドを入力してパソコンに指示を出す際に使われるプログラムです。
エンジニアがファイル操作やアプリケーションの起動、システムの状態確認などを実行する場面で活躍します。 shellを利用せずに業務を進めていると、作業に余計な時間がかかるうえ、手作業によるミスも増えやすくなり、効率や安全性に深刻な影響を与えるかもしれません。 一方で、shellの基礎をおさえておけば、コマンド1つで作業を自動化でき、開発や業務が効率的に進むでしょう。
本記事では、shellについて、プログラミングとの関係や種類、活躍する場面や学んだ際のメリットも交えて解説します。
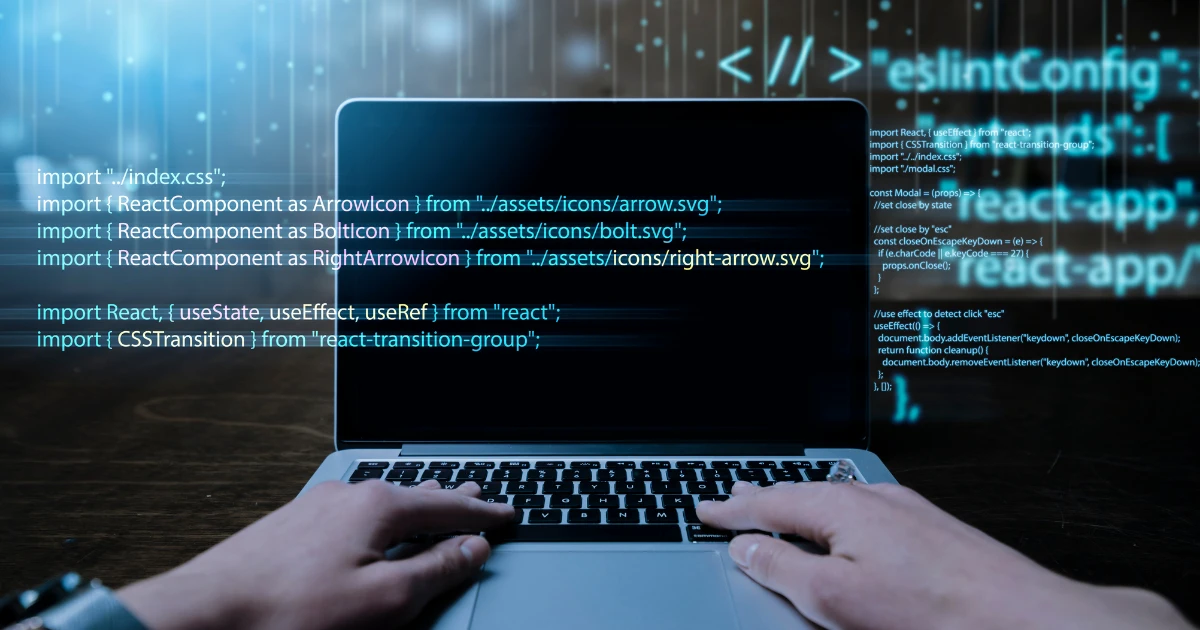
shellとは、ユーザーが入力したコマンドを解釈し、それをOSに伝えて処理させるプログラムのことです。パソコンやサーバーと人間とをつなぐ役割を持っており、アプリの操作やファイルの整理など、システム操作の多くはこのshellを通じておこなわれています。
正しくshellを活用するためにも、仕組みやシェルスクリプトとの違いを理解することが大切です。
shellの役割は、ユーザーからの命令をOSに伝え、その処理結果をユーザーに返すことです。shellにコマンドを送ると、以下の流れでコンピュータは動作します。
このように、shellは「命令の窓口」であり、ユーザーとコンピュータの橋渡しを担っています。
shellと似た言葉に「シェルスクリプト」がありますが、この2つは明確に役割が異なります。
| shell | ユーザーがその場で命令を入力して1つずつ実行するもの |
|---|---|
| シェルスクリプト | 複数の命令を1つのファイルにまとめて実行する「自動化の手順書」のようなもの |
たとえば、毎朝「ログを収集して、メールを送る作業」を手動でおこなっている場合、それらの処理をすべて自動化するものがシェルスクリプトです。一方で、「ログを収集」、「メールを送る」という作業を別々に処理するものがshellです。
このように、shellとシェルスクリプトは似た言葉であるものの、使用する場面や実行する命令の数が異なります。

一言でshellといっても、実際にはさまざまな種類が存在し、それぞれに特徴や利便性があります。shellを活用する際は使用するOSや開発環境、用途によって使い分けることが重要です。
とくに、BashやZsh、shなどは多くのエンジニアに利用されており、現場によっては「指定されたshellが使えないと業務に支障が出る」ケースもあります。なるべく多くのshellを利用できることで、携われる業務の幅も増えるでしょう。
ここでは、6つの主要なshellについて、その特徴もあわせて解説します。
Bashは、現在もっとも広く利用されている標準的なshellです。LinuxやmacOSなどのUNIX系OSに標準搭載されており、システム管理や業務自動化の場面で使用されています。
Bashはシェルスクリプトを利用した、繰り返しの作業を自動化することが得意です。同じ処理を繰り返す「ループ」、よく使う処理をまとめられる「関数」など、便利な機能も揃っています。
shellを実務で使用するならば、最初に覚えておきたいshellといえるでしょう。
Zshは、macOSの標準ログインシェルとして採用されているshellです。Bashとの互換性を保ちつつ、入力補完や見た目のカスタマイズ機能が強化されています。
たとえば、コマンドを途中まで入力すると自動で続きを予測してくれたり、コマンドやファイル名が色付きで表示されたりと、使いやすさや視認性に配慮された設計になっています。
作業効率だけでなく、見た目や操作感にもこだわっている方におすすめです。
Fishは、直感的な操作とわかりやすい構文が特徴のshellです。ほかのshellと異なる独自の構文設計を採用しており、ミスの少なさや補完機能の強さが評価されています。
Fishはコマンドを入力すると、文字の色が変わって間違いに気づきやすくなったり、過去に入力したコマンドを自動で提案してくれたりと、親切な機能が揃っています。
個人でのプログラミング学習や小規模の開発に使用する方が多いうえ、POSIXとは非互換のため、業務利用の標準にはなっていないケースが多いです。
Cshと、その改良版であるTcshは、かつて学術機関や教育現場で使用されていたshellです。構文がC言語に似ているため、C言語経験者にとっては馴染みやすい点があります。
現在の主流ではありませんが、過去のシステムを保守・運用する際に知識が求められるケースも少なくありません。このshellの知識は現場で古いスクリプトを読む必要がある、既存資産の解析や修正をおこなうといった際に役立つでしょう。
Kshは、かつて商用UNIXシステムで広く使われていたshellです。高速化を目的として開発され、処理や豊富な構文機能があり、大規模業務システムの現場で長年使用されてきました。
現在でも一部の金融系システムや製造業の保守運用現場ではKshが使われていることがあり、古い開発環境へ対応する際の知識として触れておく価値があります。UNIX環境に携わる予定がある方は、Bashとの違いやKsh独自の機能についても一通り触れておくと安心です。
shは、UNIXが台頭し始めた頃から存在する基本的なshellです。機能はシンプルなため複雑な処理には向かないものの、動作が軽いことから、最低限のコマンドを実行するには十分な性能を持ちます。
現在でも、古いシステムや組み込み機器、POS端末などの軽量OS環境ではshが使用されています。そのため、ほかのshellを使用する場合でも、命令文を書く際に「shでも動くように意識する」といった配慮が求められる場合もあるでしょう。

shellは、日常的なファイル操作以外にも、システムの運用・保守・管理を効率化するための強力なツールです。とくに、インフラ系やバックエンド業務においては欠かせない存在となっています。
shellの活用シーンを理解しておけば、作業の自動化が実現し、日々の業務を大幅に効率化できるでしょう。
ここでは、実際の現場でshellが活躍している場面を4つ解説します。
shellを使えば、Webサーバーやデータベース、バッチ処理アプリケーションなどの起動・停止・再起動を簡単なコマンド1つで実行できます。
たとえば、「systemctl restart apache2」とコマンドを入力するだけで、ApacheというWebサーバーをすぐに再起動できます。こうした操作はshellを活用することで、マウス操作よりも素早く、かつ正確に実行が可能です。
このように、shell操作はサーバーの不具合や、設定を変更後の再起動などで活躍します。
shellは、ログファイルやCSVなどのテキストデータから、必要な情報を素早く取り出す作業に便利です。
たとえば、特定のキーワードを含む行だけを探したり、必要な列だけを抜き出したりなど、コマンドの組み合わせでデータの抽出が簡単にできます。
「エラーが出たログだけを抜き出す」や「特定の日付のデータだけを集める」といった処理は、Excelよりもshellのほうが早くて正確な場合も多く、分析ツールを使う前の準備として活用される場面も少なくありません。
shellはシェルスクリプトを作成することで、定期的に繰り返すような作業は自動化できます。
たとえば、「夜にログをバックアップして特定フォルダに保存する」、「朝9時に監視結果をメールで送る」などの作業は、シェルスクリプトと自動実行の設定を組み合わせることで、決まった時間に動かすことが可能です。
自動化によって、作業ミスを防ぐだけでなく、毎回の操作にかかっていた時間や手間を削減できるため、システム運用の現場では欠かせないスキルです。
shellは、ネットワークが正常に動いているかどうかをチェックしたり、問題が起きたときに原因を調べたりするのにも役立ちます。たとえば、コマンドを入力することで、ポートの使用状況や通信経路の確認が可能です。
これらのコマンドをスクリプトにまとめておくことで、定期的に監視をおこない、異常があればメールで通知するといった自動システムも作れます。
このような自動監視を構築する際にも、shellスクリプトが活躍するでしょう。

shellはインフラや業務システムの運用・保守の現場で、バッチ処理やログ管理、監視スクリプトの作成といった多くの作業で使われています。shellを扱えることで、繰り返しの作業を自動化し、トラブルにも迅速に対応できます。
しかし、shellのスキルだけでは携われない業務も多いため、身につける際は関連スキルもあわせて学ばなければなりません。
実際の案件をもとにshellが活用されている場面を理解することで、必要なスキルを明確にしやすく、現場での対応力やキャリア設計にも役立ちます。
ここでは、実際の案件をもとにshellを扱う仕事を解説します。
ある案件では、社内DNSを更改する例にshellのスキルを使用しています。
この案件では、すでに起動しているシステムにおいて、サーバーのバッチ処理をおこなわなければなりません。shellを使えば、繰り返しの作業が多いバッチ処理でも、起動・停止・再起動を簡単なコマンド1つで実行できます。
| 概要 | 社内DNS更改案件 |
|---|---|
| 報酬 | 〜550,000円/月 |
| 契約形態 | 業務委託(フリーランス) |
| ポジション | プログラマー・テスター |
| 期間 | 中長期 |
| 作業内容 | サーバーのバッチ処理の更改 |
| 作業工程 | - |
SEESで社内DNS更改案件をチェック!
ほかの案件では、銀行向け基盤更改にともなう開発の際に、shellが活用されています。
このような案件では、システムの再構築や運用設計にともなって、ログデータやCSVファイルの抽出・加工業務が発生します。shellを使ってログファイルのなかから特定のエラーコードを探したり、日付ごとのアクセス数を集計したりといった、大量のデータの処理を扱うと考えられるでしょう。
この案件では、shell経験以外にもLinux環境やJavaScriptの経験が必要です。このことから、shell単体のスキルだけでなく、開発業務全体を理解したうえで、データの抽出・分析ができる人材が求められています。
| 概要 | 銀行向け基盤更改に伴う開発の案件 |
|---|---|
| 報酬 | 〜600,000円/月 |
| 契約形態 | 業務委託(フリーランス) |
| ポジション | プログラマー・テスター システムエンジニア |
| 期間 | 長期 |
| 作業内容 | 銀行向け基盤更改に伴う開発 |
| 作業工程 | 基本設計~テスト |
SEESで銀行向け基盤更改にともなう開発案件をチェック!
ある案件では、証券会社が運用している業務システムの安定稼働を支える際に、shellのスキルが求められています。
証券関係のシステムでは、夜間のバックアップや監視結果の収集・保存など、毎日繰り返される作業が多くあります。shellを活用することで、これらの業務を自動化でき、運用効率の向上や人的ミスを防ぐことが可能です。
この案件では、シェルスクリプトの作成経験以外にも、運用保守の実務経験が求められます。安定稼働を支えるためにも、想定外のトラブルに柔軟に対応できる力も必要です。
| 概要 | 証券関係の運用支援の案件 |
|---|---|
| 報酬 | 〜600,000円/月 |
| 契約形態 | 業務委託(フリーランス) |
| ポジション | インフラエンジニア |
| 期間 | 長期 |
| 作業内容 | 株式の約定情報から指数の算出と配信を実施 運用に関連する作業 保守対応 |
| 作業工程 | - |
SEESで証券関係の運用支援案件をチェック!

shellは作業の自動化やデータの抽出により、業務効率を大きく改善できるツールです。エンジニアがシェルを学ぶことで、作業のスピードや正確性が高まります。
一方で、shellを活用せずに作業をしていると、「作業は減らず、成果も上がらない」といった悪循環に陥る可能性も否定できません。
shellを学ぶメリットを理解しておくことで、スキルを前向きに身につけられ、業務の質とスピードを両立できるようになるでしょう。
ここでは、エンジニアがshellを学ぶメリットを解説します。
日々の作業をシェルスクリプトで自動化すれば、作業時間を大幅に短縮でき、ヒューマンエラーも減らせます。
たとえば、ログの整理やファイルの圧縮・転送、システムのバックアップなど、毎日同じ作業を手動でおこなっているなら、一つひとつのコマンドをシェルスクリプトとしてまとめることで手動の工程を自動化できます。
人手が空いた分をほかの業務に回せるため、生産性の向上にもつながるでしょう。
shellは多くのUNIX系OSに標準搭載されており、環境が変わっても同様の操作やスクリプトが通用するケースが多いです。別の現場で覚えたコマンドや自動化スクリプトを、次の現場で活かせるため、再学習の手間がかかりません。
このような高い汎用性は、職場やプロジェクトが変わってもスムーズに対応できる強みとなり、慣れない現場での作業時間の短縮やミスの防止にもつながります。
shellはC言語やJavaScriptのように、コードを一度コンパイルしてから実行する必要がありません。記述したスクリプトをすぐに実行できるため、動作確認や修正をその場で反映できます。
たとえば、少しずつ内容を調整しながらスクリプトを完成させたいときや、トラブル対応で一部だけ修正して再実行したいときにも、スピーディーに対応できます。
とくに運用現場では、素早く状況に応じてスクリプトを変更して、実行できることが高く評価されるでしょう。
shellは単体で使用する場合でも便利ですが、ほかの言語やツールと自由に組み合わせられる柔軟性を持ち合わせています。
たとえば、Pythonスクリプトを呼び出してデータを処理したり、SQLを実行してデータベースと連携したりする処理も、1本のシェルスクリプトでまとめることが可能です。
複雑な処理フローを簡潔に保ちたいときや、複数チームにまたがる作業を一元管理したいときにも、shellは頼れる存在になるでしょう。
shellは、サーバーの構築や保守、システム監視、ジョブスケジュールの管理など、インフラ系の業務で必須スキルとして扱われることが少なくありません。
実際、Linuxサーバーを操作する際には、設定ファイルの編集、サービスの再起動、ログの取得、アクセス権限の確認など、多くの作業がコマンドベースでおこなわれます。
shellを扱えることで、「この人は現場を理解している」や「障害時にも任せられる」などの信頼を得られる可能性が高まります。

shellは便利なツールですが、使い方を誤ると、かえって業務効率を下げるや、システム障害につながるおそれもあります。「とりあえず動いたからOK」と中身を理解せずに運用を始めると、予期せぬ結果を招くことも少なくありません。
shellを使用する際は適材適所を意識し、適していない場面ではほかの言語やツールを使用しましょう。
ここでは、shellを利用する際に知っておくべき注意点を解説します。
shellは、Webサイトやアプリケーションのように、画面に応じて動作が変わるような開発には向いていません。
たとえば、ユーザーごとに画面を変えたり、サーバーとリアルタイムでやりとりしたりする場合は、Python・PHP・Node.jsなどのプログラミング言語を使う方が効率的です。
無理にshellでコードを書こうとすると、内容が複雑化して修正が困難になるため、Web開発では補助的な使用を意識しましょう。
AWSやGCPなどのクラウドサービスでは、サーバーやネットワークなどの設定をAPIでおこなうのが一般的です。
shellでもコマンド入力ツールを活用すればある程度の操作が可能ですが、アクセス権の管理やトークンの更新など、細かい設定が複雑になります。
最近ではシステムの構成自体をコードで管理するために、専用ツールが使われています。こうしたツールの方がクラウドサービスと相性が良く、shellは補助的な使い方にとどめるのが主流です。
shellは、1行ずつ順番に処理を実行することが基本のため、大量のデータを一気に処理したり、リアルタイム性が求められたりする作業には不向きです。
たとえば、チャットの即時応答や動画のリアルタイム変換、大規模なログ解析などでは、処理速度が遅くなってしまうケースがあります。
このような場面では、GoやRustなどの高速処理に適した言語や、専用のミドルウェアを使うほうが安定して動作します。

本記事では、shellについて、プログラミングとの関係や種類、活躍する場面や学んだ際のメリットも交えて解説しました。
shellは、単なるコマンド入力ツールではなく、サーバー運用やネットワーク監視などの実務で、作業を効率的に進められるプログラムです。とくにインフラ領域やバックエンド業務においては、shellを扱えることが信頼とスピードを生み出す大きな武器になるでしょう。
今回紹介したように、shellには多くの種類があり、それぞれの特徴を理解して使い分けることで、より柔軟な業務対応が可能になります。
shellの技術を身につけることで、エンジニアとしてより多くの業務を任せられることでしょう。
簡単な作業でもshellを活用すれば、便利さを実感できるため、ぜひ日々の業務に取り入れてみてください。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く