40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】

Webサービスなどの提供において責任者となるプロダクトマネージャーは注目の集まるポジションです。この記事では、プロダクトマネージャーの概要、果たす役割、業務内容、必要となるスキルなどについて詳しく紹介します。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
「最近よくプロダクトマネージャーという言葉を耳にするけれど実際はどんな職種?」
「プロダクトマネージャーについて興味を持っているため詳しく知りたい」
「プロダクトマネージャーとプロジェクトマネージャーは名前は似ているけれど同じ仕事?」
エンジニアがキャリアパスを検討する中で大きな目標ともなるプロダクトマネージャーという仕事について、詳細を知りたいという方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、人気上昇中のプロダクトマネージャーとはどんな仕事かをはじめ、その役割とプロダクトマネジメントに必要なスキル、さらにはおすすめの書籍などについて詳しく説明しています。
この記事を読むことで、プロダクトマネージャーの業務についての基礎知識や具体的な業務内容に加え、目指す際に必要になるスキルが理解できるでしょう。
プロダクトマネージャーは、今後も活躍が期待される仕事の一つであるため、詳細を把握し、キャリアパスの参考にしてみてください。

プロダクトマネジメントとは、直訳すると「製品管理」という意味を表します。しかし、プロダクトマネージャーの仕事は製品管理だけでなく、より幅広いものです。
簡単に説明すると、製品やサービスが最初に意図した価値を提供できるように導くのが、プロダクトマネージャーの役割と言えるでしょう。
ここではまず、プロダクトマネージャーについて詳しく解説していきます。
「プロダクト(product)」とは、本質的には「顧客に価値を提供する」という意味を持つ言葉です。
マーケティング用語として使われる場合には、製品や制作物、商品やサービスなどを表すのが一般的でしょう。また、「どんな製品を販売するのか方針を立てる」という意味も持っています。
一例として、食品を扱う企業で考えてみましょう。
企業側は、消費者へ食品を通じて食べる楽しみや健康、安全、満足感といった価値を提供する代わりに収益を得ます。それに対し顧客は、製品やサービスを通して価値を得る、というのが「プロダクト」の考え方と言えるでしょう。
それに対し「プロジェクト」は、目的をもって作られる製品に対する計画や業務そのものを指している言葉です。
プロダクトはさまざまな企業において存在しますが、特にIT業界では自社でWebサービスやパッケージソフトウェアを提供する企業でよく使われる言葉です。継続的に自社の製品として販売し、ソフトウェアが自社の利益を生み出す仕組みを持つ場合が該当します。SIerなどがクライアントが利用するサービスを構築する場合には、あまりプロダクトという名称は使いません。
従ってプロダクトマネージャーというポジションは自社でWebサービスなどを提供する企業などに存在します。
プロダクトマネジメントは、顧客に価値を提供するために、顧客のニーズを深く理解し、どんな製品が求められているのかを知ることから始まります。そのうえで、ニーズを満たすための製品やサービスを販売することが主な仕事です。
そのため、製品管理だけでなく、事業責任者としての役割を持ち、顧客のニーズ以外にも、全体を統一したデザインや提供方法や顧客体験など、幅広くビジネス全体のマネジメントを行います。
Webサービスの場合には、プロダクトにより収益を上げ続けられるビジネスを組み立てることまでがプロダクトマネジメントには含まれます。プロダクトの成長により事業を拡大することもプロダクトマネジメントの一環です。
プロダクトマネージャーは、ミニCEOと言われるくらい、事業責任者として幅広く重要な責任を担い、プロダクトの全てのプロセスに関わります。
製品を実際に販売し、サービスを提供するまでに、何を作りどんな工程を経るのかといった上流工程から、製品やサービスを提供した後のマーケティングや撤退時期の見極めといった下流工程まで行うのが特徴です。
Webサービスを提供する事業者の場合には、ある一つのWebサービスにおいて企画や方針の検討から、開発や運用などのエンジニアの統括、ビジネスとして収益を上げることなどにも責任を持つ立場となります。
一見同じような役割を持つように見える両者ですが、責任を持つ部分や方向性が違っています。仕事の上で役割を兼務することはあるとしても、その役割には次のような違いがあることを把握しておきましょう。
プロダクトマネージャーが製品の企画をはじめ、開発・販売・改善、さらには事業の成功や目標達成にまで責任を持つのに対し、プロダクトマーケティングマネージャーの責任範囲は、あくまでも製品の販売に限るという点で異なります。
また、プロダクトマネージャーは社内に向かった働きが多いのに対し、プロダクトマーケティングマネージャーは、製品の価値を市場に伝えるなど、社外に向かう働きが多いという点も大きな違いです。
プロダクトマネージャーと混同されやすいもう一つの職業として、プロジェクトマネージャーが挙げられますが、この両者は、マネジメントする対象が違っています。これにより、マネジメントの期間や目的、必要なスキルまで、すべてが異なります。
そもそも、プロジェクトとは特定の目的をもとにして、開始時期と終了時期が決まっている活動です。プロジェクトマネージャーがマネジメントする対象はプロジェクトであり、その管理が主な目的となります。つまり、プロジェクトマネージャーは特定のゴールに向けてプロジェクトを推進する有期の仕事といえます。
プロダクトマネージャーの仕事は、市場に製品やサービスがある限り活動が続きます。事業として継続的に収益を上げ、製品の寿命が見えたらクローズするライフサイクルの終焉まで面倒をみます。製品価値を最大まで引き上げることを目的とした、息の長い仕事と言えるでしょう。

プロダクトマネージャーの年収は、上限と下限の幅が広く、その他の業種と同じくらい状況や個人によって差があるようです。
2022年にプロダクトマネジャーに対して行われた調査では、対象者625人のうち300万円未満から2,000万円以上まで年収幅があることが公開されています。
また、PROJECT COMPによる2025年3月13日時点の年収統計データからは平均年収は980万円、indeedによる2025年3月24日時点のデータでは約779万円とされています。
国税庁の令和5年分 民間給与実態統計調査において、給与所得者の平均が約460万円だとされていることから、プロダクトマネージャーの年収は比較的高いと言えます。
事業の責任者であるため、かかる負担や責任は大きく、その分収入も高いといえそうです。役職などを持つ場合も多く、エンジニアのキャリアアップ先として目指すべきポジションの一つとなります。
出典:日本で働くプロダクトマネージャー大規模調査レポート2022|一般社団法人プロダクトマネージャーカンファレンス実行委員会,PROJECT COMP - エンジニアの給与データベース,日本でのプロダクトマネージャーの給与

プロダクトマネージャーの業務はプロダクトの計画段階からライフサイクルの終焉まで全ての工程に関わるため、かなり幅広いのが特徴です。その仕事内容は製品管理にとどまらず、顧客満足度を高め、最大利益を得るためにさまざまな取り組みが必要になります。
ここからは、プロジェクトマネージャーの行う仕事内容について、それぞれ詳しくご紹介します。
プロダクトマネージャーは、プロトタイピングを行った後、ユーザーが求めているのはどのような製品やサービスなのか、どんな客層なのかというターゲット設定を行います。初期段階でターゲットを定めることで、より正しく明確に、製品開発が行えるようになります。
ターゲットを絞り込むことでニーズに合った製品を作れるようになれば、その特徴やニーズに合わせた製品開発も可能になるため、大きな成果が得られるでしょう。ただし、開発したプロダクトを利用してくれるユーザーがターゲット通りとなるかは未知数で、サービスリリース後にターゲット層が想定と違うと気づいた場合は柔軟に変更することも大切です。
責任者であるプロジェクトマネージャーは、プロダクトの企画及び立案にも関わります。前述のターゲット設定で、どんな製品なら顧客満足度が上がるのかが見えたら、次はプロダクトの企画・立案です。
ここでは、どんな製品をどんな方法で販売するのか、効果的な方法を企画・立案し、検証を重ねてロードマップを作ります。
その後、チームが同じ方向を向いて進めるよう、製品のビジョンや方向性、中間目標などについて具体的に決めていくことになります。
プロダクトマネージャーは、プロダクト・マーケティング戦略の策定を行うリーダーでもあります。そのため、顧客満足度を上げるためにどのような販売方法を行うべきかを考える下流工程も行い、プロダクトによる事業についての情報の収集・分析までも行います。
もちろん、有効なビジネスケースを作成し、新商品の開発や市場への投入方法を考えるなど、上流工程にも関わり続けます。
このように、目的達成に向けて順調に進捗しているかを測る重要業績評価指標(KPI)を定め、マーケティング戦略を策定することもプロダクトマネージャーの仕事です。
製品やサービスの品質や機能の効果の検証も、プロダクトマネージャーが中心となって行います。この検証は、プロダクトのリリース後も、製品が撤退するまで継続して行います。
リリースまでの開発やユーザーによる評価を振り返ることで、改善点を明確にし、目標を正しく定められるようになるため、これも重要な役割です。さらに、これらのフィードバックは自社の別の事業にも役立てられるため、組織としての製品価値や売り上げの増大につながるでしょう。
PdMはプロダクトマネージャーを、PMはプロジェクトマネージャーを表す略語です。
PdMとPMの役割の違いは先述の通りですが、両者の仕事内容には重複している部分もあり、総合的にスキルを持った人材は貴重なため兼任することも多いです。特に日本の企業の場合、PdMとPMでの兼任業務が発生しやすいと言われています。
PdMは製品、PMは人に向き合うと言われていますが、両者を兼任する場合は、かなり過酷な業務となることが予想されるでしょう。
 主にIT業界のプロダクトマネージャーが成果を求められる重要な3つの領域として、ビジネス・テクノロジー・UXがあげられます。
主にIT業界のプロダクトマネージャーが成果を求められる重要な3つの領域として、ビジネス・テクノロジー・UXがあげられます。ビジネスは市場でユーザーを獲得し、収益を上げられるかどうかを判断していく領域です。企業の事業としてプロダクトを運営する上では、利益をあげなければ組織への貢献ができません。
テクノロジーは、プロダクトがチームの提供する技術によって実現可能なのかどうかを判断する領域です。ただし、求めるプロダクトは既存技術だけで実現できるとは限らず、またチームに知見がない場合もあります。それでもプロダクトチームが必要なテクノロジーを活用してプロダクトを実現できるかを見極めることが求められます。
最後のUXは、プロダクトによってユーザーにあらたな経験を提供することです。Webサービスなどにより従来はなかった価値の創造、提供をすることが、今後の事業の中では重要視されています。
プロダクトマネージャーの役割は、上記の3つの領域が重なった部分とされています。

プロダクトマネージャーが近年注目されていることには、いくつかの理由があります。ここからは、プロダクトマネージャーが注目される理由について、具体的に紹介します。
プロダクトマネージャーを目指したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
従来のSIなどのIT業界のビジネスでは、企業に向けた業務効率化のためのシステム提供などが行われてきました。その必要性は変わってはいないものの、顧客向けのシステム提供ではIT企業はシステムの構築や運用費用までがビジネスの対価であり、更なる収益には繋がりませんでした。もちろん、パッケージソフトウェアという形式はありましたが、売り切りのビジネスがメインで継続的に大幅な利益を生み出すことは容易ではありませんでした。
インターネットやクラウドサービスの普及に伴い現れたのが、ITプロダクトをより広いユーザー層に提供し、その対価として直接的に収益を上げるビジネスです。一般の個人ユーザーや小規模な企業などにも、Webサービスなどの形でプロダクトを提供することでユーザー数を増やし、また後述するサブスクリプションによるビジネスモデルにより継続的に収益をあげる方法が確立されたことにより、自社でサービスを提供する企業が大幅に増えました。
このように目覚ましい発展を遂げるIT業界には、プロダクトマネージャーの技術や力量が試される場が数多くあります。慢性的な人材不足の問題があるIT業界では、プロダクトマネージャーの必要性は高まり続けていると言えるでしょう。
Webサービスというビジネスモデルでは、Webシステムそのものをクライアントに売るのではなく、Webサービスの利用を月額制などの料金体系で提供する形態が多く見られます。いわゆるサブスクリプションモデルと呼ばれるビジネス形態です。
サブスクリプションモデルは、継続的に売り上げが上げられること、ユーザーを増やすことで収益が増やせるといった利点があります。ただし、継続的にユーザーに満足してもらい利用を続けてもらう必要があるため、リリース後もサービスの改善、新規機能の追加を続けることが必要となります。
プロダクトの継続的改善が求められるサブスクリプションというビジネス形態に対し、プロダクトの責任者となるプロダクトマネージャーという役割が重視されるようになったのです。
サブスクリプションモデルなどでは、継続的な開発、リリースが前提となります。最初に全体を計画して、計画に沿って段階的に開発を行うウォーターフォールと呼ばれるシステム開発手法は、柔軟な開発と短期的にリリースを繰り返すスケジュールには適していません。
このような背景から、Webサービスなどの提供で主流になってきているソフトウェアの開発手法がアジャイル開発です。アジャイル開発では、有期のプロジェクトとは責任者に求められるスキルや役割も異なります。
アジャイル開発は反復的にくり返し一定規模の開発とリリース作業を行うことで、サービスを運営しながら改善していくことができる方式です。Webサービスの提供において最適な開発手法といわれることが多く、開発スピードの向上などが見込めますが、従来型の開発手法とはスケジュールやコスト管理についても異なる部分も多いです。
プロダクトという軸を中心としてマネジメントを行うプロダクトマネージャーというポジションは、アジャイル開発の適用のためにも大きな役割を果たしています。

プロダクトマネージャーになるために、特に必要な資格はありません。
しかしながら、プロダクトの責任者として事業を成功させるために必要なスキルは多岐に渡ります。
ここでは、プロダクトマネージャーとして活躍するために必要となるスキルについて紹介します。
プロダクトマネージャーが取り組むソフトウェア開発の業務は、新商品の開発などいままでにないものを作り上げる仕事であることが多いです。新たなことに関わるため、発想力が求められます。
既存の概念にとらわれることなく、柔軟な思考や発想の転換が必要になることも多いため、発想力の豊かさは重要なスキルと言えます。
考察力や理解力は、プロダクトマネージャーには必須のスキルです。
プロダクトマネージャーの業務には、プロダクトの周辺の課題解決が含まれています。考察力や理解力を駆使して、これらの課題に取り組むことが必要になります。
課題がどんなものかを深く理解し、効果的な解決策を導き出すための考察は、プロダクトマネジャーにとって非常に重要な作業です。
もちろん、マーケティングなどの業務でも考察力と理解力はベースとなる能力といえます。
プロダクトを作り売る仕事のため、企画・開発・販売をはじめとした分野の知識が必要です。さらには、ジャンルを超えた幅広い知識もプロダクトマネージャーには求められます。
プロダクトマネージャーは、企画・開発・販売の全てに責任を負う立場であるため、専門的な議論が必要な場面にも多く立ち会います。全体を見渡すことのできる視点とともに、広い知識を身に付けましょう。
スケジュール管理や進捗状況の把握など、幅広い分野の責任を負うプロダクトマネージャーには、開発チームの関連メンバーをサポートし、まとめる力も必要です。これには、リーダーシップやプロジェクトマネジメントスキルなども含まれるでしょう。
プロダクトチームを一体化し、ビジネスの成功という大きな目標に導く存在として重要なスキルです。
目標の利益を得るため販売目標の達成がプロダクトマネージャーには求められます。したがって、市場を把握し、適切にユーザーを掴むマーケティング能力も必要になります。
ターゲットになる客層や販売方法など、ニーズに合わせた改善を重ね、売り上げを最大化させるために必要なスキルといえます。
プロダクトの開発や運用の場面では、チームメンバーを取りまとめ、さまざまな人へ対応する必要があるため、プロダクトマネージャーにはコミュニケーションスキルが必要になります。
企業内のさまざまな部門と連携しながら業務を進めるにあたって、リーダーシップを取りながらまとめ役として仕事を進める能力が求められます。
新製品や新サービスの開発には課題がつきものです。製品やサービスに対して理解・分析した後に、課題解決にも取り組むことになります。
プロダクトマネージャーは現場の問題を洗い出し、解決策を考えて対策を実行するため、論理的思考による課題解決力が必要となります。
プロダクトマネージャーは、プロダクトに関連した幅広い分野の管理の責任を負います。
そのため、開発だけでなく、品質や在庫、納期や広告までさまざまな業務を総合的に管理し、調整する必要があります。
最終的にはユーザーの視点からプロダクトを見て、ニーズや品質向上などを検討するためにも、客観的視点が必要です。

プロダクトマネージャーになるための資格は特にはありません。しかし、業務では様々な問題が起き、それを柔軟に解決していくことが求められます。
従って、プロダクトチームのエンジニアやプロジェクトをマネジメントするポジションで業務経験を積み、スキルや能力を身に付けたのちにたどり着く場合がほとんどです。
さまざまな経験を積んで成功を重ね、結果を出し続けることでプロダクトマネージャーへの道が開けると言えるでしょう。
プロダクトマネージャーを目指すのであれば、自社の商品開発をしている企業で経験を積むことをおすすめします。

プロダクトマネージャーを目指すには、自社の商品開発をしている企業で経験を積むことが有効なアプローチとなります。
また、自分で経験を積むこと以外にも、プロダクトマネージャーに関する書籍を読んで先人の経験を参考にしてみるのもおすすめです。
ここでは、プロダクトマネージャーを目指す人に役立つ本を紹介します。興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
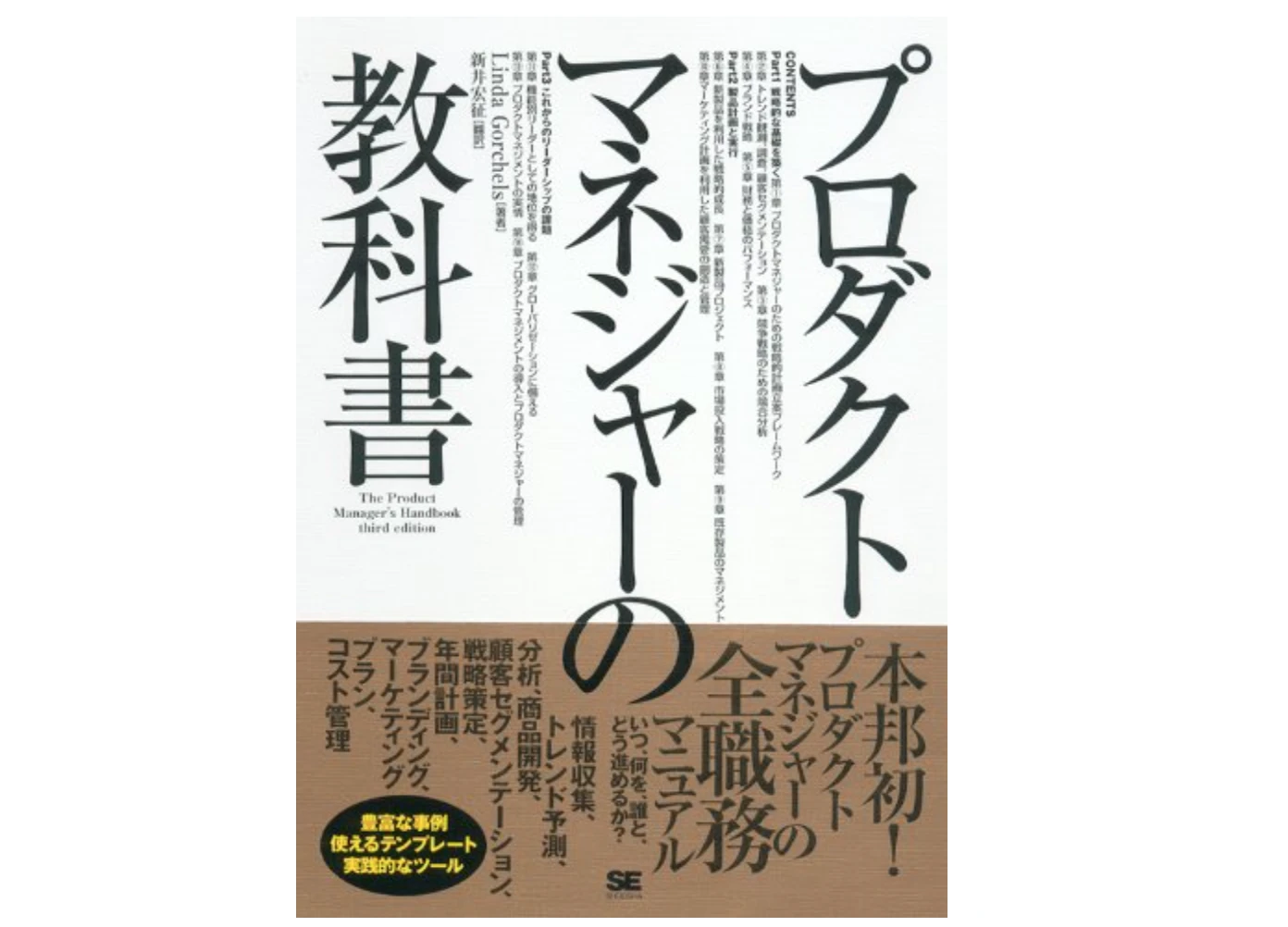
引用:プロダクトマネージャーの教科書(翔泳社、著:Linda Gorchels、訳:新井 宏征)
この本は、プロダクトマネージャーの職務マニュアルとも言える本です。プロダクトマネージャーが身に付けるべき知識からプロダクトマネジメントの考え方を組織に取り入れるときのポイントまで、基礎から教えてくれる教科書的一冊といえます。
プロダクトマネージャーを目指す人、プロダクトマネジメントについて知りたい人の両方が活用できる本です。
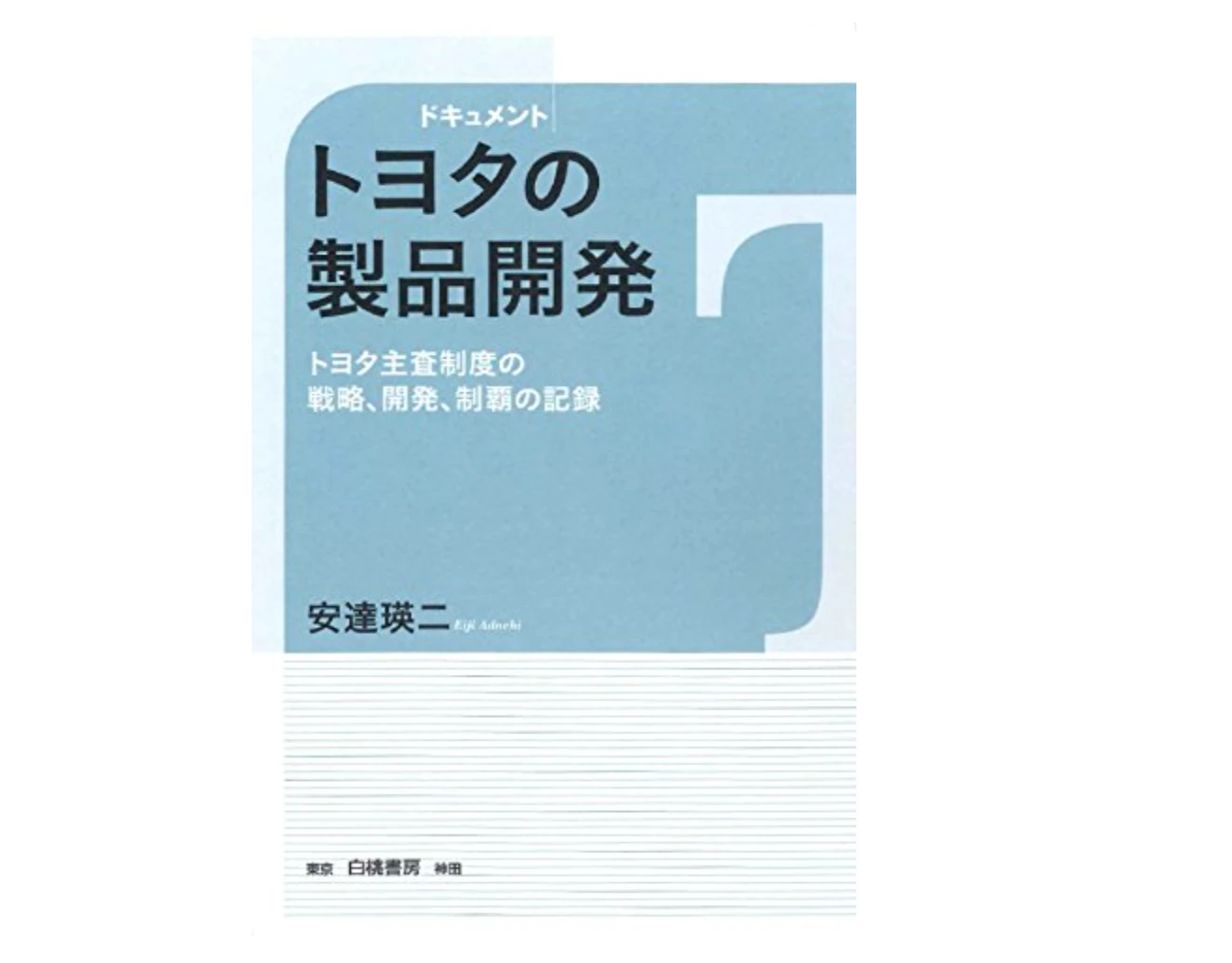
引用:ドキュメント トヨタの製品開発: トヨタ主査制度の戦略,開発,制覇の記録(白桃書房、著:安達 瑛二)
この本は、トヨタのブランドマネージャー制度に着目して書かれたドキュメンタリーです。石油危機の状況下、小型上級車を含む3つの車種の販売に挑戦した技術者たちの話が描かれています。
日本のものづくりの舞台裏を知ることによって、日本のプロダクトマネジメントの足跡を知ることができる一冊です。
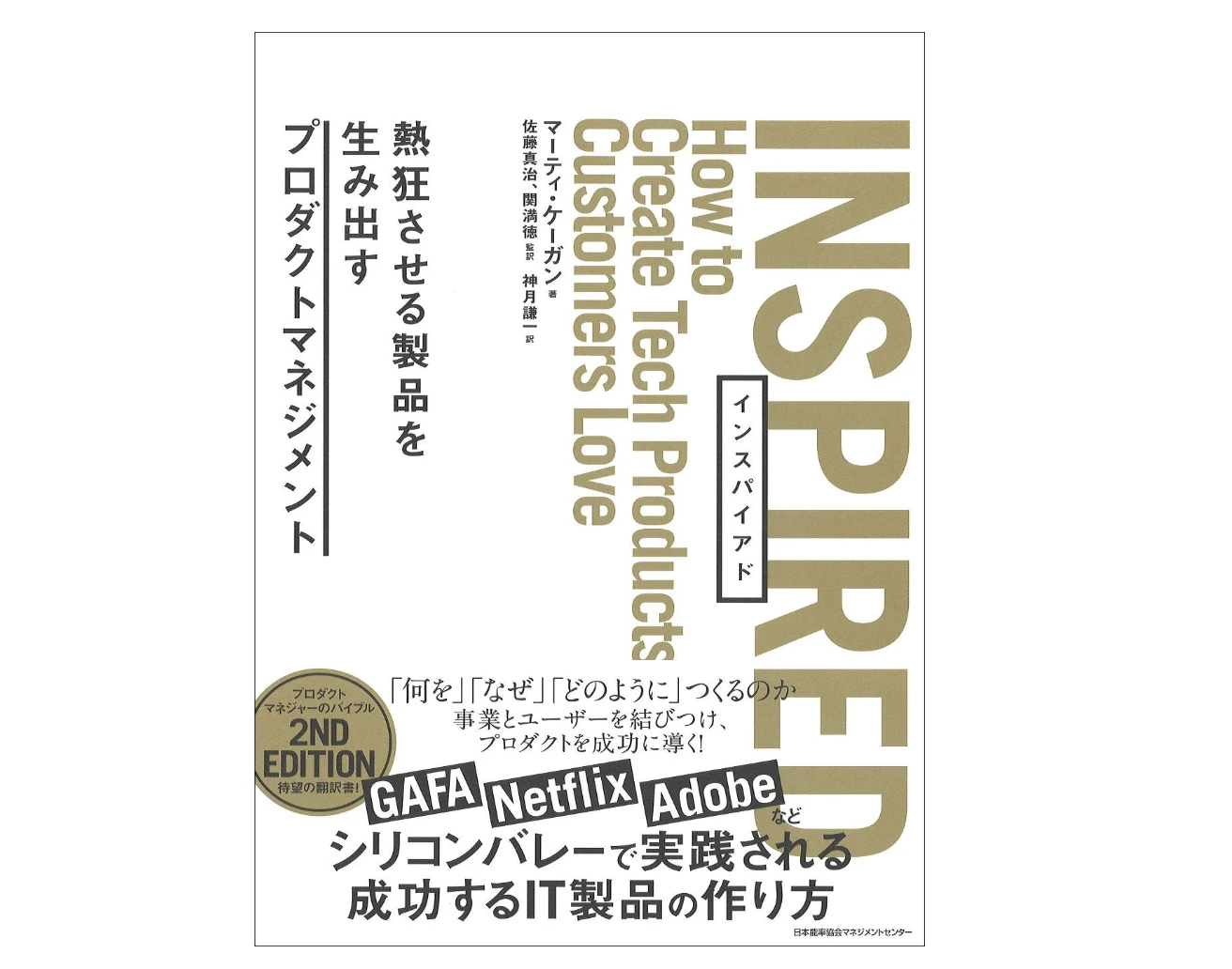
引用:INSPIRED 熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント(日本能率協会マネジメントセンター、著:マーティ・ケーガン、監修:佐藤 真治、関 満徳、訳:神月 謙一)
日本に足りないと言われている、シリコンバレーで行われているプロダクトマネジメントの手法を紹介している本です。
成功を収めている企業の事例を紹介しながら、成功する製品の開発に必要なプロダクトマネジメントについて詳細に描かれています。Adobe、Apple、BBC、Google、Microsoft、Netflixのプロダクトマネージャーが紹介されており、興味を持ちやすい一冊です。
プロダクトマネージャーは、IT業界ではWebサービスなどのソフトウェア製品の企画からライフサイクルの終焉までを見届ける事業の責任者となるポジションです。権限も責務も大きいため、エンジニアとして経験を積んだ先に目指せるキャリアとなります。
以下では、プロダクトマネージャーについてよくある質問とその回答をまとめました。本記事の内容とともにお役立てください。
プロダクトマネージャーは、企業の提供するプロダクトにおいて企画段階から製造、販売、マーケティングまでの事業の責任者となるポジションです。IT業界では、Webサービスやパッケージソフトウェアなどの継続的な開発とリリースを繰り返すプロダクトに対して置かれるポジションです。
名前の通り管理対象が異なります。プロダクトマネージャーはプロダクトの企画、製造、販売、運営、マーケティングなどを管理する責任者で、事業が続く限りプロダクトの改善と収益の最大化を目指す立場です。一方のプロジェクトマネージャーは、プロジェクトという有期の一事業における管理者といえます。
プロダクトマネージャーは業務範囲が広いため、幅広く知識とスキルが求められます。例として、下記があげられます。

この記事では、プロダクトマネージャーについて様々な面から紹介しました。Webサービスなどのプロダクトと事業の責任者となるプロダクトマネージャーは、エンジニアの目指すキャリアパスの一つの頂点といえます。
この記事を参考にプロダクトマネージャーについて理解し、自身のキャリアアップの参考にしてください。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く