40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
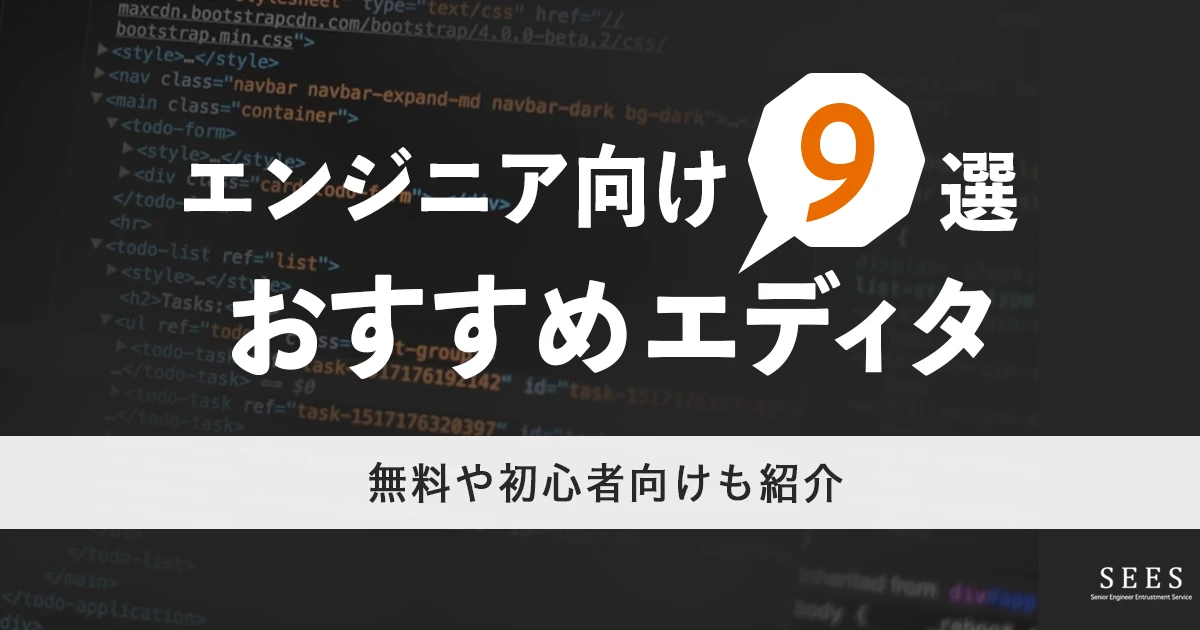
テキストエディタはテキストファイルなどを編集するためのソフトウェアです。ITエンジニアの業務では、プログラミング(コーディング)やデータの参照、加工などで使用します。本記事では業務を効率化できるおすすめのテキストエディタを紹介します。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
ITエンジニアの業務の中で、テキストファイルを編集する機会は多いものです。ログの参照やCSV、TSVなどのデータファイルの編集、シンプルな文章の作成などで利用したことのある方も多いのではないでしょうか。
また、プログラミングをする方は、コードエディタを使ってテキストファイルを編集している場合もあるかもしれません。
テキストエディタは、コンピューター上のテキストファイルを編集するためのソフトウェアです。Windowsに標準でついているメモ帳などもテキストエディタの一種ですが、より高機能なテキストエディタも存在しており、ITエンジニアの業務を効率的にするために活用できます。
本記事では、ITエンジニアの方に向けて、テキストエディタの主な機能の機能を解説し、おすすめのテキストエディタ、選定の基準などを紹介します。現在ご使用中のテキストエディタを見直す機会にご利用ください。
 テキストエディタとは、コンピューター上のテキストファイルなどのファイルを編集するためのソフトウェアです。GUIやCUIなど、OSの形式にあわせたインタフェースのテキストエディタがあります。
テキストエディタとは、コンピューター上のテキストファイルなどのファイルを編集するためのソフトウェアです。GUIやCUIなど、OSの形式にあわせたインタフェースのテキストエディタがあります。
「テキスト」エディタという名前から、文章の編集のみに利用できると思われるかもしれませんが、あくまでテキスト形式のファイルを編集できるソフトウェアのため、記述する内容は文章以外でも問題ありません。
軽量に動作するソフトウェアとして作られていることが多く、ちょっとした作業でファイルを編集する際に欠かせません。テキストエディタによっては高度な機能を持つ場合もあり、業務の効率化に活躍するツールといえます。
テキストエディタと似た言葉として、コードエディタがあります。テキストエディタ同様にITエンジニアの業務でよく利用されるツールです。こちらは「コード」、つまり各種のプログラムを作成するためのソフトウェアです。
プログラムを効率的に記述するための機能が搭載されていることが特徴ですが、テキストエディタとよく似ており、重複する機能も少なくありません。この二つのソフトウェアの境界は曖昧で、どちらの情報の扱いに特化しているかで名称が決まるともいえます。
本記事内では基本的に「テキストエディタ」および「コードエディタ」をあわせて、テキストエディタと呼称して扱います。
テキストエディタの主な機能を紹介します。これらの機能はすべてが必須というわけではなく、エディタによって搭載されている機能は異なります。
テキストエディタの最も基本的な機能は、様々な文章などの文字列を記述できることです。デバイスが対応している言語であれば、日本語や英語などでの記述に対応します。文章に限らず、文字の羅列であるデータやプログラムなども編集可能です。
テキストファイルなどのファイルを読み込んで表示し、編集した内容を保存する機能です。新規のファイルの保存やファイルの上書き保存も一般的な機能といえます。
テキストファイルのデータの読み込みには文字コードを指定し、保存の際にも文字コードを指定できる場合が多いです。これにより、テキストファイルなどの文字コードの変換にも利用できます。
テキストファイル内に特定の文字列が存在するかを検索します。ファイル内のキーワードのある位置までのカーソル移動や、マーカーをつけるなどテキストエディタによって結果は異なりますが、テキストファイルを効率的に扱ううえで欠かせない機能です。
また、置換は検索したキーワードを置き換える処理です。全置換処理機能で複数のキーワードを該当文字列を一度に変える処理はデータの編集やコードの修正ではよく利用します。
テキストエディタによっては検索・置換処理に正規表現を利用することもできます。正規表現は特定のパターンを文字列で表現する方法で、前方一致や特定文字の繰り返しなどに合致する文字列を検索することが可能です。使いこなせれば、強力なツールとなります。
テキストファイル内の特定文字列を強調表示する機能です。背景色を変える(マーカー)やアンダーバー、波線などで強調表示します。
検索したキーワードを強調表示する場合や特定のテンプレートを用いてパターンを指定して強調表示を行う場合もあります。コードエディタでは、特定のプログラミング言語ごとのテンプレートが用意されており、変数宣言や各種の予約語などを強調することでプログラミングをサポートしてくれます。
コードエディタの中には、入力補完機能を持つものもあります。サジェスト機能、自動補完機能、候補表示機能などと呼ぶ場合もあります。
エディタ上で途中までキーワードを入力すると、該当するキーワードの候補を選択することができます。検索エンジンのサジェスト機能と同様のイメージです。
特定の言語(英語など)やプログラミング言語などにおけるスペルのチェックを行う機能です。スペルが誤っていると思われる記述箇所に波線表示などを指定してくれるため、作業のミスを防ぐことに繋がります。
一行のデータが長い場合には、指定の文字数で折り返しての表示機能を使うと視認性が高まります。
エンジニアの業務の中では、特定の文字数で定義された固定長を利用する場合も多々あり、テキストエディタの表示で折り返しをすることにより、作業の効率化やミス防止に役立ちます。
エディタによって提供しているかどうかは異なりますが、複数のファイルを並列表示する機能も便利です。例えば、プログラムのコードが複数バージョンある場合は並べて見て確認したいことがあります。さらに差分表示機能を持っているエディタも存在します。
テキストエディタ上の特定の操作手順を覚えさせ、キーひとつで使えるマクロ機能もテキストエディタが提供していることの多い機能です。繰り返し行う作業をマクロとして登録することで、作業を簡易化することができます。例えば、データを3行ごとに必要なデータが記載されているファイルから不要行を消す作業などはマクロを使えば一種類の操作で実現できます。
テキストデータの各行の並べ替えを行う機能です。テキストデータの各行をデータの一覧として扱い、アルファベット順や番号順で並べることにより、簡易なデータ整理を実現できます。
ITエンジニアが業務内でテキストエディタを活用するシーンを確認しておきましょう。下記はあくまでも一例で、業務によっては別の利用法もあります。
プログラムコードを実際に記述する際にはテキストエディタやコードエディタ、あるいはIDEなどを利用することが一般的です。特に環境が揃っていない状況でもすぐに作業にかかることができるのが、テキストエディタです。IDEのように高度な機能は持っていませんが、動作が比較的軽く使いやすいため、コードエディタを愛用するエンジニアは珍しくありません。
ITエンジニアがアプリケーションやOS、ミドルウェアなどのログファイルを参照する際には、テキストエディタを使う場合も多いです。データ量が多いファイルにも対応し、折り返しや検索機能を使うことで該当箇所を見つけやすいため、内容確認を効率的に実現できます。
CSV(カンマ区切り)やTSV(タブ区切り)、固定長などのテキストデータのファイルはITシステムの入出力としてよく利用される形式です。これらの形式のファイルはあくまでテキストのため、テキストエディタで扱うことができます。テキストエディタは余計な処理がなく、正規表現による置換などを利用することで効率的にデータを加工することができます。
CSVやTSVはEXCELなどを利用して編集する場合もありますが、自動的な記号の変換などが発生する場合があり、ミスのもととなることがあります。テキストエディタとの使い分けをするとよいでしょう。
 テキストエディタを業務で活用するエンジニア職種としては、アプリケーションの開発を担当するエンジニアやインフラの構築や運用を行うエンジニアがあげられます。
テキストエディタを業務で活用するエンジニア職種としては、アプリケーションの開発を担当するエンジニアやインフラの構築や運用を行うエンジニアがあげられます。
アプリ開発のエンジニアの場合、コードエディタとして利用する機会があります。また、テストデータの編集、システム運用におけるログ参照でも利用するでしょう。
インフラの構築の構築、運用をするエンジニアもテキストエディタをよく利用します。サーバー上で実行するスクリプトの編集、設定ファイルの編集、サーバーログの確認などが利用シーンとなります。
また、あらゆるエンジニア職では設計書などのドキュメントやレポート作成も業務に含まれますが、このなかで記載する文章の下書きなどでもテキストエディタを利用する人もいます。
 エンジニアがテキストエディタを利用するメリットとして、業務の作業効率を向上させられることとミスの防止があげられます。コードやデータの編集を素早く行え、編集のミスを防ぐための手順もテキストエディタでは実施しやすいためです。
エンジニアがテキストエディタを利用するメリットとして、業務の作業効率を向上させられることとミスの防止があげられます。コードやデータの編集を素早く行え、編集のミスを防ぐための手順もテキストエディタでは実施しやすいためです。
テキストエディタの各種機能を用いてエンジニアの業務を効率的に行うことが可能です。コードの記述やデータの編集などの作業を行う際には、入力補完や正規表現を用いた置換などにより作業時間を大幅に短縮することができます。
エンジニアの作業はちょっとしたことの積み重ねです。少しずつしかない作業でも効率化することで、業務全体では作業時間の短縮、コストの削減などが実現できます。
テキストエディタを使うことで作業のミスを減らすことが可能です。例えば、ログファイルから特定の文字列を探す場合、人間の目視ではデータが大量な場合には見落としや見間違えが起こります。テキストエディタの検索機能を用いることで、これらを防ぐことができます。スペルミスなどの単純なミスの防止にも役立ちます。
 以下では、エンジニアが業務で利用するテキストエディタ、コードエディタのおすすめ製品を紹介します。各エディタには固有の優れた機能や適した用途などが存在するため、どのような業務で利用するかも想定して、選定の参考にしてください。
以下では、エンジニアが業務で利用するテキストエディタ、コードエディタのおすすめ製品を紹介します。各エディタには固有の優れた機能や適した用途などが存在するため、どのような業務で利用するかも想定して、選定の参考にしてください。
サクラエディタはMS Windows向けの日本語テキストエディタです。オープンソースで無料で利用することができます。
動作は軽く、テキストエディタとしての主要機能を搭載しているため定番といえるほどの普及度合いで、初心者が使い始めるのにもおすすめです。1998年に開発が始まり、現在はGitHubにて有志による開発が続いています。
秀丸エディタは有限会社サイトー企画によるWindows向けのテキストエディタです。シェアウェアとして提供されているため、問題発生時のサポートも存在します。
テキストエディタとしての一般的な機能をすべて備えており、ユーザーも非常に多いです。また、関連の秀丸シリーズのソフトとあわせて利用しやすくなっています。
Visual Studio CodeはMicrosoft社の提供するコードエディタです。Windows、Linux、MacOSに対応しており、無料で利用できます。
Microsoft社の統合開発環境(IDE)であるVisual Studioの名前がついている通り、プログラム開発に適しており、多数のプログラミング言語に対応しています。また、コンパイルや実行環境との連動など開発に便利な機能も多数備えていますが、動作は軽量です。拡張機能も充実しており、追加することでより利便性を高めることができます。
Stack Overflowの開発者に向けた調査(2024年)でも、最も多くの開発者が利用する開発環境という結果が発表されています。
Sublime TextはSublime HQ Pty Ltdの提供するテキストエディタ、コードエディタです。シェアウェアですが、無料で試用することが可能です。Windows、Linux、MacOSの各環境で利用できます。
各種の言語でのプログラミングに対応しており、第三者によるプラグインでの拡張も多数提供されています。また、独自の機能として複数個所を選択しての編集、エディタ内でのコードの実行、自動保存などの機能も持ちます。
Bracketsはオープンソースのコードエディタです。アドビ社により開発され、サポート終了後はコミュニティによって開発が続いています。
Windows、Linux、MacOSに対応しており、HTML、CSS、JavaScriptによって作られています。さまざまな言語に対応していますが、特にWeb(HTML、CSS)画面の作成、デザインで人気のあるエディタです。
TerapadはWindows環境向けのシンプルな日本語テキストエディタです。長い歴史を持ち知名度も高いですが、近年(2023/9)でも更新が行われています。TpChatGPTというChatGPTへの連携機能も拡張機能として提供されています。
VimはUNIX系ではお馴染みのviから派生したテキストエディタです。UNIX、Linux、Windowsなどに対応していますが、特にLinux上で利用される機会の多いエディタ―です。CUIで動作することが大きな特徴ですが、GUI版も存在しています。
Notopad++はWindwos上で動作するオープンソースのテキストエディタです。シンプルで軽量ながら、拡張も可能なため人気のソフトウェアです。
コーディングにも適しており、シンタックスハイライト(強調表示)の見やすさなどが評価されています。
WebStormはJetBrain社の提供するJavaScript、TypeScriptおよびHTML、CSSなどのWeb開発に適したエディタです。プラグインによる拡張機能も多数用意され、AIによるサポート機能などもあります。
 本記事で紹介しているテキストエディタ、コードエディタは数ある中のほんの一部です。これらの多数のエディタの中から、利用するエディタを選定する際のポイントを紹介します。
本記事で紹介しているテキストエディタ、コードエディタは数ある中のほんの一部です。これらの多数のエディタの中から、利用するエディタを選定する際のポイントを紹介します。
もちろん、最終的には利用者が納得できることが一番の基準となります。試しに使ってみる理由として参考にしてください。
エディタをどのような用途で利用するかは先に確認しておきたいポイントです。文章を書くため、コードを書くため、データの加工など用途を絞ることで、適したエディタを選びやすくなります。
エディタに期待する特定の機能が存在する場合には、選ぶ基準の一つとなります。コード記述のための入力補完や、正規表現を用いた強力な検索機能などはすべてのエディタに備えられているわけではありません。特定の機能を持っているかは、確認すべきポイントです。
どのような環境で利用する予定かも確認が必要なポイントです。Windows、Linux、MacOSといったOSや、GUI/CUIなどエディタごとの利用できる環境を押さえておきましょう。
見やすいことも重要なポイントです。テキストエディタやコードエディタを業務上で利用する場合、長い時間見ることになるため目の疲れづらさも大切です。
エディタによってはテーマの切替などを持っている場合もあるため、試して確認するのがよいかもしれません。
テキストエディタに多くの人が求めるのは軽量で快適に動作することです。こちらに関しても、各エディタを試してみるか、他者の評判などから確認するのがよいでしょう。
扱いやすい、操作しやすいことも重要なポイントです。実際に触ってみないとわからない部分のため、試用版などで試してみるとよいです。
もし機能や視認性などに問題があったとしても、カスタマイズによりカバーできることもあります。拡張機能が提供されている場合や、自分で設定することで利用しやすくできるカスタマイズ性能も選定のポイントにあげられます。
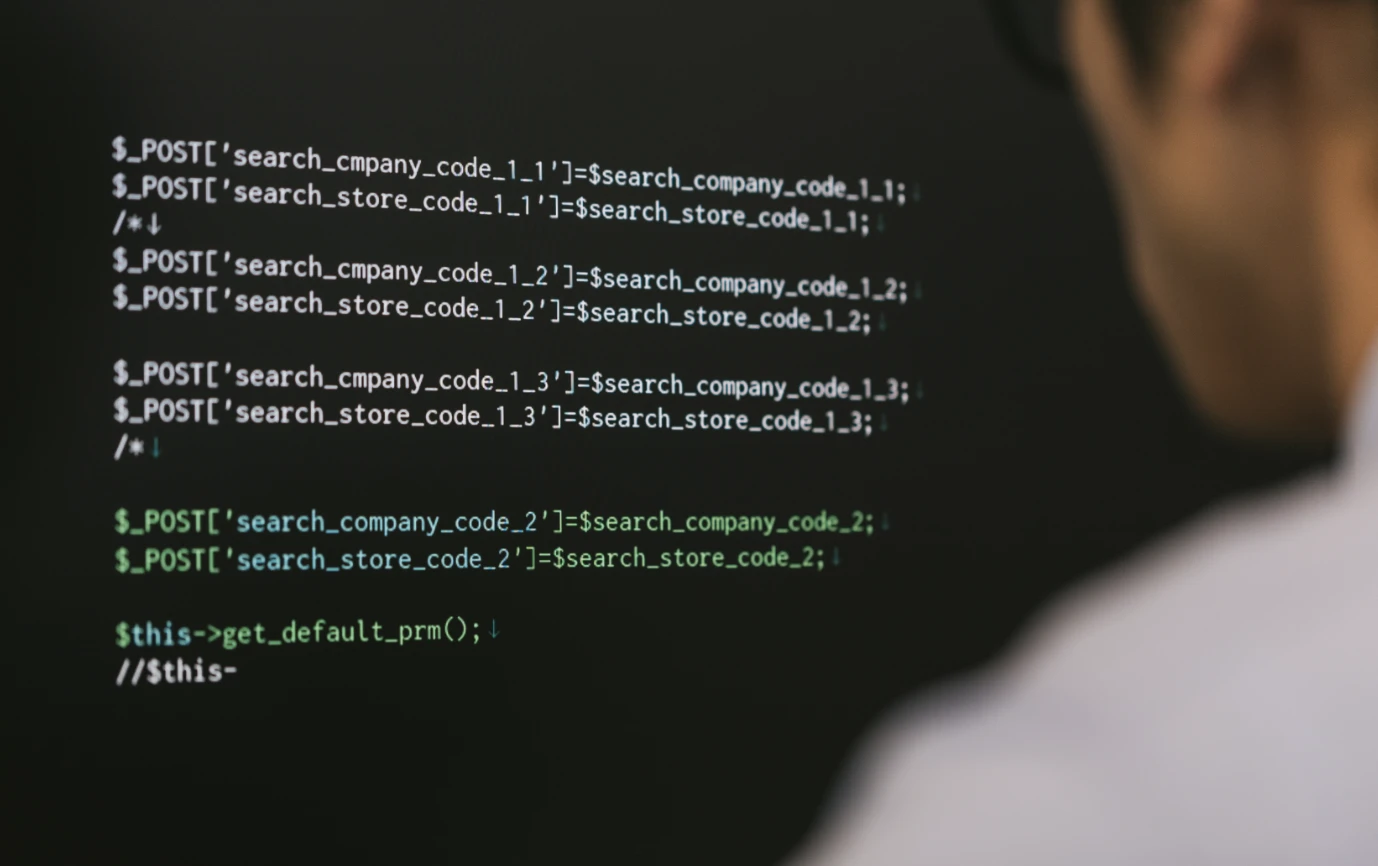 テキストエディタやコードエディタと比較されるソフトウェアにIDE(統合開発環境)があります。それでは、エンジニアはテキストエディタとIDEどちらを業務で使うべきなのでしょうか。
テキストエディタやコードエディタと比較されるソフトウェアにIDE(統合開発環境)があります。それでは、エンジニアはテキストエディタとIDEどちらを業務で使うべきなのでしょうか。
結論から言えば、自分の使いやすいツールを使うのがベストです。IDEの高機能なサポートが必要という人も、テキストエディタの軽量な点が使いやすいという人もいます。プロジェクト上のルールとして定められていなければ、自分が高い生産性を出せるツールを使うことが重要です。
また、コード記述以外の利用においてはテキストエディタの方が便利なことが多いです。
IDEはソフトウェア開発に最適化されたツールで、コードの編集機能、コンパイル機能、実行機能などを兼ね備えています。効率的なソフトウェア開発を実現する目的で、開発現場で導入していることが一般的です。
代表的な製品として下記などがあげられます。
おすすめのテキストエディタについて、よくある質問と回答を紹介します。
テキストエディタの持つ機能やおすすめの理由、選び方などを押さえて、新たなエディタを使ってみましょう。
テキストエディタでは、テキストファイルの編集が可能です。テキストファイル内には文章やプログラム、データなどを記述できます。
より高度な機能を持ったソフトウェア製品もありますが、軽量で気軽に使えることがテキストエディタの魅力といえます。
プログラム作成は、IDEやテキストエディタ、コードエディタなどを利用して行うことができます。IDEは高度な機能を提供していますが、その分利用環境に求めるスペックが高いというデメリットもあります。テキストエディタ、コードエディタは軽量なソフトウェアのため様々な環境で動かすことが可能です。
エンジニアはプロジェクトで指定のツールがあればそれを使い、特に指定がなければ自分に合った方を選択すればよいです。
テキストエディタ選定の基準として、見やすさ、操作性、求める機能、利用予定の用途のサポートなどがあげられます。Web上で利用者の声を参考にすることも選定方法の一つです。また、無料で利用できるものも多く、試用版が提供されているケースもあるため自分の環境上で試してみることもおすすめです。
テキストエディタは幅広い用途で利用できます。エンジニアの業務の中でもテキストエディタを利用できるシーンは多数あり、使い方を工夫することで業務効率を高めることが可能です。また、ユーザーが手作業で行っていたことをテキストエディタの機能で実現すれば、人的ミスの防止にも繋がります。
エンジニアの方は、自分に合ったテキストエディタを見つけ、業務の効率化にお役立てください。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く