40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】
40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】

COBOLからJavaへの移行を検討している方へ。技術的な違いから移行のメリット・デメリット、主な手法や進め方、注意点、成功事例、保守運用のポイントまで、プロがわかりやすく丁寧に解説します。今後のIT戦略を見直すきっかけにも最適です。
<業界実績19年>
ミドル・シニアフリーランス専門
エージェントSEES


40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!
ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。
目次
近年、企業のIT部門では、レガシーシステムの移行が急務です。特に、長年にわたり業務を支えてきたCOBOLシステムの老朽化や保守の難しさが顕在化し、Javaへの移行が注目されています。
本記事では、COBOLからJavaへの移行の背景、メリット・デメリット、具体的な進め方について、実際の事例や専門家の見解を交えながら解説します。

COBOLは長年にわたって多くの業務システムを支えてきた実績がありますが、その存続には限界が見えてきました。
保守人材の減少やコストの増加、さらにはデジタル化の波に対応しきれないという課題が背景にあります。こうした状況下で、より柔軟かつ将来性のある言語への移行が求められているのです。
ここでは、COBOLを取り巻く現状と移行の必要性について詳しく解説します。
COBOLは1959年に登場して以来、主に金融、保険、公共機関などの基幹システムで利用されてきました。信頼性の高さと高速なバッチ処理性能は、業務の根幹を支えるうえで大きな強みでした。(参考:COBOL - Wikipedia)
しかし現在、その強みが課題に変わりつつあります。まず大きな問題は技術者不足です。COBOLを熟知したエンジニアは年々減少しており、新卒のIT人材がCOBOLに触れる機会もほとんどありません。
さらに、老朽化したシステムは柔軟な改修が難しく、他のITサービスとの連携やクラウド化にも対応しづらい構造になっています。結果として、セキュリティ上のリスクや、変更対応の遅れが顕著になっているのです。
これらの背景から、現行COBOLシステムを維持すること自体が、業務効率や競争力を損なう要因となっているケースが増えています。
COBOLの限界を受けて、代替となるモダンな開発環境へのニーズが急速に高まっています。なかでもJavaは、多くの企業が採用するオープンで汎用性の高い言語として、移行先の有力候補とされています。
まず、Javaはオブジェクト指向であり、大規模なシステムでも構造化しやすく保守性に優れています。
さらに、Spring FrameworkやApache Strutsといった高機能なライブラリが整っており、開発速度や拡張性が飛躍的に向上します。加えて、クラウドネイティブ開発との相性も良く、DX推進の中核を担う存在です。
これらの理由から、多くの企業がCOBOLからJavaへの移行を検討し、すでにプロジェクトを開始しているケースも増えています。(参考:三菱重工:COBOL資産をJava変換し脱ホストを実現|事例 | アクセンチュア)

COBOLからJavaへの移行を検討する際、両言語の特性を正しく理解しておくことは不可欠です。ここでは、以下3つの観点から解説します。
COBOLとJavaは、設計思想と用途がまったく異なります。COBOLは業務処理に特化し、自然言語に近い記述が可能な反面、柔軟性に欠ける場面も多くみられます。
一方のJavaは、オブジェクト指向による構造的なコード記述が可能で、複雑なアプリケーション開発にも対応可能です。
さらに、Javaは豊富なライブラリや開発支援ツールを活用することで、開発効率を向上させられます。COBOLが適しているのは安定した処理が求められるレガシー業務であり、Javaは頻繁な改修や拡張を前提としたシステムに適しています。
結果として、現代のビジネススピードに対応するうえでは、Javaの方が実用的といえるでしょう。
人材の確保は、言語選定のうえで深刻な課題の一つです。COBOLエンジニアの多くは高齢化しており、新たに人材を採用・育成することは難しい状況です。
IPAでも、2019年に基本情報技術者試験からCOBOLを廃止し、Pythonを新たに追加しています。(参考:IPA、基本情報技術者試験にPythonを追加/COBOLを廃止:アセンブリ言語は残る - @IT)
一方、Javaは大学の情報系学部や専門学校、さらにはオンライン講座などでも広く学習されており、国内外を問わず人材の多さが特徴です。そのため、プロジェクト立ち上げやメンテナンス体制の構築においても、Javaのほうが柔軟に対応できます。
将来的な保守運用を見据えるのであれば、エンジニアリソースの豊富さは大きなアドバンテージとなるでしょう。
COBOLのシステムは、一見すると長期間にわたって安定稼働する堅牢さが魅力ですが、その反面、保守や運用にかかるコストは年々増加しています。
主な要因は、専任技術者の人件費高騰と、老朽化したハードウェアの維持費用、さらにドキュメントの不足やコードのブラックボックス化です。トラブル時の対応に時間がかかり、ビジネスへの影響も小さくありません。
一方、Javaはオープンソースのツールやクラウドとの親和性が高く、ITインフラの柔軟な設計が可能です。開発や運用に関わるベンダーの選択肢も多く、価格競争が働きやすい環境にあります。
その結果、総保有コスト(TCO)の観点でも、Javaのほうが持続可能性の高い選択肢といえるでしょう。

COBOLシステムからJavaへと移行する際には、目的や予算、システムの規模によって最適な手法が異なります。代表的なアプローチとしては、「リライト(再構築)」「自動変換ツールの活用」「AIによるコード変換」の3つが挙げられます。
ここでは、それぞれの移行手法の概要と実務上のポイントについて詳しく解説します。
リライトとは、既存のCOBOL資産を一度解体し、業務要件を再整理したうえでJavaで新規に開発し直す手法です。
移行のなかでもっとも手間とコストがかかる方法ですが、再構築によりモダンなアーキテクチャの導入や将来的な拡張性の確保が可能になります。また、レガシーコードに依存していた部分を見直すことで、システム全体のパフォーマンス向上や保守性の改善にもつながります。
ただし、開発工程が増える分、スケジュールの長期化や要件のずれが起こるリスクもあるため、事前にPoC(概念実証)を実施してリスクを最小化することが推奨です。
自動変換ツールを使った手法は、COBOLの既存コードを専用ツールでJavaに変換し、構文やロジックの大枠を保持したまま新言語へ置き換える方法です。リライトに比べて期間やコストを抑えられる点が大きなメリットです。
例えば、「Chameleon」や「Fujitsu PROGRESSION」などが提供する商用ツールでは、コードの整形だけでなく、データベース定義やジョブスケジューラの変換まで対応しているものもあります。
ただし、変換されたJavaコードは機械的な処理結果のため、保守性や読みやすさが必ずしも理想的とはいえません。移行後のコードレビューやテスト工程が不可欠となります。
近年注目されているのが、AIを活用したCOBOLからJavaへの自動変換です。IBMの「watsonx Code Assistant」など、生成AIを活用したツールでは、従来の機械的な変換だけでなく、業務文脈を加味した構造的なコード生成が可能になりつつあります。
AIを用いることで、膨大なコードの解析・変換を高速かつ精度高く実行できるため、大規模案件や工数削減を求められるプロジェクトにおいて効果を発揮します。
しかし、現時点では万能ではなく、業務ロジックの完全な再現には限界もあるため、AI変換後のレビュー・検証体制の構築は必須です。技術の進展とともに、今後さらに実用性が増していくことが期待されています。
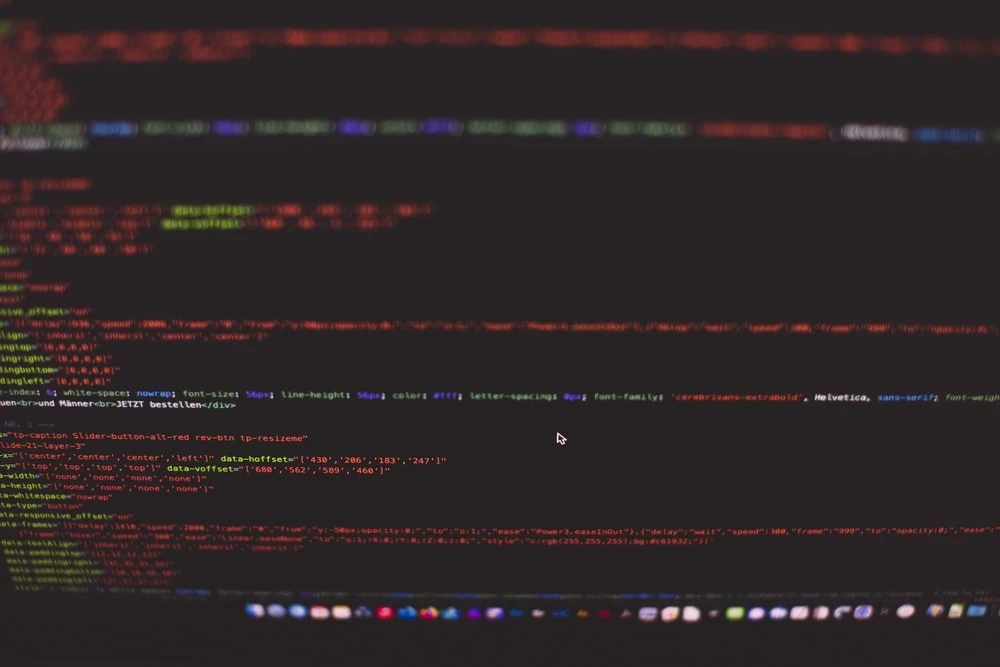
COBOLからJavaへの移行は、単なる言語の置き換えではなく、システム全体の構造を見直す大規模なプロジェクトとなります。
ここでは、プロジェクト開始から本番移行後までの各フェーズごとに、重要なポイントと注意点を具体的に解説していきます。
まず初めに必要なのが、既存COBOLシステムの徹底的な調査です。ソースコードの規模、依存関係、業務ロジック、バッチ処理の有無、連携システムの構成などを把握することが不可欠です。
特に、保守されていないコードやブラックボックス化した部分の存在は、移行リスクを高める要因となります。また、ドキュメントが不足している場合は、ソースから仕様を読み解くリバースエンジニアリングの実施も視野に入れましょう。
さらに、業務担当者やベテラン技術者へのヒアリングを通じて、暗黙知として残っている仕様や処理ロジックを洗い出すことが、成功の鍵となります。
調査結果を踏まえ、どのような移行方針をとるべきかを明確にしましょう。主な選択肢には、「全面リライト」「ツールによる自動変換」「ハイブリッドアプローチ」などがあり、それぞれメリット・デメリットがあります。
例えば、全面リライトは柔軟な設計が可能な一方で工数が大きくなりがちです。逆に、変換ツールを使えばスピードは上がるものの、生成されるコードの品質には再検討が必要になることもあります。
併せて、Javaによる再構築時に採用するアーキテクチャ(MVC、マイクロサービス、APIファーストなど)も検討し、将来的な保守性や拡張性を意識した構成にしていくことが求められます。
h3>PoC(概念実証)の実施
PoCは、移行方針が実際の業務要件を満たせるかどうかを小規模な環境で検証するプロセスです。部分的なコード変換や画面移行などを通じて、実行性能、コード品質、UI/UXなどの確認を行います。
PoCの段階で技術的な課題が判明することもあるため、移行方法やアーキテクチャを再評価するためにも欠かせない工程です。また、ステークホルダー(特に非技術部門)に向けてPoCの成果を提示することで、移行に対する理解と合意を得やすくなります。
プロジェクトの本格始動前にリスクを可視化できる点でも、PoCは重要な位置づけです。
PoCで得られた知見をもとに、移行対象の全体設計と本番スケジュールを策定し、いよいよ移行作業へと進みます。本番移行では、ダウンタイムを最小限に抑えるための切替戦略(段階移行、ビッグバン方式など)の選定や、ロールバック手順の準備も必要です。
また、移行後の検証では、処理結果の正確性はもちろん、パフォーマンス、セキュリティ、エラーハンドリングといった非機能要件の評価も欠かせません。
業務影響を抑えるためには、業務部門と密に連携し、ユーザーによる受け入れテスト(UAT)をしっかりと実施することも重要です。
COBOLからJavaへの移行では、単体テスト・結合テスト・システムテストといった段階的なテスト工程を重ねることが求められます。特にレガシーシステムは、テストケースが整備されていない場合も多いため、新たにテストシナリオを構築する必要があります。
また、COBOL時代にはなかったJava特有の問題(メモリリーク、例外処理、スレッド競合など)にも目を向けるべきです。加えて、コードレビューの体制やCI/CDパイプラインの整備によって、テストの自動化と品質管理を並行して進めていくと、長期的な運用にもつながります。
品質を担保することは、移行成功の最終ゴールを実現するうえで欠かせない工程です。

COBOLからJavaへ移行した後の運用・保守を成功させるためには、以下のポイントが大切です。
ここでは、移行後のポイントを解説します。
COBOLからJavaへ移行した後は、新たなシステムに適した保守体制を再構築する必要があります。Javaでは技術者の層が厚く、言語仕様もモダンなため、内製化や外注の体制も柔軟に組みやすくなるでしょう。
特に、モジュールごとの担当制を敷くことで対応スピードが向上し、変更にも柔軟に対応できます。また、保守業務の属人化を避けるため、設計書やコードのドキュメント整備、ナレッジ共有の仕組み作りも欠かせません。
業務知識と開発知識を持った人材の確保が、長期的な保守品質を左右するポイントになります。
Javaは汎用性の高い言語ですが、COBOLに比べると実行時のパフォーマンスに課題が出るケースもあります。そのため、移行後は必ずパフォーマンスチューニングを実施し、ボトルネックを洗いだす必要があります。
例えば、メモリ使用量やGC(ガーベジコレクション)の発生頻度、SQLクエリの最適化など、複数の観点でチューニング対象を絞り込みましょう。さらに、監視を高めるためのログ出力設計や、APM(アプリケーションパフォーマンス監視)ツールの活用も効果的です。
Javaへの移行はゴールではなく、新たなスタートです。移行後も、コードの品質維持や業務要件の変化に応じた改善を行う必要があります。そのためには、技術的負債を減らすためのリファクタリングや、設計の見直しを定期的に実施しましょう。
また、新機能の追加やUI/UXの向上も並行して進めることで、利用者にとって価値あるシステムへと成長していきます。こうした取り組みを可能にするには、アジャイル的な開発運用体制やCI/CDの導入も有効です。
コードの健全性を保ち、ビジネスのスピードに対応する体制を構築することが求められます。
Javaへの移行は、DX(デジタルトランスフォーメーション)実現に向けた大きな一歩です。
移行後のシステムはクラウド環境との親和性が高く、従来のオンプレミスに比べてスケーラビリティや柔軟性に優れています。これを活かすことで、災害対策、コスト削減、データ活用など幅広い改善が可能です。
また、SaaSやPaaSなど外部サービスとの連携も容易になるため、ビジネスの俊敏性が高まります。ただし、セキュリティやガバナンスへの配慮も忘れてはいけません。クラウド活用とDX推進はセットで検討し、経営とITが一体で動く体制づくりが鍵です。

COBOLシステムを今後も維持していくのは、技術的にも人的にもますます困難になっていきます。将来を見据えたJavaへの移行は、企業の安定と成長のために極めて有効な一手となるでしょう。
技術的ハードルはあるものの、適切な計画と体制を整えれば、移行は決して不可能ではありません。今こそ、レガシーから脱却し、柔軟で拡張性の高いシステムへの転換を前向きに検討するときです。
移行に踏み切ることで、DXやクラウド活用にもつながり、企業全体の競争力強化へとつながるでしょう。まずは現状の課題を正しくとらえ、一歩を踏みだすことが大切です。
40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』


40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。
SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。
エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。
転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。
SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。
会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。
給与の支払いサイトは30日で統一されています。
また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。
さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。
独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!
『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?
皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!


株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、
上記3項目においてNo.1を獲得ししております。


株式会社Miraie
2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。
監修者インフォメーション
目次を開く